アンソニー・ジャクソン(b)、サイモン・フィリップス(dr)とのザ・トリオ・プロジェクトや、エドマール・カスタネーダ(ラテン・ジャズ・ハープ)とのデュオなど、現代ジャズの最先端で世界屈指のプレイヤーと共演を繰り広げている上原ひろみ。最新作『
Spectrum』は、2009年の『
プレイス・トゥ・ビー』以来10年ぶりとなるソロ・ピアノ・アルバムだ。作品全体を貫くコンセプトは“色彩”。それも、シンプルなカラーリングではない。万華鏡のように刻々と変化するきらめき。真っ白な雪景色のなかで微かに浮かぶ濃淡。ブルーな音色が映し出す細やかな喜怒哀楽。言葉では描写できない繊細で豊かなイメージが、高度な作曲力と超絶的な演奏テクニックで見事に表現されている。
――本作のコンセプトはどこから思い付いたんですか?
「2017年にエドマールとのデュオ・アルバムを発表した後、次はひさしぶりにソロを出そうとまず決めました。自分の中で、最低でも10年に1枚ソロ・アルバムを作るというルールがあって、ピアニストである私自身の記録としても、そこはちゃんと残していきたいなと思っていました。それで、前作『
プレイス・トゥ・ビー』から10年で自分がいちばん成長できた部分はどこかとあらためて考えたとき、それは音色じゃないかという気がしたんですね」
――音のカラー、ですね。具体的にはどういった部分でしょう?
「ちょっとした音の響きのカラフルさとか、グラデーションの豊かさとか。要は、ピアノという楽器のコントロール力が上がったということだと思います。たとえば作曲をしていて、“ここに〈青っぽい〉音がほしい”と感じたとしますよね。そういうときに単純な色味だけでなくて、それが深くて鮮やかなブルーなのか、淡い水色なのか自然と意識して表現するようになったというか……」
――なるほど。
「色彩感だけじゃなく、音の強弱についてもそうですね。ピアニシモひとつ取っても、そこには柔らかいピアニシモや、軽やかなピアニシモ、コミカルなピアニシモ、哀しくせつないピアニシモなど、いろいろな表情がある。その弾き分けも、自分なりに細かくなった気がします。この10年、毎日ずっとピアノと向き合ってきたことで、パレットの上にある絵の具の数も増えたし。描きたいイメージも広がった。“色彩”をモチーフにした楽曲を並べることで、1枚のアルバムとしてその広がりも表現できたらと考えました」
――最初に生まれた楽曲はどれですか?
「かなり昔からモチーフを温めていた曲もありますが、曲として完成したという意味ではタイトル・ナンバーの〈スペクトラム〉ですね。この曲はアイディアが先にあったわけではなくて、メインのテーマになる旋律が頭にバッと浮かびました。そのメロディをどんどんリハーモナイズして、別のコード感や音域に置き換えたり、フレーズの形を微妙に変化させることで、同じ旋律でも違った音色で響くのが面白かったです」
――まさにスペクトラム、ですね。プリズムで分光された虹色の帯のように、主旋律が少しずつ色合いを変えながらシームレスに連なっていく感覚。
「はい。そうやって少しずつ変化していくプロセスを、ひとつの楽曲に仕上げました。このナンバーが完成したことで、1枚まるごと“色彩”をテーマにアルバムを作るという思い付きのアイディアが確信に変わったところはありましたね」

©Muga Miyahara
――指先のコントロール力では、1曲目の「カレイドスコープ」もすさまじいインパクトがありました。このナンバーでは、左手が4つの音を強く鳴らし続ける一方で、右手はその均等な拍を擦り抜けるように、一瞬も淀むことなく奔放なラインを描き続けます。
「コンセプトは“構築と破壊の共存”という感じです(笑)。左手はあえてエモーションを殺して、ひたすら機械的にパルスを打つ。一方の右手は、拍やリズムをまるで気にせず、感情の赴くままにひたすらパターンから逸れていく。そういった相反する要素を、ひとつの曲に同居させたかったんです。もしかすると自分のなかでは、機械への挑戦という意味合いもあったかもしれません」
――機械への挑戦、ですか?
「そう。マシンを使えばどんなビートも簡単に作ることができる今、生身のミュージシャンにしか表現できない“揺らぎ”みたいなものをピアノ1台でやってみようと。左と右の手にまったく違うルールが求められるので、正直、演奏の難易度はとびきり高くなります。だけどこの曲は、とにかく弾いていて楽しかった。レコーディングの時、長年ずっと一緒にやってきたエンジニアから“ひろみ、この曲はクレイジーだね。どうやって弾いてるのか皆目わからないよ”と呆れられましたが(笑)」
――アルバムのセルフ・ライナーノーツには、「視点を変えれば、広がる世界はどんどん変わる」と書かれています。演奏に即して言うと、これはどういうことですか?
「それこそ万華鏡を覗くような感覚で、正面から眺めていた対象をパッと横から見たり、裏側に回ったりということを、メロディに置き換えて試しています。たとえば右手のフレージングでは、バッハの対位法的な意味合いで、ある旋律のモチーフを部分的にひっくり返して弾いたりしてるんですね。ただこの曲ではそういう作り込みより、むしろ音が自分を未知の方に連れていってくれる感覚を大事にしているので。だからステージで演奏するたびに、右手から出てくるメロディは全然違うんですよ」
――この2曲にかぎらず、ひとつの楽曲内でテンポが自在に変化するのも、本作の大きな魅力だと感じました。こういう伸縮や緩急がフリーな感覚は、バンドではなかなか出しにくいものですか?
「どうでしょう。たとえばトリオ・プロジェクトで、同じことを再現すること自体は可能だと思います。アンソニーもサイモンも本当に素晴らしいプレイヤーですから。でもその場合はもう少し、フランク・ザッパっぽいサウンドになるというか(笑)。ガチッと構築された仕上がりになる気がします。だけどソロの場合はそうじゃない。もちろん、曲ごとに大まかなルールは設定していますが、アイディアがひらめいた瞬間、コード進行だってどこにでも行けますし。1曲の中で拍子やテンポを急に変えてもかまわない。そういう壮大な自由はありますね。もちろんその逆もまた真なり、なんですけれど」
――逆も真なり、と言いますと?
「バンドの場合、もし自分が演奏の途中でインスピレーションに詰まったとしても、仲間が助け船を出してくれたり、あるいは彼らのフレーズからある要素をさっと借りてきて自分なりに展開させたり、いろんな打開策がありえるんですね。でもソロの場合は頼れる人は誰もいないし。何が起きても自分1人で事態を収拾しなきゃいけない。そこは表裏一体なのかなと」
――つまり上原さんにとってソロ・ピアノとバンドやデュオによる活動とは、ピアニストとして“車の両輪”みたいなものなのでしょうか?
「そうですね。バンドで学んだことをソロの演奏に応用し、ソロで得たものをバンドのアンサンブルに生かす。循環の面白さはあると思います。たとえばソロの場合、バンドに比べてピアノの左半分を弾く絶対量が増えるんですね。単純な話、自分がベーシストとして、ずっと低音部も担当しなければいけないので。左手の活躍度はいつも以上に高くなる。同時に、ドラマー不在だからこそ自分がしっかりリズムをキープしなきゃという意識も強くなります。そうやって1人でリズム・セクションもこなさなきゃいけないとき、どういうベースラインを紡ぎ、どんなグルーヴを生み出していくのか。その引き出しの部分では、アンソニーやサイモンとのトリオ・プロジェクトで培ってきたものはすごく役立っていると思います」

©Muga Miyahara
――自在なテンポ・チェンジでいうと、チャップリンに捧げた「ミスター・C.C.」も印象的でした。往年のラグタイムを思わせるこの曲では、パートによってチョコマカと小走りしたり、ときに蹴躓いたり気取ったりと、“喜劇王”のさまざまな表情が浮かんできます。
「この曲のモチーフはかなり古くて、私がバークリーに留学していた頃、古いサイレント映画にアドリブで曲を乗せる遊びをよくやっていたんですね。なかでもチャップリンの動きが、私のピアノと相性抜群で……。勝手に親近感を抱いていました(笑)。何だろう……彼はいわば、モノクロの世界でも色彩を表現できる人だと思うんですよ。ピアノもそれと似ているでしょう。白と黒の鍵盤から、無限の音色が生まれてきますので」
――たしかに。本作『Spectrum』のテーマそのものですね。
「それもあって今回、あらためてチャップリンに捧げる曲をひとつ書き下ろすことにしました。実際の演奏では、スクリーン上を彼が走ったり蹴躓いたりしているのを想像しつつ、リズムやテンポをいろいろと変えています。これも冒頭はストライドっぽいリズムから始めて、途中で3拍子に行って……みたいな大まかなシナリオはありますが、あいだあいだでは即興のパートもかなり多い。こういうのを自由にできるのもソロ・ピアノならではですね。ちなみにこの曲を流しながらYouTubeでチャップリンの動画を再生すると、どの映像でも不思議とぴったりハマるんですよ(笑)」
――レコーディングは今年2月。米カリフォルニア州の「スカイウォーカー・サウンド」で3日間で録ったそうですね。これはどういう場所なんですか?
「ジョージ・ルーカスさん所有のスタジオで、本来はオーケストラ編成で映画音楽をレコーディングするための設備なんです。室内に巨大スクリーンがあり、巨匠ジョン・ウィリアムズさんが映像を見ながら『スター・ウォーズ』のサウンドトラックを指揮した場所でもある。私は公開日の午前0時に劇場に駆け付ける猛烈な『スター・ウォーズ』ファンなので(笑)。個人的にもすごく感慨深かったです。今回はぜいたくにも、その巨大なスタジオにピアノを1台だけ置いてレコーディングをさせていただきました」

©Muga Miyahara
――実際に録ってみた感触はいかがでしたか?
「とにかく音が素晴らしかった。もともと映画のオケ用に考えられた場所なので、広いだけでなく天井もすごく高いんですね。だからピアノを弾いていると、恵みの音が上から降ってくるような感じで……。ソロをレコーディングする場合、ピアノがきれいに鳴る場所で録るというのは絶対条件。気持ちよければ気持ちいいほど、やっぱり演奏への集中力も高まりますので。その意味では文字どおり最高の環境でした」
――音色の豊かさを届けるという本作の趣旨には、まさに最高の場所ですね。
「本当にそう思います。トリオやデュオと違ってピアノ・ソロ作品では、自分が奏でた音のすべてが聴き手にしっかりと届きます。本当に微かなピアニシモから、旋律のディテール、倍音の響かせ方まで、逃げ隠れはいっさいできない。演者にとってはそこが怖いところであり、同時に、面白さでもあります。アルバムが完成してあらためて思うのは、ピアノをいっぱい弾けて嬉しかったということ(笑)。誰よりも私自身が、その音色と響きを余すところなく聴けた気がします。ピアノって最高だなって、心から思えたレコーディングでした」
取材・文/大谷隆之

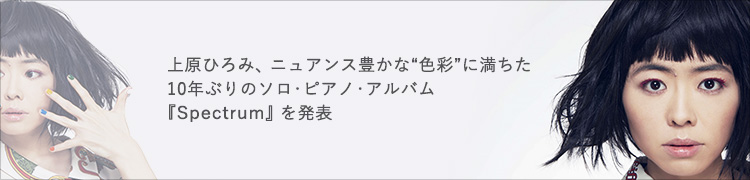





 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。