毎日の生活に気軽にアートを取り入れてほしい。そんな願いから
“Photographers Art Japan” というサイトがオープンしました。国内屈指の写真家を紹介し、厳選された珠玉のアート写真を販売する新しい形のWebサイトで、音楽ファン垂涎の写真を、オリジナルプリントで、リビング、自室、エントランスなどお好みの空間に飾って楽しむことができるようになります。
その第1弾として、ローリング・ストーンズのオフィシャル・フォトグラファーとして著名な有賀幹夫作品の中からストーンズの写真を販売開始。これを記念し、先日、原宿のJOINT HARAJUKUで写真展も開かれましたが、そんな有賀に元CDジャーナル編集長で“非メイン・ストリートのビートルズやくざ者”藤本国彦がインタビューを敢行。ストーンズとの出会いから、撮影の裏話までたっぷり話をおうかがいしました。今回はその前編をお送りします。
撮影: 清藤耕一
――そもそも、ローリング・ストーンズを初めて聴いたのはいつ頃でしたか?
「〈悲しみのアンジー〉(73年)が流行っていた時、僕は中一でしたが、ラジオで聴いて、“なんていい曲だ!”と思いました。今みたいなネット時代じゃないし、テレビでストーンズがしょっちゅう見れるわけでもない。それで『ミュージック・ライフ』を見てみたら、“汚なかっこいい”みたいなメンバーたちの佇まいで、〈アンジー〉を聴いたイメージとは真逆だったんで驚きました」
「それで逆にハマったというか、こんな世界があるんだ、と。ビートルズも好きだったけど、解散してベスト盤の『赤盤』『青盤』が出た頃で、メンバーがソロを出せばみんなナンバー・ワン。いわば“振り返りの一発目”の時期だったわけ。だから当然のようにビートルズも好きになりました。ただストーンズはバリバリ現役で、新曲を聴いて、それがたまたま〈アンジー〉だったわけだけど、ルックス見たら“えー!”みたいなさ(笑)。なんていうのかな、“一見さんお断り”みたいなイメージなのに、ああいうキャッチーな曲を出して、ちゃんとヒットさせて、日本のラジオでもかかる。それがすごいなと思って、すぐにハマりました。
VIDEO
その曲が入ってる『山羊の頭のスープ』(73年)はドローンとした感じで、むしろその当時は――この話すると長いんだけどさ(笑)――、ハードロックにプログレ、演奏のテクニックがうまくて起承転結がはっきりとした曲が日本では人気が高かった。イエスとかパープルとか、来日もしたバンドはとくに人気が上がるんですよ。だから、そういうロック好きからは、ストーンズはちょっとバカにされてたイメージがありました。“ギミック・バンドでしょ?”みたいな。へただし、レコードの音は悪いし、みたいな評価で。そこで僕は燃えたんです(笑)。万人受けじゃないけど、ヒットをちゃんと出し、存在感を示すっていうのは、ちょっとねじれているしそこがかっこいい、と思ったんです。その存在感にもすごくハマったのが最初のきっかけ、ということですね。もちろん73年初頭の幻の初来日公演は、多くのファンがチケットを求めて徹夜で並んだわけで、その世代より僕は少し下だったので、あくまでも僕が13歳でストーンズにはまった時の僕のまわりでは、という事ですが。
それでストーンズは『メイン・ストリートのならず者』(72年)で終わったとか、〈ミス・ユー〉(78年)なんかディスコでダメだ、とか言いきる人いますよね。でも僕から言わせると、〈アンジー〉を聴いてハマった13歳がここにいるだろ、と。昔僕より5歳くらい年上の人に“有賀くんってストーンズは何から入ったの?”って訊かれて〈アンジー〉って答えたら、大笑いされたことがあるんですよ。その人は全共闘の時代、学生運動の時代の人で、実際相当活動されていたらしい(笑)。そうすると、〈ストリート・ファイティング・マン〉(68年)とかさ、バリケードを突破っていう時に、ストーンズのそういうラジカルな曲が鳴り響いていたわけで、〈アンジー〉が出た時に、“あんな軟弱な売れ線狙いを出すんだったら、ストーンズはもう終わった”って、むしろ離れたって言うわけですよ。だけどそこがストーンズのクレバーなところだと僕は思っていて。73年には学生運動は世界的に鎮静化して、シラケの時代になり、内向的なシンガー・ソングライターが流行っていた。そこにストーンズは〈アンジー〉をシングル盤で出して、ラジオでかかり、それまでストーンズを知らない13歳がキャッチしたわけじゃないですか?
VIDEO
そうなると、〈ミス・ユー〉だって同じで。“君、どこからストーンズ入ったの?”って僕より若いやつに訊いて、〈ミス・ユー〉ですって言われたら、今度は僕が、“いやストーンズはそれじゃないんだよね~”って言いたくなる(笑)。その時々の13歳を惹きつけるような、ラジオでかかるような曲をちゃんと時流に合わせて出してきて、そうやってずっと転がってきたんだよね。
だからディスコを出したからダメだっていうのはむしろ反対で、そこを評価しなくちゃいけないと僕は思っているんです。〈ミス・ユー〉も、“ド”ディスコではないし、どこかいなたいブルースチックな匂いがちゃんとあるわけじゃないですか。それで世界中で大ヒットしたわけだから。だから短絡的に『メイン・ストリートのならず者』で終わったとか言うのはおかしいぞ、と。〈スタート・ミー・アップ〉(81年)くらいまではシングル曲でその時々の13歳を惹きつけたよね。その後、日本では83年に公開された81年USツアーの映画見てハマった、と言うファンも多い。そしてついに初来日、と言う流れですね~」
VIDEO
――さすがの見立てですね。ストーンズは、60年代に解散したビートルズとは存在感がまた全然違いますよね。
「『プリーズ・プリーズ・ミー』から『アビイ・ロード』までの7、8年の完結度がビートルズのすべてですよね。進化がすごい。ストーンズはそのたびごとに意匠を変えていくのがうまいバンド。ビートルズは“サイケデリック”まではものすごい勢いでやったけど、ストーンズと共通の音楽を目指そうっていう時に解散に向かってしまいましたからね、『レット・イット・ビー』のころ。そこでストーンズの、“ルーツは俺たち得意だよ”という存在感をグッと見せちゃったから、あのへんでストーンズもビートルズの影響下から逃れられたとも思うね」
――雑食性というか、何でも取り入れて自分たちの音にするのがストーンズだと。
「自分たち流に変えていく、っていうか。“結構簡単にやれるんじゃないの、俺たちももともとルーツだったんだから”みたいな感じで」
――60年代の先頭にいて、音楽や文化を牽引していたビートルズが、ザ・バンドをはじめ、周りの影響を取り入れるようになってきたと。
「そうそう、みんなザ・バンド・フィーバーにかかったよね。ハンブル・パイも最初はそうだった」
――有賀さんがカメラマンになりたいと思ったのは、いつ頃ですか?
「大学は日芸(日本大学芸術学部)のデザイン学科だったけど、超落ちこぼれで。でも大学2年の時に、ジョン・レノンが暗殺されて、ボーッとして日本で大学生活をしていると、“地球上のどこかにいる、そういう偉大な人もこんな形で亡くなっちゃうんだ”みたいなショックがあって。そして80年にRCサクセションが〈ニューイヤー・ロック・フェスティバル〉に出たのをテレビで観て、衝撃を受けた。こんなにかっこいいロック・バンドがいるのかと。フォーク時代のRCは全然知らなかった。僕くらいの世代だと、日比谷野外音楽堂の100円コンサートに行った人はいるけど、僕はそれも知らなかった。でも四人囃子、サディスティック・ミカ・バンド、キャロルは好きでした。よく読んでた『音楽専科』でも四人囃子は大きく取り上げられていてね。
で、僕はRCが新人バンドだと思ってテレビで観た。その時に、こんなにかっこいいロック・バンドが日本でも登場するんだったら、食えるか食えないかは置いといて、カメラマンとしてやっていきたいなと思ったんです。キャロルも最高にかっこいいけど、それを見てカメラマンになりたいと思う歳じゃなかったから、RCのおかげですね。それくらいRCに希望を見た。さっきも言ったように、ねじれたストーンズの魅力にも感動しているわけじゃないですか。そうすると、“日本で本当にクレバーなバンドとか音楽家っているのかな?”って。ストーンズはさ、70年代まではファンはミック・ジャガーもキース・リチャーズもバカだと思わされていたところがあるよね。その後、80年代になって、どうもミックはインテリで、ツアー前はジョギングしているらしいぞ、と次第にわかってきた。キースも『トーク・イズ・チープ』を出したあたりでこんなにクレバーな人だったのか!?って。RCもどこか知的な匂い、意識的にやんちゃなパフォーマンスをやってる印象があって本当に好きになりましたね」
――それまではミックもキースもジャンキーのイメージでしたもんね。
「悪ガキがたまたまいい感じに転がっちゃったくらいのイメージを持たれていたけど、本当は大クレバーだったわけですよ。そういうバンドは日本にはなかったと思う。でもRCを観て、“えっ、この人たちはもしかして?”みたいなのがあった。それとストーンズのイメージも取り入れつつ、清志郎さんの歌唱スタイルはミックと真逆じゃないですか。ミックはもごもごして何歌っているのかよくわかんないよねって海外の人も言うくらいで。〈ジャンピン・ジャック・フラッシュ〉の歌詞を聴きとれ~っていうアメリカのコメディー映画の題材にもなるくらいですから。一説によると、そうやって聴きとりにくいほうが実際にレコードを買って何回も聴くだろ、という理由らしいけど(笑)」
――それは頭がいい(笑)。
「でも(忌野)清志郎さんは真逆で、一音一音がちゃんと聴こえる。その歌詞も素晴らしくてね。だけど、ストーンズのイメージを完全に踏襲している。だからRCをTVで観たのがきっかけでカメラを始めたんです。でも日本人カメラマンのことは全然知らなかったし、目標にしたい人とかはいなかったんですよね」
――知らないのがよかった、ということですね。
「そう、怖いものなしの感じ。ストーンズを撮れたのも、業界の常識を知らなかったから。年功序列感とか、こうやってこうやったら次のポジションに行けるかな、とかやっていても多分ストーンズは撮れないですよ。突撃かまして、常識ある人だったらやれない動きをしたら、ストーンズの目に留まったというところがある。べつに、レコード会社から仕事をいただいて、ストーンズを撮ったら、ストーンズが気に入ってくれた、とかじゃないから」
――あとは運と縁で。
「はい。それと90年の初来日公演の時に僕はストーンズのオフィシャル・フォトグラファーにスタッフとして選ばれたんだけど、その前に、ミックが88年にソロで来た時にも、日本人カメラマンを採用しようかっていう話があったらしい。ストーンズって、その国のカメラマンがオフィシャルをやるというセオリーみたいなのが昔からあったんです。今はデジカメだから関係ないけど、確かにそのほうが都合はいいんですよ。たとえばアメリカ・ツアーにオフィシャルで付いたフランス人のカメラマンに“プロラボ行って現像してきて”って言ってもどこに行けばいいのかわかんないでしょ、っていうことだと思うんだけど。当時の撮影はすべてフィルムだから、その国のプロがその国のプロ用のフィルム現像所事情を一番知っているわけ。
だからミックの日本公演の時も、レコード会社側で何人かの大物日本人写真家のリストや作品を先方に送ったらしい。ただしミックにとってこれは初のソロ・コンサートだったから、結局ボブ・ディランの『欲望』のジャケットを撮ったケン・レーガンという大物を連れてきた。映像を手がけたのは、ビートルズの『レット・イット・ビー』を撮ったマイケル・リンゼイ=ホッグ。フジテレビで放送された番組は彼が監督したんです。つまり冒険はおかさずに旧知の大物スタッフを海外から連れてきたわけ。90年のストーンズ初来日でも、同じように慎重にいくべきなんじゃないかっていうふうに思うかもしれないけど、ストーンズ側はその前のアメリカ・ツアーを大成功させてたから、もうその時点で上がりというか、余裕なわけ。それで、日本人のカメラマンを使おうと冒険してくれたんでしょうね」
©Mikio Ariga
――なるほど。
「そういうことがあって、その前に動きまわっていた僕が彼らの目に留まって、“あいつにやらせてみよう”っていうことになった」
――実際、90年の〈スティール・ホイールズ・ツアー〉は、最初から最後までフルで撮れたんですか?
「もちろん。今もオフィシャルは全曲です。海外に行くとプレス扱いで2曲だけだけど。イギリスでは、イギリス人がオフィシャルとして撮るから、フォト・パスは出してくれるけど、2曲ですよっていうのが昔からの決まりです」
――撮影の前には、どんなふうに撮ろうとか、有賀さんなりの心構えはあるんですか?
「ありますね。ここ10年、ストーンズは、アルバムを出さないでランダムに大中小の会場でのツアーが続いているじゃないですか。2012年の50周年ツアーからベスト・アルバムを出して、2016年は『ブルー&ロンサム』っていうブルースのカヴァー・アルバムだけど、それまではオリジナル・アルバムを出して夏からアメリカ・ツアーが始まって年末まで、翌年の2、3月に日本、オーストラリア、もしくはブラジル、夏はヨーロッパ・ツアーっていう2年がかりのツアーで、一つのアルバムのツアーをやりきるっていうのが長年にわたる基本的なスタイルで。
僕が初めてストーンズを撮れた〈スティール・ホイールズ・ツアー〉は、スタッフも含め再集結し直しての新たなるツアーとなった。ツアー・プロモーターが以前とは違うっていうのも大きな理由だけど、そういうのもあって、アメリカ・ツアーに何回か行って、それでここが撮影の狙い目だなっていうのを自分で計算し、それで翌年日本に来たらここがポイントだな、っていうところはキッチリ撮ろうと。
今は体勢が変わったけど、ミックのアシスタントと、キースのマネージャーがすべての写真のチェックをするんですよ。ミックのアシスタントが、ミックとチャーリーとビル(・ワイマン)だったかな。キースのマネージャーがキースとロン(・ウッド)をチェックする。90年の〈2000光年のかなたに〉の演奏前にミックが“ひとり演劇ダンス”みたいなのをやったんです、パフォーマンス、パントマイムを。でも、ストーンズのスタッフ側は、ランダムにまんべんなく良い写真を全部オッケーを出してくれるわけじゃなくて、このツアーで彼らがここを強調したいっていう写真ばっかり拾うんです。たとえば僕が“この写真、良いと思うんですけど”と言うと、“アメリカ・ツアーでこういう写真はいっぱい撮ってすでに持ってるるからいいや”みたいな。だからこっちも、先の先を読む。オッケーカットを一枚でも多く出したいじゃないですか。
そういうふうにやってきたから、事前に相当考えましたよ。つまり、メンバーをかっこよく撮るのと同時に、ツアーのテーマを1枚で表現するような写真はかならず撮らないといけない。“こいつやっぱり印象的な写真を撮るな”と向こうに思わせたいから。こっちもさらに深堀るっていうか、深読みをしたりします。でも、たいてい読みは当たるので楽しかったですね。やっぱり、それだけ僕はストーンズが好きだから」
(つづきます)
有賀 幹夫
80年代半ばより音楽フィールドを中心に活動を始め、RCサクセション、ザ・ブルーハーツ、浅川マキなどを撮影。1990年、ザ・ローリング・ストーンズ初来日にあたりオフィシャル・フォトグラファーとして採用され、以降2014年までのすべての来日公演を撮影する。これらの写真はバンド制作物に多数使用され、2019年に日本でも開催されたザ・ローリング・ストーンズ展〈Exhibitionism〉では唯一の日本人クリエイターとして作品提供者に名を刻む。
https://www.facebook.com/mikio.ariga 取材・文/藤本国彦

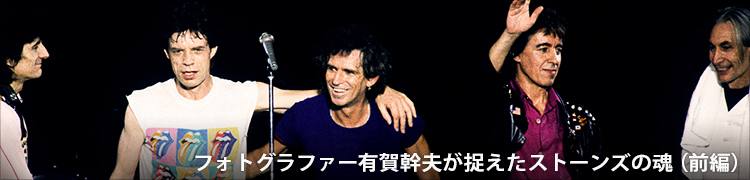




 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。