洋楽のロックやポップスの名曲をクラシックのテクニックで演奏する、というコンセプトでスタートした1966カルテット。これまでビートルズやクイーン、マイケル・ジャクソンなどさまざまなアーティストをカヴァーしてきた彼女たちが、新作『DIAMONDS』でUKロックの名曲に挑戦。ハード・ロック、サイケ、プログレなど、時代を超えた多彩な楽曲を演奏して新境地を切り開いた。昨年、活動歴10年という節目を迎えたなか、メンバー・チェンジでパワーアップした4人に話を訊いた。
――オリジナル・アルバムとしては7年ぶりの新作ですが、前作『アビイ・ロード・ソナタ』からメンバーが2人変わりました。バンドにとっては大きな変化ですね。
松浦梨沙(ヴァイオリン)「これまで以上に良くなったと思います。以前のピアニストは“私、頑張ってついていきます!”というタイプだったんです。でも、みのりん(増田みのり)は“俺についてこい!”っていうタイプで、そこでサウンドがガラッと変わりましたね。ドラムが入ったような重量感が生まれて、これまで以上にバンドっぽくなったと思います。そのあとにチェロの伊藤ちゃん(伊藤利英子)が入ってきたんですけど、その時には新しいサウンドの基盤ができていたので、伊藤ちゃんは“ロックをやらなきゃ!”って意識せずに自分の音を出せたんじゃないかな」
花井悠希(ヴァイオリン)「ピアノが引っ張ってくれる、という安心感があるから、私たちヴァイオリンも歌のパートでは自由に弾けるようになりました。だから演奏していて、すごく新鮮なんですよね。“今のカルテットだったら、こんな音ができるのか”って」
――ピアノの存在感が増したんですね。
松浦「みのりんはロックがめちゃくちゃ好きなんですよ。クラシックの人に“これを弾いて”って言うと“わっ!”って驚かれる曲も、彼女は問題なく弾いてくれる」
花井「それに楽しんで弾いてる感じが伝わってくるんですよね。私たちのようなクロスオーバーな音楽をやっていると、そこが重要なんです。奇をてらってやっているわけじゃなくて、本当にやりたいと思っているという気持ちが伝わることが」
――増田さんはどんなふうにロックと出会ったんですか?
増田みのり(ピアノ)「クラシックの学校に通っていたんですけど、ニューヨークで留学生活を始めた矢先に9.11が起こったんです。それでクラスメイトたちが宗教の話とかをするようになったのですが、私はそこに全然入れなくて。自分が温室育ちだったことに気づいて、それからクラスメイトと一緒にいろんなイベントやパーティに出かけるようにしたんです。そこで初めてロックを聴いたんですけど、歌詞にまず驚いたんですよね。日本で聴いていたポップスは恋愛のことばかりだったけど、ボブ・ディランやレディオヘッドがすごいことを歌っている。まず歌詞があってメロディが生まれるというのも新鮮で、それから“歌”を意識して音楽を作るようになったんです」
――なるほど。クラシックとロックを融合させた1966カルテットは、増田さんにはうってつけのグループですね。
増田「(松浦)梨沙ちゃんが書いてくる楽譜がけっこうロックなんですよね。それを自分なりに解釈して弾くようにしています」
――プレイヤーが自由に解釈して弾くというのも、ロックっぽいですね。クラシックではそうはいかない。
増田「最初は一音変えるたびに確認してたんですけど、途中から勝手に変えてました(笑)」
松浦「基本はそれぞれ自由に弾いてもらってますね。気になった時だけ言うようにして」
――伊藤さんはロックは聴かれていました?
伊藤利英子(チェロ)「ずっとクラシックしか聴いてこなかったんです。でも、私はイギリスで生まれたのでロックには興味があって。実際に演奏してみると、すごく迫力があるし、なんだか燃えるというか(笑)。演奏や音色もクラシックとは全然違うので楽しいですね。雑音のほうが大事だったりして」
花井「そうね、勢いが大事だから」
伊藤「これまで丁寧にやっていたものを、あえて壊したりしています」
――音楽活動を通じてロックを学んでいるわけですね。今回のアルバムはUKロックがテーマになっていますが、なぜUKロックをやろうと思われたのでしょう。
花井「これまではアルバムごとに一組のアーティストに絞ってカヴァーしてきたんです。とくにビートルズは何度もやってきたんですけど、ビートルズの遺伝子を感じさせるUKロックのアーティストをヒストリー的にカヴァーしたら面白いんじゃないかと思って。4年前から、まずライヴでやり始めたんです」
松浦「アルバムでやるにあたっては、“きっとビートルズを聴いていただろうな”というアーティストを時代ごとに選びたいと思ったんです。それで年表みたいなものを作って、そこから代表的なアーティストを選んでいきました。私たちだけの知識だと無理だと思ったので、いろんな方に話を伺いました」
――バランスよく選ぶだけではなく、自分たちで演奏できるのか? というポイントも加わると選曲は大変ですね。
花井「そうなんですよ。ストリングス3本とピアノという編成でかっこいい曲が作れないと意味がないので。“パンクは私たちの演奏では成立しないんじゃない?”って思ったりして」
増田「(ローリング・)ストーンズの選曲も難しかったね」
松浦「いい曲いっぱいあるし」
増田「だいたい、チャーリー(・ワッツ)の刻みで成り立ってるんだよね」
――今回は「黒くぬれ!」をカヴァーしていますが、最初は何のカヴァーかわかりませんでした。もろにクラシックで、そこから厳かに「黒くぬれ!」のメロディが立ち上がる。
松浦「あれはバロック調にしてみたんです。ブライアン(・ジョーンズ)のシタールからリュートを連想して、それでレスピーギ『リュートのための古風な舞曲とアリア』の〈シチリアーナ〉が浮かびました。この曲はクラシックを学んだ人なら誰でも知っている曲なんですけど、それと同じ構成とリズムを使って、そこに〈黒くぬれ!〉のメロディを加えているんです。ある意味、パロディというか」
増田「クイーンの〈レディオ・ガ・ガ〉のカヴァーもバッハの無伴奏チェロ組曲が入ってくるしね。私はピアノでショパンのエチュードを入れたりして」
――クラシックを聴いている人にはピンとくる引用がちりばめられているわけですね。
花井「それがクラシックのカルテットらしい部分が出せるところなので」
――「黒くぬれ!」ではストリングスでロックのスピード感を出していますが、続くディープ・パープル「ハイウェイ・スター」でさらに加速。ストリングスの演奏が圧巻です。
松浦「クラシックでこんなふうに荒々しくストリングスを弾くことはないですね(笑)」
伊藤「腕が大変でした(笑)」
松浦「これまで、あえて雑音を出したり、音程を外したりすることでロックの表現を学んできて、その成果がこの曲に出ていると思います。自然に疾走感を出すことができました」
――疾走感を出す以上に大変だと思ったのはグルーヴです。ジャムの「悪意という名の街」のカヴァーには驚かされました。
松浦「この曲は私が好きでやりたかったんです」
伊藤「あのベースのリズムをチェロで弾くのは大変でした」
増田「私はピアノでダウンビートを刻めるんですけど、この2人(花井と伊藤)は裏ビートを感じ続けながら弾かなきゃいけないので」
花井「日本人のDNAにはないリズムだから、とにかく体に刻み込むしかないと思って、ひたすら同じリフを弾き続けたんです」
――パンクもそうですけど、シンプルなリズムの繰り返しの曲をストリングス・カルテットでカヴァーするのは難しいですね。グルーヴ感がごまかせないので。
花井「そうなんですよ。その点、レディオヘッドはグルーヴを作りやすかったですね。音楽的な展開もあるし」
――メンバーのジョニー・グリーンウッドがクラシックの教養がありますからね。
花井「曲の構築感が全然違います」
増田「レディオヘッドは大好きです。ジョニーさまは変態としか言いようがないですね(笑)。バッハにオマージュを捧げたピアノ・ソロの楽譜を発表しているんですけど、とんでもない曲なんです」
――今回は「パラノイド・アンドロイド」をカヴァーしていますね。
花井「曲の展開も面白いし、私たちがクラシックの要素を入れなくても、純粋に曲に取り組めば、自分たちらしい仕上がりになると思ったんです」
松浦「花井ちゃんのノイズ研究がすごかったね」
――ノイズ研究というと?
花井「曲で爆発する箇所があるじゃないですか。あそこはパン! って世界が変わらないといけないのに、うちの編成でそれをやるのが難しくて」
松浦「ドラムもなんもないからね」
花井「世界が変わるところをパチッと聴かせるには、どういうサウンドが必要なのかを考えたんです。手と指と弓だけでどんな音を出せるのか? 指板を押さえながら叩くと、マイクが拾って打楽器みたいな音がするので、それを入れてみたりして」
松浦「ほかにもいろんな技法を教えてくれたけど、私はいまだにできない(笑)」
――レディオヘッドがやっていそうな音響実験をしていたわけですね。
花井「あと、トム・ヨークの歌って音程が微妙なので、それをどう弾くかも悩みましたね」
――たしかにフラフラしてますもんね。
花井「“音にするとどっちなの?”というのが多くて、それを弦楽器で弾くと音程が悪いヴォーカルになってしまう。それにトムの歌声は、聴く人によって音程が違って聞こえるんです。そんな歌声をどこまで忠実に弾くかは最後まで悩みました」
――1966カルテットでは、ヴォーカル・パートはストリングスが担当したり、ピアノが担当したりして、メンバー全員が“歌える”のもこのカルテットの強みですね。
松浦「今回、〈悪意という名の街〉は私がヴォーカルを弾く、という設定でアレンジしたんですけど、基本はみんなにメロディを回すようにしています。そうやってコロコロ変わると飽きずに聴けるかな、と思って」
花井「私たちは歌詞がないので、語り口が一人だと飽きられちゃうと思うんですよね。楽器も弾く人も変わることで、それぞれの原曲の捉え方、メロディの捉え方を表現できる。しかも、弦楽器の視点で聴くのとピアノの視点で聴くのとでは曲はぜったい違うから、メロディを弾く人がどんどん変わると、味付けが変わって面白いんじゃないかなって思います」
――たしかにそうですね。4年前からコンサートでUKロックをやられていたそうですが、レッド・ツェッペリン「天国への階段」をやってほしい、というファンからのリクエストが多かったそうですね。今回、ついにアルバムに収録されました。
松浦「これもアレンジが難しくて、初めて聴いた時は、どこから手をつけたらいいのかわかりませんでした。それで曲を4つのパートに分けて、それぞれのパートで重要なところだけ押さえてアレンジしてみることにしたんです。それをコンサートで演奏して、削れるところを削っていって今の形になりました」
花井「少しずつ洗練されていったんだよね」
松浦「演奏も難しくて。やっぱり、ギターのソロを外すわけにはいかないじゃないですか。だから、そのままコピーすることにしたんですけど、ギターとヴァイオリンって全然違うから、ギターの速弾きをヴァイオリンでコピーするのは大変なんですよ。“何!? この指使いは?”って」
――難易度高そうです(笑)。今回もビートルズ関連の曲が3曲(ビートルズ「ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンズ」、ジョン・レノン「スターティング・オーヴァー」、ウイングス「007 死ぬのは奴らだ」)収録されていますが、メンバーのソロのカヴァーは初めてですね。
松浦「メンバー4人のソロの曲をやりたい、という思いがずっとあったんです。今回はビートルズの曲はやるつもりはなかったのですが、ビートルズの遺伝子を感じさせる曲を集めたアルバムに、ビートルズの曲が入っていてもいいんじゃないかなと思って」
――それが「ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンズ」というのもすごいですね。アレンジするのは大変だったのでは?
松浦「難しかったです(笑)。1回、自分でやったやつをボツにして、いつもお願いしている直江(香世子)さんにお願いしました。直江さんのアレンジはサビでスウィングするんですよね。その発想はすごいと思いました。クラシックにはないグルーヴを入れることで、私たちならではのサビになったと思います」
――「007 死ぬのは奴らだ」はいかがでした? 急にレゲエになる変な曲ですが。
松浦「レゲエのリズムを再現するのは難しかったですね。でも、これは私がすごくやりたかったんです。このアルバムを作る前から勝手にアレンジして弾いていたくらいで」
――原曲のどんなところが好きなんですか?
松浦「ライヴで好きになったんですよ。ポール(・マッカートニー)はよくこの曲をやるんですけど、その時のかっこよさがハンパじゃない」
増田「火柱がバーンと上がるんだよね」
松浦「そうなの! セットリストのいちばんいいところにこの曲がきて火柱が上がる。それで“私も弾きたい!”って思っちゃって」
――1966カルテットのコンサートでも火柱を上げたいですね(笑)。
松浦「上げたい! ロケット花火とか」
花井「あんまりショボいのはイヤだなあ。景気よく上げたいね」
――10月に予定されているコンサートが楽しみですね。
松浦「このメンバーでライヴをするのが、今からすごく楽しみなんです。アルバムの曲ではライヴでできないことはぜったいしない、と決めているので、アルバムそのままの形でお届けできますし、生だともっとエキサイティングな音で聞いてもらえると思います」
花井「UKロックが好きだけど、クラシックは聴かない人は多いと思うんですよね。そういう方がクラシックに興味を持つきっかけになったら嬉しいです。クラシック・ホールで聴く生楽器の演奏がどういうものか、ぜひ体験してほしいですね」
取材・文/村尾泰郎

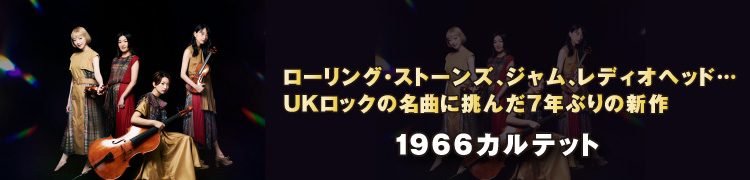


 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。