シンガー・ソングライターの広瀬咲楽が、セカンド・フル・アルバム『春の盤』をリリースする。透明感あふれるナチュラルな歌声で、あたたかみのあるメロディと等身大の心の揺れを綴った歌詞を、シンプルなアコースティック・サウンドとともに聴かせるのが彼女の持ち味だ。もとより春っぽい曲が多い人だが、今回はタイトル通り春の曲ばかりで構成され、彼女の真骨頂を示したアルバムといえる。宮城県出身でもともと役者としてデビューし、その後シンガー・ソングライターとなって珠玉の楽曲を生み出してきた彼女に、これまでの活動も含めて話を聞いた。
――広瀬さんは14歳からお芝居を学んで、17歳から曲作りを始めたそうなんですが、ということは小さい頃からなりたかったのは役者さんなんですか。
「はい。もともとは女優さんになりたくて、小学校の時からオーディションを受けていました」
――それで2012年に劇団ハーベストに入るわけですね。
「中学校に上がった頃から大手芸能事務所のオーディションを受けはじめました。でもすぐに震災が起きて、家やその周りや親戚も被害を受けてしまいました。もう諦めないといけない、と自分では思ったんですけど、半年経った夏にもう一回だけ挑戦したいと思って、"これが落ちたらもう目指すのを辞める"って言って受けたオーディションで合格しました。それがアクトレースというオーディションで、その最終審査に残った人で結成したのが劇団ハーベストだったんです」
――17歳から曲作りを始めたのは、なにかきっかけがあったんですか。
「地元の“仙台すずめ踊り”という大きいお祭りがあって、私は小学校の時にそのお囃子隊で和太鼓を6年間やっていたんです。父がもともとドラムを叩く人で、だから打楽器ルーツで、そこから音楽が楽しいって思えるようになっていって。それで劇団ハーベストの舞台で、バンドものをやらせていただくことがあって、そこでドラムを叩いてました。そういうことをやっていくうちに、バンドやりたいという気持ちが出てきて。高校の文化祭でバンドを組んでドラムをやったりしてました。劇団のメンバーの子たちにも、“本気でバンドやりたい”と誘ったら“私たちはお芝居がしたい”と言われちゃって、そりゃそうだよなと思って(笑)。その時に、じゃあ自分で曲を書こうって思って、そこからです。姉がギターやっていたので、見よう見まねでギターを買って練習して、そこから曲を作りました」
――その時点で、お芝居とともに音楽への思い入れも強くなっていったんですね。
「ずっとお芝居は憧れていてやりたかったものだったんですけど、音楽を演奏することや歌うことは別の楽しみがあるということにバンドモノのお芝居をやった時に気づいたんです。お芝居をしながらなんだけど、音を鳴らして、みんなで呼吸が合って、お客さんがいて、その感じをやってしまったらやっぱり楽しいと思いました。お芝居は“考える楽しさ”で、音楽は“体を動かして表現する楽しさ”みたいな」
――それでいろいろな舞台の劇中に使う楽曲を書いていくことになるわけですけど、それは劇団側からオファーがあって曲を作るということなんですか。
「“こういう脚本なので、これに合う音楽を作ってください”という話をいただくのですが、かなりまかされるというか、自由度はすごく高いんです。曲を作るうえでは、自分で納得がいって、お客さんにもいいねって言っていただけるものを書けてきているのかなとは思います」
――そうやって曲を書いていくうちに、曲を作るのっておもしろいとなっていったんですか。
「最初から楽しかったです。中学生くらいから歌詞、文章を書くのが好きで、自分の考えていることを、歌詞みたいにしてノートに書いていたんです。なので、自分が考えていることを歌にできるってことが楽しくて。そこからは、歌詞の文章を書く段階でリズム感がある歌詞になっていって……そうすると作りやすいんですよね。そこからどんどん生まれていくのがいつも楽しいです」
――2019年に、“女優という夢ではなく、シンガー・ソングライターとして夢を追いかけたい”ということで、ハーベストを卒団して俳優活動を停止します。この時に役者よりもシンガーになりたいことのほうが勝った、ということなんですか。
「そうですね。自分の中で、芸術を通してやりたいことが決まってきたのが2019年で、その時に“音楽か役者かどっちか”と言われたら絶対に音楽だと思ったんですよ。それは理由があって。私がその音楽をなぜ書いているのかと思った時に、自分の時間の一瞬一瞬って過ぎていってしまうじゃないですか。今日はもう明日になったら昨日になってしまって、自分が体験してきた、嬉しかった今日とか悲しかった今日っていうのが、どんどん過去になっていく、目の前からなくなっていくのが、すごく寂しくて。でもそれを歌にしたら、ずっと残っていくかもって思って。音楽はその想いが、一番純粋に作れるものなんです。お芝居も好きなんだけど、自分が人生の中で一番やりたいのはなに?って言われた時に、私の中にある本当をこのまま出すためには音楽しかないって思いました。そこが一番の決め手でした」
――その後にお芝居のお仕事も復活して、今はまた両方やっていますよね。それは、やっぱりお芝居はお芝居で魅力的ということなんですか。
「自分の中では、お芝居はずっと向き合うものという感じです。劇団にいた頃は本当にすごく忙しくて、毎日ついていくのに本当に必死だったんです。一旦2019年にお芝居をストップした時に、最初不安になったりするのかなと思ったら、ビックリしたのが、どんどん“自分というもの”がわかってきて、そっちの方がお芝居に生かせるっていうことに気づいたんですよね。皮肉にも、一生懸命お芝居をやっていた時期ほど自分のことを知らなくて、時間が出来た途端に自分の事がわかってきました。お芝居を離れてちょっと時間が経ったから、この状態でお芝居をしたらどうなるんだろう?という興味に変わったので、また続けようかなと思いました」
――自分の中で両方ないとダメというか、両方あってこそバランスが取れる、というような感じですか。
「音楽はずっとやっていたいです。音楽が第一です。お芝居は、卒団してからお芝居の自分の置き場所が変わったので。なので、まだお芝居も再始動してから時間が全然経っていないので、これからまたどう感じるかわかってくるのかなという感じではあります」
――では、今回のアルバム『春の盤』なんですが、全曲が春にちなんだ曲ということで、こういうアルバムを作ろうと思ったのは?
「もともと春の曲が多かったのですが、このテーマでひとつのアルバムにしたら面白いんじゃないかな、と思ってこうなりました」
――1曲目の「海の駅」は新曲ですけど、どういうイメージがあったんですか。
「実際、そういう名称の駅があるわけじゃないんですけど、宮城の風景の中にある海沿いの街のどこかの駅みたいなイメージです。そういう駅は宮城にはいっぱいあるんですけど、私だけの曲になって欲しくないので、聴いた人それぞれにとっての“あの駅かな”って、想像できる余白を残しています」
――このアルバム全体に東日本大震災に関連する言葉が随所に出てきますけど、それは意識しないでも出てしまいますか。
「震災のことは、曲を創る時もお芝居をしている時も、表現をしている上で、やってもやっても足りないっていう想いがあります。たぶん、それだけ自分が経験してきたものと、自分の感性が拾い集めてきてしまったものが、膨大だったんだなって、自分の中で感じています。だからやってもやっても足りない。震災のことを書いた曲が『春の盤』には何曲か入っていますが、それをやってもやっても、想いがどうしても終わらなくて。かつ、現在進行形で動いていることなので。その街の状態とか生きている人たちにとっては」
――ではこの先も、曲作りをやると自然に出てくると思いますか。
「おそらく。アイデンティティとして受け取ったものだと思っています」
――ラストの「321」は震災から10年経った2021年に書いたそうですけど、すごくポジティヴで力強い言葉が目立ちますね。
「この曲は去年、震災から10年のタイミングで、TOHOKU Roots Projectの配信でやったお芝居(『十年後のミラーボール』)の主題歌なんです。そこで俳優の活動をリスタートさせてもらったんです。この10年のタイミングは、続いているけどひとつ区切りとして受け止めるタイミングだと自分で思って、思うことを素直に書かせてもらいました。それで“これから高く飛ぶ”と漠然と思ったんですよね。ずっと高く飛びたかったし、ずっと頑張ってきたんですけど、でも自分の中では上手くいかなくて沈んでしまうことが多くて、でも10年を迎えた時に、これからどういう自分になりたいかと思った時に、“私は高く飛ぶ”って思って。それを書いた時にひらめいたんですけど、(震災が起きた日の)“311”ってよく言われますけど、10年の10を足したら〈321〉になるって思って。『春の盤』には震災のことで弱音を吐いている曲が多いんですけど、〈321〉で“自分がずっと、ずっと嫌だった”という歌詞を書いた時に、泣いてしまったんです。10年の結論として出したのが〈321〉なので、ほんとにギュッと詰まったなって感じはします」
――そういう重要な曲を生み出したことで、自分の中でひとつケリがついた、という感覚があるんじゃないですか。
「ケリは一生つかなくても、こういうふうに思っていてもいいんだっていう、自分が欲しかった言葉を自分で書いたみたいな感覚です。だからこの曲が地元の人に届けたいと思いますし、たとえば震災の経験だけじゃなくて、他にも大事な人を亡くしていたりとか、会えなくなってしまっている人がいる人に届いたらと思います。そういう気持ちを曲に込めたエネルギーが大きかったのかと思います」
――アルバムとして、大きな区切りになった作品という感じはしますよね。
「そうですね。出せて本当に良かったです」
――最後に、これからどういうシンガーになっていきたいと思いますか。
「日頃から、その問いかけをずっと自分にしているんですけど、私は、自分が間違っているかもしれないというのがずっと怖かったんです。お芝居をする時も、正解があるから自分がやることが間違っているかもしれないってどこかで不安に思っていて。でも、自分の中にある本当は、本当に本当なんだっていう事を、一旦お芝居を辞めてから自分がわかってきた時に感じました。私の曲を聴いた時に、誰かが、自分も自分でいるって思ってくれたらいいなとずっと思っています。自分の性格としては“本当かどうか”にすごくこだわっていて。嘘をつくのはヘタだし、嘘をつきたくないんです。それはたぶん上手にできないし、その人への誠意が欠けることが、昔から嫌いで。そういう自分を周りからいい子ぶってるとか言われて育ってきて、そういう事が沢山あって、そうかもしれないって思った時が一番苦しくて。でもよくよく考えればそうじゃなかったなみたいなことが、今すごく沢山あるんです。だから私は音楽を通して、自分が自分でいていい場所を獲得できたと思ってます。それが皆さんに届いたらいいと思います」
取材・文/小山 守

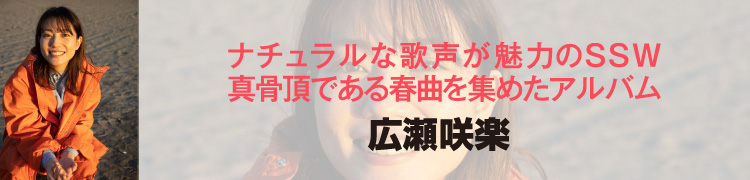


 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。