フリー・ソウルやカフェ・アプレミディといった人気コンピCDシリーズを手がける選曲家にして編集者、そしてカフェのオーナーでもある橋本徹(SUBURBIA)。彼のコンパイラー人生30周年を記念するコンピレーションが各レーベルから続々リリースされているが、そんな橋本に、今回は『Gratitude〜Free Soul Treasure』、そしてフリー・ソウルのことを中心に、そのコンパイラーライフについて語っていただきました。
――5月24日にULTRA-VYBEから『Gratitude〜Free Soul Treasure』が出て、26日にもう1枚、INPARTMAINTから『Merci〜Cafe Apres-midi Revue』がリリースされました。すでにP-VINEからリリースされていた『Blessing〜Free Soul×Cafe Apres-midi×Mellow Beats×Jazz Supreme』に続く、橋本さんのコンパイラーライフ30周年を記念する第2弾、第3弾にあたるコンピレーションで、第2弾の『Gratitude〜Free Soul Treasure』はこれまでULTRA-VYBEからリリースされたコンピレーションの中から、フリー・ソウルの魅力を凝縮させたような内容になっていますね。
「今までULTRA-VYBEで作らせてもらったコンピの多くがフリー・ソウル・シリーズで、以前にレーベルやアーティストごとの選曲のオファーをいただいたときに比べても音源が充実して、メジャーのレコード会社は別にすると、今、みんなが大好きなフリー・ソウルの音源を持っているのはULTRA-VYBEなのかもしれないな、って感じながら選曲していました」
――収録曲を見たら、このレーベルもULTRA-VYBEなんだ、というような発見が続きます。
「そうなんです。ホット・ワックス/インヴィクタスをはじめ、ブランズウィック、サルソウル、ウエスト・エンドも作らせてもらったし、ハイやマラコ、タブーも。あとはいちばん充実したものができたかもしれないT.K.、その後はフライング・ダッチマンもコンパイルしました。気づいたら、この10年ぐらいの間にULTRA-VYBEでたくさん選曲させてもらっていましたね。90年代を思い返すと、基本的にすでにレコード会社が持っている音源の中で僕が好きな曲をアプルーヴァル申請して許諾が下りたものでコンピレーションを作るっていう感じだったんですが、時が経ってインターネットの時代になったことで、90年代当時は権利者になかなかたどり着けなかったようなインディペンデントなレーベルや音源に対しても、インディーのレコード会社がアプローチできるようになって、90年代には収録できなかったような曲をコンピに入れられるようになったのは、すごくうれしいことだなって、ここ数年感じています」
――そのT.K.からはフリー・ソウル・クラシックであるリード・インクの「What Am I Gonna Do」が収められています。
「『Free Soul T.K.』を2019年に作らせてもらったときに、ひとつの達成感があったんですけど、この曲は本当に思い入れ深い大好きな曲で、今回のコンピにも入れましたが、いい形で選曲できましたね。自分的なハイライトはフリーダ・ペインの「We've Gotta Find A Way Back To Love」からリード・インクにいって、そこで情緒的には最初のクライマックスがやってきて、次のジュディー・ロバーツ「You Light Up My Life」をブリッジにコンピの後半に入っていく流れです」
――まさにこの『Gratitude〜Free Soul Treasure』には橋本さんが30年にわたって貫いてきたコンパイラーとしての揺るぎない姿勢も感じ取ることができました。それは有名無名に関係なく、また誰も知らないようなレアな曲を入れてひけらかすということでもなく、常に自分の感性やセンスを選曲の基準としてきたことだと思います。
「それはもう、大学生のときに中古盤を熱心に探すようになった頃から変わらない気持ちですね。選曲に臨む際に限らずですけど。ちょうどその頃、イギリスからのレア・グルーヴ・ムーヴメントを知るんですけど、そこで僕が共感したのはフィロソフィー的な部分で、埋もれていた、見過ごされがちだったレコードの中に自分たちの価値観に合う良さを見いだすという精神だったんです。レア・グルーヴというと、入手困難なファンクみたいなイメージで捉える方もいるかもしれませんが、元々は埋もれている安いレコード、知られていないレコードの中から宝物を探し出す、という行為だと僕は解釈してシンパシーを抱いていました。そういうフィロソフィーというか、考え方は自分の好きな音楽と出会っていく中で基礎、基本になっていて、当然自分が提案したフリー・ソウルというムーヴメントを貫く考え方にもなっています。それは自分の好みや価値観に忠実に、先入観や偏見にとらわれずに好きな音楽と出会う、楽しむということであり、変わらず30年以上にわたって自分の音楽との接し方において貫かれていることかなと思います」
――そうした過去の音楽へのフラットで自由なパースペクティヴを持ち続ける一方で、毎週の新譜チェックも怠らないことも常に新たな視点を持った選曲につながっている気がします。
「新譜も旧譜も自分に訴えかけてくれる、共感できる共通点みたいなものを感じながら自由に縦横無尽に行き来できることが、楽しいリスニングライフだと思っているんです。それもやはり30年以上変わっていないことですね。“Not New, But Fresh”と感じることも多いですし。自分自身が新しい音源でも古い音源でもフレッシュな出会いをしていないと、クリエイティヴの部分でもインスピレーションが湧いてこないんじゃないかな。自分は大きな意味で編集する人間だと思っていて、それはCDや雑誌だけじゃなく空間や時間も含めてなんですが、単にDJです、ライターです、カフェ・オーナーです、みたいな気持ちはないんです。もちろんレコードのコレクターという意識もない。編集する人として必要があるときに、楽しくやれるときにDJをしたり、文章を書いたり、空間をプロデュースしたりしているだけであって、そういった仕事を楽しくやり続けるには、自分の好きなものに出会うときめきみたいなものを大切にしたいというか。それがなかったら、30年も続けてこれなかったでしょうね」
――2010年代には『Free Soul〜2010s Urban』シリーズもスタートしました。それまでのフリー・ソウルと共振するような現在進行形のトラックがセレクトされ、フリー・ソウルがアップデートされました。
「それまでのファンやリスナーに新たなリスニングスタイルを提案するということは、送り手として『Free Soul〜2010s Urban』シリーズをスタートさせるときにとても意識していました。2010年代のアーバン・ミュージック――ジャズやネオ・ソウル、ヒップホップやビート・ミュージック、チルアウトやバレアリカが混ざり合うようなシーンの中で、フリー・ソウルのコンピに入っていた70年代のメロウ&グルーヴィーな音楽と、90年代にそれと並行して楽しんでいたであろうUKソウルやアシッド・ジャズ、あるいはニュー・クラシック・ソウル、ジャジー&メロウなヒップホップを聴いていた人が、2010年代の音源ならこういう曲を聴いたら肌に合うんじゃないか、という提案をしたかったんです。今の音楽にも自分たちの肌に合うものがたくさんあるということに気づいてほしいという気持ちが強くありましたね」
――90年代のフリー・ソウルはやがて、自分にとって気持ちいい、ワクワクさせてくれる音楽という記号になっていきました。言葉による説明が必要なく、その音楽の魅力を感覚的に共有できる存在になっていったように思います。
「そういう信頼みたいなものは、30年かけて築き上げてこれたかなという風には思いますね。そういう意味でもポップな輝きみたいなものと、スピリチュアルな信頼みたいなものを両立させることを大切にして選曲、コンパイルしてきました」
――ベン・ワットがSpotify上で自分のお気に入りの曲をセレクトしたプレイリストを公開していますが、彼のプレイリストもフリー・ソウルに通じるジャンルやスタイルにとらわれない感覚的なフィロソフィーを感じるんですよね。
「そういうベン・ワットに対する信頼感は僕にもすごくありますね。1996年リリースの『哀しみ色の街』で“ドラムンベースは21世紀のボサノヴァだ”という言葉とともに、エヴリシング・バット・ザ・ガールを段落替えして、2000年代頭にはミシェル・ンデゲオチェロやマックスウェルの至福のハウス・リミックスを手がけたり、自らのハウス・レーベルにティム・バックリーの曲名から“Buzzin' Fly”と名付けたり、そういうセンスにはとても共感できます。ベンやトレイシー・ソーンの音楽を聴いていると、音楽と人生みたいなことをすごく考えるんですよね。僕は1980年代前半、高校生の頃に『ノース・マリン・ドライヴ』や『遠い渚』、EBTGのファースト『エデン』を聴いたことが原点のひとつなんですが、あの時代のアーティストから受けた影響というのが、世代的にもすごく大きくて。フリー・ソウルも要は、ポスト・パンク〜ニュー・ウェイヴの時代にメジャー7thを使ったアコースティックなポップスを始めたアズテック・カメラやペイル・ファウンテンズ、スタイル・カウンシルみたいなものなのかなって思うことがあるんです。フリー・ソウルはネオアコ好きにもおすすめできるソウル・ミュージック、なんてこともときどき言ってたんですが、ハウスやヒップホップが全盛の90年代に、生音やメロディーも大切にしながら、でも同じ土俵というか、近いフィールドでクラブでのパーティーを楽しんでいたという、カウンター的な存在感も通じますし」
――いわゆるネオ・アコースティックと呼ばれる音楽の魅力である光と影は、フリー・ソウルで選ばれた曲に通じるところが大いにあると思います。
「もっと言うなら、ポール・ウェラーがジャムを解散させてスタイル・カウンシルを始めるときのスタンスに、17歳の僕はすごく影響を受けたんですよね。ジャムのファンや原理主義的なモッズの人たちは、細身のスーツで決めて、デコレーションしたスクーターに乗ってというステレオタイプなスタイルに象徴されるように、ある意味で60年代の再現、疑似体験に向かっていたと思うんですが、ジャムでやるべきことはすべてやり尽くしたポール・ウェラーは音楽的にもパンク〜ネオ・モッズからソウル・ミュージックやジャズ、ラテン、ボサノヴァに影響を受けた音楽にシフトしていったり、ファッション的にもいわゆるモッズ・スタイルからフレンチ・トラッド〜フレンチ・アイヴィーへと移り変わっていきました。綺麗な色のニットを合わせたり、ステンカラーのコートを羽織ってパリのカフェに佇むスタイルを選んだポール・ウェラーがすごくかっこよく思えた人間なので、フリー・ソウルの在り方というか、それまでの日本の音楽ジャーナリズム、特にブラック・ミュージックのジャーナリズムを担ってきた年配の方々の権威主義的な、父権的な押しつけや上から目線への違和感を表現する際には、彼の影響をとても受けていると思います」
――旧来の評論やメディアに対して、自分たちの世代の価値観は違うんだということを打ち出す、ジャーナリズム的な側面もフリー・ソウルは持ち得ていたんじゃないでしょうか。
「結果的にそうなっていきましたね。ジャムからスタイル・カウンシルへと移行するタイミングで、ポール・ウェラーはピート・タウンゼントを、言わば“親殺し”しました。僕はこれはある意味で必要なことだと思っているんですよね。自分が中古レコード屋で好きなものといろいろ出会って感じたことと、それまでの日本の黒人音楽評論界隈で築き上げられていた価値観、物差しの違いを大学生から20代の頃にすごく感じていたんで。そういった旧態依然とした前時代的なものに対するアンチテーゼ、カウンターであるべきだということは、僕自身フリー・ソウルの中で常に意識していたことで、その父権性に抗う上で、フラワー・チルドレン的な、あるいは“ぼくの伯父さん〜モノンクル”的なスタンスで自由にフレンドリーに音楽を楽しみたいということを掲げていったんです。年配の偉い方とか、より詳しい方の価値観に右にならえではなくて、自分にとって本当にいいと思える音楽を同じセンスや趣味を共有できる人たちと一緒に楽しむ、それがフリー・ソウルの精神だったんですね。だから20代の自分にとってフリー・ソウルはレベル・ミュージックでもあったんですよ。音楽的にはもちろん怖いものでもないし、難しいものでもない。むしろピースフルで心地よく、かっこよく、グッとくる音楽だったり、楽しくて気持ちいい音楽ということを大切にして、共感者が増えたらいいなと思っていたんですが、90年代にフリー・ソウルを立ち上げてからしばらくの間は、レベル・ミュージックという思いも胸にやっていましたね」
――渋谷の一区画で声なき声を上げたレジスタンスですね。
「そうですね。ロンドンのレア・グルーヴ・シーンとも心の中で連帯した、東京ならではのムーヴメント、楽しみ方を目指していました。先日亡くなったリンダ・ルイスも、シリータやミニー・リパートン、デニース・ウィリアムスといったメロウな女性歌手たちもそうですが、90年代前半まで日本ではそれこそスティーヴィー・ワンダーやチャカ・カーンでさえ、日本の黒人音楽愛好家たちには正当に評価されていなかったんです。リロイ・ハトソンやテリー・キャリアーなんて、それどころかまったくで。これいいなあと思ってレコード買ってきて、先輩方が書いたディスク・ガイドのどこかに出ているだろうと探しても載っていなかったり、歌が弱いとか、ジャズ寄りすぎて黒くないとか、けなされていたりしていた状況に対して、自分はこう感じるというのをぶつけていったのがフリー・ソウルの最初期なんです。そのスタンスがすごく象徴的に表れているのが1995年にコンパイルした『Groovy Isleys』と『Mellow Isleys』というコンピで、アイズレー・ブラザーズはそれまで甘々のバラードか重量級ファンクという視点でしか評価されてこなかったものを、例えばキャロル・キングやトッド・ラングレンなど白人のシンガー・ソングライターとの接点にある魅力を見いだして形にするとかしていったんですね。幸運なことに、それがとても支持されたわけですけど」
――“フォーキー”というのもフリー・ソウルの一要素になっていました。
「1995年はフォーキーの年だみたいなことを僕はよく言っていたんですが、1993年にポール・ウェラーの『Wild Wood』、1994年に『Live Wood』、95年に『Stanley Road』という流れがあったり、ガリアーノがクロスビー・スティルス&ナッシュの「Long Time Gone」のカヴァーをしたり、プライマル・スクリームの「Movin' On Up」が人気を集めたり、マザー・アースのマット・デイトンがフォーキーな名作アルバム『Villager』をリリースしたり、アメリカでもベイビーフェイスがフォーキー化していたり、現在進行形の音楽とリンクする形でソウル・ミュージックでもフォーキー寄りの魅力にアプローチしていこうという動きに自然になりました。その当時の空気と70年代の空気がつながっていることを表現することで、旧来の価値観を刷新していくことにつながっていったように思います。同時にコンピやリイシューが外資系のCDショップにずらりと並び、品揃えが充実していったことが、21世紀の今とつながるシーンの礎になったというか、21世紀の一般教養を準備したんじゃないかなと、今となってそう振り返ることができますね」
――まさにその外資系CDショップの総合チャートでフリー・ソウルのコンピが1位になるほどの勢いが当時ありましたね。
「90年代半ばから後半にかけて、こちらがブレーキをかけないと、どんどんレコード会社からオファーをいただくというような状況でしたね。同時に1999年にはカフェ・アプレミディを開いたり、フリー・ソウル以外の自分を表現できるようにしていったことで、少しずつ僕のキャリアも拡がっていったというか。とはいえ、30年で350枚以上コンパイルしてきているんですが、そのうちの120枚以上はフリー・ソウル・シリーズなんです。だからフリー・ソウルに対する思い入れはもちろん強くあるんですが、実はそれだけじゃないっていう気持ちも僕はそれ以上に強く持っているんですよね。世間的にはフリー・ソウルの橋本徹なんだけれども、僕自身はそうじゃなくていろんな自分があるということも自己表現させてきてもらえた30年でした。フリー・ソウルが支持されたことを本当にありがたいなと思うのと同時に、でもそれだけじゃないよということも知ってもらえたらうれしいなというのは今でもあったりしますね」
――30年という歳月の中で選曲のスタイルは変わってきたのでしょうか。
「フリー・ソウル・コンピのサブラインがいろいろできて、僕自身の選曲スタイルも少しずつ変化していったと思います。90年代のフリー・ソウルのコンピは、サッカーだったらキックオフの瞬間からオフェンシヴに行くような感じ、ボクシングだったら1ラウンドからノックアウトを狙っていくような求心力、吸引力があったと思うんですが、歳を重ねるにつれて時間をデザインする感覚、80分間を演出するという感覚をコンピに反映させられるようになっていきました。今回の『Gratitude〜Free Soul Treasure』には、フリー・ソウルの90年代からの人気曲、キラー・チューンがこれでもかとたくさん入っていますが、セレクションの組み方としては時間をデザインする感覚があると思います。このコンピはギル・スコット・ヘロンの「I Think I'll Call It Morning」で始まるんですが、昔だったらギル・スコット・ヘロンなら「It's Your World」や「The Bottle」、「When You Are Who You Are」あたりを選んで、とばしていたかもしれませんね。でも、この1曲目に選んだ「I Think I'll Call It Morning」には今の僕の心情が委ねてあるんです。“陽光の中、鳥の歌を聴き、自由について思う。雨よ、もう降らないでくれ。今の俺の気持ち”という歌詞は、今の僕の思いそのままですね。要は30周年っていうことがまた新しい出発になればいいな、スタートになればいいなっていう気持ちをこの曲に託してあるんです。30周年をこれからへの第一歩というか、新しい朝にしていきたいですね。うん、僕は朝と呼ぼうと思います(笑)」
取材・文/油納将志

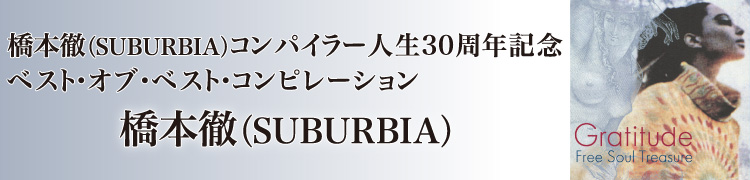


 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。