『Ayako Fuji Cover Songs 喝彩〜Kassai〜』は、2011年の『WOMAN』、2017年の『GENTLEMAN〜私の中の男たち〜』に続く、藤あや子にとって3枚目のカヴァー・アルバムだ。
お恥ずかしいことに取材時には報道を知らなかったのだが、アルバムのプロデューサーは、藤が所属するバーニングプロダクションの名物宣伝部長として知られ、11月14日に81歳で亡くなった河西茂夫氏だった。
人生の最後に藤の歌声で聴きたい、葬式で流してほしい曲を選び、アレンジを小倉良に委ね、病を押してスタジオに現れ、ほとんどの工程のチェックにも関わったという。まさに遺作、河西氏にとっての『マイ・ラスト・ソング』(久世光彦の著書のタイトル)だったわけだ。
実際、出棺の際にはこのアルバムから「喝采」(ちあきなおみのカヴァー)が流されたという。藤自身も「ミラクル」と称するエピソードがいっぱいのインタビューをお届けする。
――オリジナル歌唱が女性の『WOMAN』、男性の『GENTLEMAN』に続く3枚目のカヴァー・アルバムですが、『喝彩』は過去の2枚とはどういうところが違うんでしょうか。
「じつは何もかも、まったく違うんですよ。そもそも “アルバムを作ろう”という話から始まった企画じゃないんです」
――とおっしゃいますと?
「もともと、11月に亡くなったうちの事務所の河西という者が、去年の暮れに“あや子の声で最後に残したい歌を”って言ったところからスタートしたアルバムなんです」
――下調べ不足で存じ上げず失礼しました。河西さんがアルバムのプロデューサーなんですね。
「そうなんです。ジャケットをよく見ていただきたいんですけど、ローマ字表記の“KASSAI”で、Sが……」
――重ねてありますね。そうか、1文字で“KASAI”にも見えるように。
「そうなんです。河西さんプロデュースの、という意味を込めて。ダジャレみたいですけど(笑)」
――(この日の午前中に届いたというCDのブックレットをめくりながら)ああ、“Produced by Shigeo Kasai(Burning Production)”とクレジットがありますね。
「私が35年前に事務所に入ったときにはすでにいらっしゃったんですけど、かっこいい人で、いい意味で“わっ、業界人だ”って思った方なんですよ。ただ、ずっと紙媒体担当の宣伝マンで、誰かをプロデュースしたなんて聞いたことがなかったんです。河西さんがガンになられて、去年の暮れに元気づけるための食事会が開かれたんですけど、その席で“あや子って、歌うまいんだよなぁ”ってほめられたんです、初めて」
――35年一緒にいて、初めてですか!
「初めてでした。それで“えーっ!”とまず驚き、“あや子の歌でアルバムを作りたいんだよね”と言われてまた“えーっ!”と驚き。ソニーミュージックのスタッフもそこにいたので“よし、やろう”ってなったんですけど、河西さんが“俺、医者に言われたんだよね。もう来年の桜は見れないって”って言うんですよ。ということはあまり時間がないじゃないですか。焦りましたね、間に合うかなって。そこから河西さんもすごく頑張ったと思います。目標ができたんだと思うんですよね。10月にヴォーカル録りをしたときも来てくれたんですよ。それ1回きりでしたけど」
――春の桜を見れないと言われていたのに、10月にスタジオまでいらしたわけでしょう。すごいですよ。
「私はせつないわけですよ、河西さんがいらっしゃるスタジオで、お葬式で流したいという歌をレコーディングしているんですから。ちょうど〈あなた〉を歌っていたんですけど、この歌って子どものころに聴いたときは、大きなおうちに暖炉があって犬がいて……みたいな夢のある歌だと思っていたんですけど、いざ歌ってみたら、そこに“あなた”がいない歌なんですよね。〈あなた〉に限らず、別れの歌や自分のことを忘れないでほしいって歌ばっかりだから、河西さんがこれを私に歌ってほしいって思った気持ちを想像しちゃうんです。だからもう、本当に苦しくて、つらくて、せつなくて」
――そうなりますよすね……。
「でもね、そのとき河西さんは“あや子、もっと自由にのびのび、枠からはみ出すくらいに歌って”って言ったんです。きっと私の気持ちを歌のなかに感じ取ったんでしょうね。“そうだ、自分らしく自由にのびのび歌わなきゃ。もともと私はそういう気持ちで歌っていたんだ”と思えて。背中をポンと押されたような感覚でした。そのひとことが私にとっては遺言、最後のメッセージだったんです」
――10月というと亡くなる前月ですから、河西さんも苦しかったでしょうにね。
「最初は舌ガンだったんですけど、転移して……。レコーディングに来てくれたときは、左腕が倍に腫れ上がっていて、うまく動かせないような感じでした。それでも入院もせず、“もう治療しないから、いいのいいの。いまの薬は効くから痛くないんだよ”とか言いながら、亡くなる2週間ぐらい前まで、自力で歩いて会社にも行ってました。そんな人、見たことないですよ」
――はぁぁ……(ため息)。
「レコーディングが全部終わって、トラックダウンも終わって、その間も河西さんに全部チェックしてもらっていたんですけど、完成したその日に亡くなったんです」
――えっ!
「そうなんです。そして、河西さんが思い描いた通り、お葬式で出棺のときに〈喝采〉が流れるなか見送られていきました。最後までかっこよく」
――最後の命の炎が……。
「このなかに。すごいアルバムができました」
――ちょっと涙が出てきちゃいました(鼻をかむ)。
「河西さん喜んでると思う(笑)。こんな生き方も亡くなり方も、なかなか計算してもできないですよね。私だったら絶対に無理。あえて見せてくださったんだと思います」
――衝撃的な経緯に、お聞きしようと思っていたことが全部吹っ飛んでしまいましたが、気を取り直してまいります。アルバムの選曲も河西さんがされたんですね。
「100曲以上セレクトしてくれて、そのなかから私とスタッフで厳選していきました。〈さよならエレジー〉〈366日〉〈海鳴り〉〈Far away〉の4曲だけは私が提案したんですけど、原曲とその歌い手へのリスペクトを込めて、徹底的に聴き込んで、できるだけ忠実に、という気持ちで取り組みました。ただ、さっきお話しした通り、どうしても河西さんの気持ちを想像しちゃうので、レコーディングはつらかったです」
――河西さんに選曲の理由はお聞きになりましたか?
「唯一、“(郷)ひろみの〈ハリウッド・スキャンダル〉、あや子に歌わせたら面白いよね、きっと”というのだけ聞きました。ひろみさんも同じ事務所なので、河西さんはずっと担当されていたんですけど、数ある曲のなかでなんでこれなの?と思いました。自分だったら選ばなかったろうし、内容的にも女性が歌う歌ではないですしね。でも歌ったらハマったので、さすがだなと思います。やっぱりどれもいい歌です。阿久悠先生(〈街の灯り〉)、なかにし礼先生(〈グッド・バイ・マイ・ラヴ〉)など、名だたる巨匠たちの作品が、じつはこんなシンプルな歌だったんだ、だから名曲なんだなって思いました」
――歌謡曲の凄みですね。永六輔さんの「見上げてごらん夜の星を」なんて、言葉数はわずかなのに情報量がめちゃくちゃ多くて。
「人が亡くなると星を見て“あそこにいるのかな〜”なんて思ったり、祈ったりするじゃないですか。そうして自分のことを思い出してほしいという河西さんのメッセージなのかな、と思ったりしました。河西さんの選曲でとくに私が意外に感じたのが〈離したくはない〉で、男性の歌だし、ご本人の曲をあらためて聴いてみたらとても難しいし、大丈夫かなって思いましたけど、いざ歌ってみたらこれもハマったんですよ。私のなかのロック魂が反応したんですね(笑)。ライヴで今度歌いたいな、って思わせてくれた曲のひとつです」
――僕が個人的にすごく印象的だったのは、「冬のリヴィエラ」のサビの“♪ふ〜”のところの高音でした。響きがきれいで。
「うれしいです。でもこれ、歌詞を読んだらひどい男ですよね(笑)。勝手にひとりで出て行っちゃって“陽気な唄でも聴かせてやれよ”なんて。 “は?”と思ったけど、きっと男の美学なんでしょう」
――「街の灯り」は、堺正章さんは軽妙な感じで歌っていましたが、藤さんの歌はしっとりしていますね。
「そうそう。自分で歌うまで、こんなせつない歌だったなんて知らなかったです。〈グッド・バイ・マイ・ラヴ〉だって、かわいい歌だと思ってたんです。ところが実際には残酷なせつない歌じゃないですか。子ども心によく聴いたり歌っていた歌も、あらためて歌ってみると記憶とのズレがあるんです。メロディも自己流で歌って覚えてたのと違っていたりして、発見や学びがたくさんありました」
――藤さんが昔からずっとお好きな歌というとどれですか?
「〈さよならの向う側〉は(山口)百恵さん大好きですから歌ってましたし、〈海鳴り〉もそうですね。高校生のころ、親友が中島みゆきさんのアルバムを買ってきて、“これ聴かない?”と言ったなかに入ってたんです。多感な女子高生ですから、先生や親に怒られたとか、いろんな悩みがあるわけです。そういうときは“みゆきさん聴こう”と言って、女の子だけ4、5人で集まって、カーテンを閉めた薄暗い部屋で、みんなで合唱したりして。そんな思い出の歌だったの。暗い女子校時代です(笑)」
――いやいや、素敵です。藤さんは過去にもみゆきさんの曲を歌っていらっしゃいますし、お好きなんですね。
「大好きです!詞を書くようになってから、自分のなかでいかにみゆきさんの存在が大きいかを痛感しました。前に何かで読んだんですけど、辞書が愛読書だそうです。言葉選びが絶妙じゃないですか。“ガラスなら あなたの手の中で壊れたい”(〈あした〉)とか。尊敬しています」
――「海鳴り」以外に「さよならエレジー」「366日」「Far away」も藤さんセレクトですね。
「石崎ひゅーいくん大好きなんです。車に乗るときはほとんど洋楽しか聴かないんですけど、唯一聴いている日本のアーティストがひゅーいくんです。もともと声フェチで、だからジョン・ボン・ジョヴィとかスティーヴン・タイラーも好きなんですけど、めめしい男がロック・サウンドで歌い上げるのがたまらないんです(笑)。ひゅーいくんにはめめしい男を歌い続けてほしい。“これ、私にちょうだい!”ってお願いしたい歌がいっぱいあります」
――「さよならエレジー」も名唱だと思います。ひゅーいさんや菅田将暉さんが放っていた青春のくぐもった輝きが、藤さんの歌で聴くと、大人がもう一回ネジを巻いて頑張っている印象に変わるというか。
「そうですよね。いろんな経験をしてきたから、一抹の悲しみが(笑)。やっぱり、ちょっと挫折感がないとダメなんですよ」
――「366日」にもそれに通じる味わいがありました。
「女性は老いも若きもみんな大好きな、永遠の失恋のテーマなので、絶対やりたいなと思いました。それこそ悲しみや挫折を経験した〈366日〉で、若い方が歌うのとはまた違う景色だと思います。若い子が世の中を悲観して、みずから命を絶ったりするじゃないですか。10代、20代って、小さなつまずきがものすごく悲しくて、お先真っ暗な気分になって、死にたくなっちゃうんですよ。でもね、ぐっとこらえて年齢を重ねていくと、楽しいおばさんになれるんです(笑)。だから傷ついて絶望してる子たちに聴いてほしい。おばさんになっても〈366日〉を目をハートにして歌える日が来るから(笑)、頑張ろうね、という応援歌でもあります」
――中学生、高校生のときって、好きな子がほかの子のことを好きだと知っただけで死んでしまいたいって思ったりしますよね。はっきり振られたわけでもないのに。
「ごはん食べないとか、学校行かないとか。気持ちはわかるんですよ、自分も通ってきてるから」
――偉い!そこで“そんなのいまだけだ”とバカにするんじゃなく、“わかるよ”と優しく寄り添えるのが素敵な大人だと思います。
「わかりますよ!だってあの当時の悲しみってほんと半端ないですから。傷つきやすいし、傷つけられたことを忘れない。ところがね、だんだんそれも癒えていくんですよ。おばさん化とともに、だんだん皮が分厚くなってくる(笑)。だから歳を重ねるのは悪くない。頑張ってほしいなって心から思います、悲しいニュースなんか見るとね」
――悲しいニュースが多いですよね。
「〈喝采〉を歌ったときはとくに、もちろん河西さんのことを思っていましたけど、日々流れてくるニュースを見ながら、人間ってどうして平和でいられないのかな、もっと平和を意識してもいいんじゃないかな、と思っていたのも重なりました」
――イスラエルとハマスの戦争はもう始まっていましたか。
「ちょうど始まったころでした。子どもたちの映像なんか見ると、つらくてね。家族や大事な人を失った人の気持ちが憑依しちゃったんですよ、歌いながら」
――「喝采」は絶唱と言っていいのではないでしょうか。
「私もまいりました。ア・カペラ始まりで、ギターの方(福原将宜)とふたりだけで録ったんですけど。じつは〈喝采〉は最初は選曲に入れてなかったんです。別の曲を入れる予定で、歌ってみたんですけども、なんとなく私のなかで“これ、違うな”と思って。〈喝采〉は河西さんが最初に選んでくれた100何曲のなかには入っていたんですけど、アルバムのタイトルを『喝彩』に決めていたので、“ここに〈喝采〉を入れるといかにもって感じになっちゃうから”と外していたんです。でも1曲なくなったから、“河西さんのリクエストにも入っていた〈喝采〉しかないね”となりました」
――うわ〜。いろいろと奇縁が重なったアルバムですね。
「本当にミラクルばっかりでした。河西さんはアルバムを “〈街の灯り〉で始まって〈あなた〉で締めたい”と言っていたので、〈喝采〉はスタッフ含めてみんなからのプレゼントというか、ボーナス・トラック的な位置で入れましょうと」
――あ、そうだ。「Far away」のお話をまだおうかがいしていませんでしたが、これも藤さんセレクトですよね。
「水越けいこさんの原曲(タイトルは〈Too far away〉)が大好きで、絶対に歌いたいと思ってお願いしたんですけど、ちょうどこの曲のエディットの日、午前11時から作業していたら、その日の午後に谷村新司さんの訃報が届いたんです。“いつか谷村さんにも聴いてほしいね”なんて言ってたのに」
――谷村さんも歌っていらっしゃいましたもんね(〈Far away〉に改題)。何かとドラマチックで、もうため息しか出ません……。
「こんなこと35年やっていて初めてですよ、私たちも。アルバムが完成したその日に河西さんが旅立たれたのも、現実にそんなことあるのかなって。映画のなかにいるような気分でした」
――まいっちゃいそうですが、ふたたび気を取り直して(笑)。藤さんは演歌を歌われることが多いですが、こういうJ-POPを歌うときは心がまえや取り組み方が違ったりしますか?
「私はもともと演歌を聴いてなくて、デビューするまでは洋楽含めてあらゆるポップスやロックを聴いていたんです。同級生には“いつの間に演歌なんか歌えるようになったの?”って不思議がられたりするんですけど(笑)。『喝彩』にはそのころカラオケで歌っていた曲も多いんですけど、その後に演歌を35年歌ってきたので、いま歌うと当時とは全然違うんです。面白いのは、コブシではないけど、ちょっとした“揺れ”みたいなものが、ふと出るんですね。それは演歌を学んでこなかったら出なかった歌唱法だと思います」
――考えてみたら演歌を歌い出してからの人生のほうが長いんですもんね。
「長いんですよ。でも演歌歌手のなかでいちばん演歌を聴いてないと思う(笑)。いまだに歌番組で懐メロ企画があると、ほかの人はみんな知ってるのに私だけ知らないから、必死で覚えていくんです。父親が好きだった川中美幸さんの歌は家でかかっていたし、ヒット曲はなんとなく聴いていましたけど。なので“演歌歌手です”と言いながらも、わかってないんです」
――だからこそなのかな。演歌をスタイルと捉えて、理知的というかクールなアプローチをされている気がします。
「捉え方も違いますね。だからドロドロなすごい内容の歌を歌っても、どっちかと言うとクールなんです。着物を着てジトーッとしてる悲しい女みたいな主人公の歌も、私が歌うとそこまでじゃないんですね。ジーパン穿いてる、みたいな。着物でごまかしてますけど、全然演歌人間じゃないっていう(笑)」
――35周年を締めくくる「女がひとり」のミュージック・ビデオを拝見すると、演じるように踊りながら歌っていらっしゃいます。あの感じはもしかしたらそうしたクールなスタンスから生まれるものなのかなって。
「私、小さいときから民舞をやってたんです。20歳過ぎてからもアルバイトで踊りに行ったりしていたくらい。なので、振りも考えなくても自然に出てくるんです。21歳のときに民謡を習いはじめて、それからコブシを自分で作り出していまに至るという」
――やっぱり特殊ですね、ちょっと。
「本当に特殊です。もともとはソプラノのストレートの発声でしたし。民謡を始めてから2回ぐらい喉を潰して、ちょっとハスキーになったりして。自分で聴いていて“息、漏れてるなぁ”と思いますよ(笑)」
――そんな歌声の魅力もいっぱい発揮された、素敵なアルバムだなと思います。
「うれしいです。河西さんにちょっぴり恩返しができたかな」
――「女がひとり」で35周年を締めくくって、このアルバムからは36年目になるわけですよね。
「本当ですね。信じられません。ふるさとよりも東京のほうが長いってだけでも信じられないのに、ましてや芸能界なんて……(笑)」
――これから40周年を目指して、じゃないですけれど、どういう藤あや子を見せていきたいとお思いですか?
「そういう質問をお受けするたびに思うんですけど、私、本当に何にも考えてないんですよ。やりたいことやってるだけ。“今年はこれを念頭に頑張ります!”みたいなのが何もない。常にゆるゆる状態です。そのぶん、何か来たときにフットワークよく動けるようにしてるつもりではあります」
――いいですね。ヨガっぽい。
「そうそう、ヨガなんですよ。何が来ても対応できるように、とにかく準備をしておく。それが大事です」
――ありがとうございました。僕からはこんなところですが、藤さんから何か言っておきたいことはありますか?
「こちらこそありがとうございました。ちょっと盛って書いてください(笑)」
取材・文/高岡洋詞

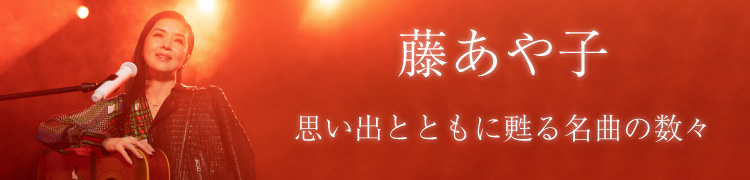






 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。