私たちの生きる世界の、このうえなく美しくて叙情的な部分と、どこか不穏で緊張感に満ちた部分。その二つが混じり合うことなく共存し、不思議な色合いを見せている。ジャズ・ピアニスト魚返明未の最新作『照らす』を繰り返し聴いて、そんな感想を抱いた。何気ない日常と音楽の深遠さとを繋ぐ力を備えた一枚だと思う。
東京藝術大学の作曲科出身で、日本の新世代ジャズを牽引する若き俊英。近年は映画音楽の分野でも活躍し、2023年公開の映画『白鍵と黒鍵の間に』(主演:池松壮亮)は各方面から高い評価を受けている。そんな魚返にとって本作は、6年ぶり3枚目となるピアノ・トリオのアルバムだ。前作からトリオのメンバーを一新。高橋陸(b)、中村海斗(ds)と、まったく新しい音像を提示している。この6年間で何が変わったのか。新境地とも言うべき本作に至るプロセスをじっくり伺った。
――ピアノ・トリオ作品は、2018年の『はしごを抱きしめる』以来6年ぶりですね。今回の『照らす』ではメンバーも一新されていますが、何かアルバムのコンセプトはありましたか?
「いえ、とくに意識はしてなかったです。今のトリオでコンスタントに演奏を始めたのが、2020年くらい。4年間でオリジナル曲も増えたし、ライヴを重ねて3人の演奏もいい状態に練れてきたので、とにかく今のサウンドを、録音物として残したかった。ですから本作には、手持ちのレパートリーを思いきって詰め込みました。もう少し取捨選択すれば、アルバムとして明確なストーリー性が出せたのかもしれないけれど。それよりは今の勢いとか、バンドの空気感を優先しています。ただ、収録曲のほとんどはコロナ禍以降に作ったものなんですね。なので、その期間中に自分が感じたことは、トータルで反映されているかもしれません」
――前作の発表時には、インタビューで「作曲者として達成感があった」とも発言されていました。たしかに楠井五月さん(b)、石若駿(ds)さんとのアンサンブルも非常に新鮮でしたが、それは一度リセットして、新しい展開を模索しようと?
「そうですね。達成感というと聞こえがいいけれど、正直あの時点では、自分の中でちょっと手詰まり感があった気がする。それで前のバンドはいったん解散し、しばらくギタリストの井上銘くんとのデュオに移したんです。でもやっぱり、ジャズのピアニストにとって、トリオという編成は避けては通れないので。その間の経験も踏まえて、いちばんベーシックなスタイルに立ち返ってみたと」
――手詰まり感というのは、具体的にはどういうことでしょう?
「これは完全に、僕の問題です。2人のメンバーを想定して曲を書いていく過程で、だんだん柔軟性がなくなってしまった。たぶん自分の中で、このトリオで奏でるべきサウンドのイメージが固まってしまって。無意識のうちに、それに縛られるようになっていたんだと思います。楠井さんも石若くんも同じ若手でしたけど、僕よりずっと経験が豊富で、すばらしいミュージシャンですから。今にして思えばプレッシャーで背伸びしていた部分もあった気がします。それで言うと、今のトリオはけっこう逆なんですよ。何だろう……作曲者が予想もしなかった方向に、演奏が広がっていくというか」
――こうあらねばという縛りが薄らいで、演奏の風通しがよくなった?
「だと思います。結局、僕自身が音楽に求めるものが変わったんでしょうね。メンバーが突然思いがけないフレーズを奏でたり、急に予想外の展開が始まったりするのを、楽しいと思えるようになってきた。相手の音を、もっと注意深く聴きたい。繊細なニュアンスの一つひとつを全身で受け取って、自分もそれに響き合うようなピアノを弾きたい。ここ数年、とくに強くそう感じるようになりました。その意味では銘くんと組んで、ギターとピアノというちょっと変わった編成に打ち込んだ経験は大きかったかもしれません。あとはコロナ禍で、しばらくライヴ活動ができなかった影響は確実にあったと思う」
――枠から解き放たれた自由さは、今回の『照らす』というアルバムから強く伝わってきました。ベースの高橋陸さん、ドラムの中村海斗さんとは、どのような流れでトリオを結成したのですか?
「2人とも、知り合ったのはけっこう昔なんですよ。陸くんは5つ年下で。僕が20歳頃からセッションのホストをしていたジャズ・バーに、よく遊びにきていました。最初に会ったとき、彼はまだ高校に入りたてだったと思います。その後、2018年くらいかな。僕が参加していた“.push(ドットプッシュ)”というバンドに、彼がベースで加入して。メンバー同士じっくり共演してみたら、すごく波長が合いました。ミュージシャンとしての陸くんは、とにかく予定調和が嫌いなんですね。高い演奏技術は持ちつつも、ジャズの暗黙のルールより瞬間の閃きやアイディアを優先するタイプ。しかもそれが、自己完結していないというか。衝動的に放った音に対して、彼自身が戸惑ってる気配がある(笑)。そこが好きですね」
――なるほど(笑)。今回のアルバムでも、ベースが突っ走り歌いまくってるパートがとても魅力的でした。ドラマーの中村さんは2001年生まれ。魚返さんよりも10歳下の最年少ですね。
「海斗君は中学時代から、前のトリオのライヴを観にきてくれていて。そこで出会ったのが最初ですね。すでに地元・群馬のライヴ・シーンではセッション・ホストを務める腕前で。僕自身、ゲストで呼んでもらったこともあります。彼のドラムが素敵なのは、スピード感と柔らかさの両方を兼ね備えていること。柔らかいタッチと柔軟なリズム感覚で、とかく前のめりになりがちな僕のピアノに寄り添い、包みこんでくれる安心感があります。この2人となら、前のトリオとはまた違った、開かれた演奏ができるんじゃないかなと思って。僕から声をかけて、コロナ禍の2020年頃から少しずつ演奏の機会を増やしてきました」
――高橋さんと中村さんは、魚返さんが音楽を手がけた映画『白鍵と黒鍵の間に』(2023年)のサントラにも参加されています。ライヴを中心に、さまざまなシーンを通じて関係を熟成させてきたと。
「ですね。ステージでの瞬間的なやりとり、いわゆるインタープレイの緊密さもかなり上がってきたと思います。僕自身もいろんなレベルでインスパイアされますし、演奏中も一つの場所にとどまっている感覚がない。それこそ、この2人の音をもっと聴きたい。全力で耳を澄まし、ヴィヴィッドに反応することで、自分も新しい音を紡ぎだしたい。心からそう思わせてくれる関係です。陸くんも海斗くんもたぶん、そういうトリオのあり方を面白がってくれてると思う」
――その意味では、本作のタイトル・ナンバー「照らす」は象徴的ですね。この曲には、キャッチーではっきりしたメロディ・ラインは見当たりません。魚返さん自身はライナーノーツの楽曲解説で「小さな懐中電灯くらいの灯り」のイメージと書いておられましたが。
「はははは(笑)、書いてましたね」
――たしかにこの曲のピアノは、どこか輪郭のにじんだ光を思わせます。そういう独特なサウンドに、たゆたうように歌うベース、さざ波のように寄せては返すドラムスが響き合って。リリカルな世界像を織り上げていく。10分を超える長さですが心地よい緊張感がずっと持続し、リスナーを引き込みます。
「そう感じてもらえたのなら、すごくうれしいです。この曲はじつは、着想段階ではもう少しはっきりした構造を持っていたんです。ビートも一定で、よりパワフルなイメージだった。でも2人のプレイを想像しながら推敲するうちに、いつしかリズムに揺らぎが出てきて。結局、今のようなちょっと流動的な形に行き着きました。まあ僕自身、もともと明るい陽光よりも、暗闇を仄かに照らす灯りに惹かれるところがあるので(笑)。そういう自分の気質みたいなものも、たぶん無意識ににじんでるんじゃないかなと」
――暗闇の中の仄明かりというイメージは今回、ジャケットのモチーフにもなっていますね。誰もいない深夜の自動販売機というのは、魚返さんのアイディアですか?
「いえ、これは友人のデザイナーが提案してくれました。あらかじめ収録曲のタイトルは伝えていたので。たぶんそこから連想して、イラストを起こしてくれたんじゃないかな。たしかに今回のアルバムの内容と絶妙に響き合っている感じがして、すごく気に入っています」
――自販機の灯りって、この世の中でもっとも顧みられない光というか。ふだん、気に留める人はほとんどいないですよね。でも確実にそこにあって、人知れず路上を照らしている。
「そうそう、そうなんですよ」
――そういうささやかな温かさ、不穏さの中に見え隠れする希望みたいなトーンは、じつは今回の『照らす』というアルバム全体に通底している気がします。
「はい。最初にお話ししたコロナ禍の残響というのは結局、そこに繋がっているんだと思います。じつはこのイラスト、よく見ると路上に百円玉が落ちてるんですよ。自販機の青白い光が、硬貨をぼんやり照らしている。個人的にはそこに、一つのコミュニケーションを感じるというか(笑)。内気な自分もそんなささやかな感じで、誰かと繋がっていたいなと。周りのミュージシャンの音からもっといろんなことを感じ、受け入れることで自分自身も変わっていきたい。コロナ禍以降、そういう意識は作曲にも演奏にも強くにじむようになった気がします。あと、構成的な面で言いますと、〈照らす〉という曲はストーリーテリングの単位が短い。ゆらゆらと不定形にたゆたっているようで、じつは短いリフレインを繰り返す作りになっています。それを3人で重ねていく中で、徐々に音の渦が大きくなっていくイメージ。これは〈照らす〉だけでなく、たぶん今回のアルバム全体の傾向ですね」
――前のトリオの作品に比べて、どの曲も総じてミニマルな構成になっていると。それもまた、プレイヤーの個性に合わせて自然に変わってきたわけですか?
「そうですね。ジャズというのは、突き詰めればループの音楽だと思うんですけど、やっぱり最小単位が短いほうがその瞬間の閃きを生かしやすい。演奏中に何かアイディアが浮かんだら、次のターンですぐ試せますからね。たとえば前のアルバムでは32小節で語っていたことを、本作では16小節とか8小節に凝縮しているというか。今のトリオの個性としてそこは大きいと思います。起承転結のストーリー性から、よりプリミティヴなルーツ音楽に近づいた感覚ですかね。あえてブルース的、と言ってもいいかもしれない」
――面白いですね。サウンド的にはブルースの匂いがほとんどしない。むしろかけ離れた印象があります。
「僕らは通常、いわゆるブルース・コードとはまったく違った和音を使って演奏しているので。連想する方は少ないかもしれませんね。でも短いシークエンスを繰り返すという意味で、楽曲の構造はどんどんブルースに近づいていると思う。それで言うと1曲目の〈曇り空〉もそうですね。この曲ではシンプルなメロディに、いろんなコードやハーモニーを次々にあてている。何だろう、1人の役者さんがずっと舞台に立っていて、ライティングだけが果てしなく変わっていくようなイメージ」
――なるほど。そこにもブルース的な構造の面白さがある。
「たとえば楽曲の中心に強烈な磁場みたいなものが存在して。そこに近づいたり離れたりするのがブルースの面白さだとするならば、自分たちが今やっている音楽は完全にそれだと思います。中心からの距離がどんなに遠くなっても、磁場そのものが消えることはない。そうやってループする感覚は、陸くんと海斗くんもきっちり共有してくれてるんじゃないかなと。あえて言葉で確認したことはないですけど」
――トリオ内でそういう話はあまりしませんか?
「しませんね。大ざっぱな言い方ですけど、メンバー3人とも不器用な性格なので。言葉にしちゃうとそれが独り歩きして、たぶん嘘の部分が増えてきちゃう。なので、演奏で語り合ってるほうがいいのかなと(笑)」
――4曲目の「アルコールジェル」は、魚返さんいわく「ジェルタイプの消毒液のネバネバした感触」を連想させるナンバー。つんのめるリズム、濁った和音はどこかセロニアス・モンクを思わせます。
「この曲は導入部のパートのみ事前に決めていて、それ以降は完全に即興。ある意味、各プレイヤーの個性がもっともダイレクトにぶつかり合ってる曲です。導入部のリフレイン要素も、このアルバムでいちばん短いと思います。その意味でもプリミティヴな匂いが強いナンバーですね。血が沸き立つようなアドリブがあって、ふと気付けば自分が立っていた地面がなくなっているような(笑)。そんな面白さを狙ってみました」
――アルバムのクライマックスとも言える6曲目「棘」と7曲目「Normal Temperature」は、ひと連なりの組曲のように聞こえました。スケール感のあるイントロダクションから、印象的なベースのブリッジを挟んで、緊張とスピード感に満ちた楽曲へとなだれ込んでいくという。
「最初は別べつの曲として演ってたんですけど、〈棘〉はさっきお話しした意味合いでのブルース構造が薄いと言いますか。独立したナンバーとして収録すると、今回のアルバム内では少し浮きそうな気がしたんですね。それで〈Normal Temperature〉の前奏曲的な位置づけにしてみた。わりと現実的な理由です」
――「Normal Temperature」の導入部分では、5つの音が執拗に繰り返されます。8分強の演奏を通して、3人がその5音の桎梏(しっこく)から逃れようと格闘している趣がある。伝わってくるのは、平熱とはほとんど正反対のフィーリングです。
「この曲を書いたのは2021年の夏で、誰もが否応なく、平熱で過ごすことを意識せざるをえない時期でした。そのとき感じたひっかかり、違和感が作曲のベースにあるので。それでどこか、牢屋に閉じ込められているような閉塞感、そこから逃げ出したいという焦燥感に繋がっているのかもしれませんね」
――アルバム後半の高ぶり方がすさまじかったです。ライヴでぜひ観たいと感じました。4月28日(日)の東京・新宿ピットインを皮切りに、全国ツアーも予定されています。今後、トリオとして、どういった活動をしていきたいですか?
「考えていることは至ってシンプルで、このトリオのためにどんどん曲を書いて、ライヴで育てていきたい。で、どんな状況でも刺激的な音楽が生み出せるように、3人で経験を重ねていきたいですね。とはいえバンドとしては、やっとスタートラインに立てた感覚なので。まずは全国ツアーをしっかり走りきって、それを踏まえて次のアルバムに向き合えればいいなと。そう思えるメンバーと出会えて、演奏できていることが、今はすごくうれしいです」
取材・文/大谷隆之
〈魚返明未トリオ ニューアルバムリリースライブ〉4月28日(日)東京・新宿 Pit Inn、6月5日(水)鹿児島・Heaven、6月6日(木)熊本・tsukimi、6月7日(金)福岡・博多 New Combo、6月8日(土)大分・Naima、6月20日(木)静岡・浜松 Hermit Dolphin、6月21日(金)愛知・名古屋 Mr. Kenny’s、6月22日(土)岐阜・アイランドカフェ、6月23日(日)兵庫・神戸 zing、6月24日(月)広島・Bird、6月26日(水)岡山・SOHO、6月27日(木)大阪・Gallon、6月28日(金)三重・松坂 Serai、6月29日(土)静岡・藤枝 Body&Soul
〈ツアー・ファイナル〉
7月17日(水)東京・丸の内 Cotton Club
https://www.cottonclubjapan.co.jp/jp/sp/artists/ami-ogaeri/ 
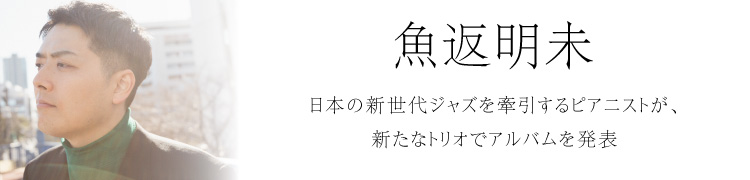




 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。