
――オーストラリア育ちですよね。ニューヨークに移ったのはいつですか。
スコット・マシュー(以下同) 「97年3月。それまではシドニーに住んでいたんだけど、うんざりしてしまって。オーストラリアは地理的に孤立していて、世界から取り残されているような感覚があるんだ。今は大好きだよ。里帰りもするし、故郷だと思っている。住みたいとは思わないだけでね(笑)」
――ニューヨークに12年住んでいて変わったことは?
「前ほどはエキサイティングじゃないけど、まあ僕が街に慣れたということもあるかも。でも街そのものも変わったよね。ずいぶん商業的になったし、カネがかかるようになった。クリエイティヴな人たちが住めなくなって、創造性が低下したと思う。ただ、僕は基本的にいつもツアーしているから、四六時中ニューヨークにいるわけじゃないんだ。おかげで今も街を堪能できているのはラッキーだね」
――映画を通して名が売れてきたところがあると思いますが、『ショートバス』に出演された経緯は?
「完全な偶然なんだ。あるパーティでジョン・キャメロン・ミッチェルに会ったとき、彼はすでに脚本を書き上げてシンガー・ソングライターの役を探していた。じゃあよかったら、ってCDを渡したら気に入ってくれて、脚本を読ませてもらっていくつか曲を書いて……まさにトントン拍子だったね」
――本来シンガー・ソングライターのスコットさんですが、アニメの仕事ではシンガーに徹しましたね。
「素晴らしい経験だったよ。よう子さんは才能豊かで親切で、いい音楽を作るために適材を適所に配するセンスに長けている。スタジオでも“こういう歌い方を試してみてもいいんじゃないかな”みたいな優しい口調で指示を出すんだ。形容詞を巧みに使って、イメージをつかめるよう工夫してくれる。とても聡明な人だね」
――菅野さんやミッチェルがあなたを起用したくなった理由はわかる気がするんです。歌声がすごく個性豊かでエモーショナルだから。声に物語があるというか。
「ありがとう。あなたの言う通りだと思います。彼らは“こんな声しかほしくない”というくらい明確なイメージを持ってシンガーを探していた。僕は“こんな声でしか歌えない”から、ピタッときたんだね」

――悲しい声だねって言われますか。
「聴いた人は必ず言うよ。幸せそうな声だねって言われたことはないし、もし言われたら“君、おかしいよ”って答えるだろうね(笑)」
――歌にも悲しい言葉がいっぱい出てくる。自分は悲観的だと思いますか?
「そういうときもある、って感じかな。だれでもそうだと思うよ。いつもハッピーなんておかしいものね。僕も愉快なときもあれば悲痛なときもある。ただ、曲を書きたくなるのは悲しいときなんだ」
――幸福よりも悲しみや痛みがあなたにとってソングライティングの原動力になるってことですね。
「そう。悲しい歌には美しい歌が多いと思う。むしろ美しさの問題だよ。美しいものを作りたいんだ」
――好きな歌はやっぱり悲しいものが多いですか。
「イエス。いちばん好きなのは
ロバータ・フラックの〈ジェシー〉って曲なんだ。出て行った男に“寂しいわ、帰ってきて”と女が呼びかける歌。男が戻ってきたときのために毎日、テーブルを用意し、階段の灯りをつけるけれど、彼が帰らないと知っているんだ。悲しいでしょ。ニ番めに好きなのも彼女の〈ドゥ・ホワット・ユー・ガッタ・ドゥ〉で、ひどい目に遭わされた女が相手の男に、“悪いのは私よ、私のことは気にしないで好きなことをしてちょうだい”と語りかける」
――話を聞いてるだけでウルウルきました。
「ごめんね〜(笑)」
――『THERE IS AN OCEAN THAT DIVIDES|AND WITH MY LONGING I CAN CHARGE IT|WITH A VOLTAGE THATS SO VIOLENT|TO CROSS IT COULD MEAN DEATH』はサウンドも印象的です。アコーディオン、ストリングス、ウクレレと、ポップ・ミュージックには珍しいアンサンブル。これはあえて?
「はい。成熟した大人の音楽にしたかったので。1stを作ったときは自分が何をやっているのかいまひとつわかっていなくて、明確なヴィジョンを持ち得なかったんだ。それはそれで誇りに思っているけど、2ndではさらに内容を高めることが重要だった。プロフェッショナルなレコードを目指したんだ」
――ウクレレを弾きながら歌うのもちょっと珍しいですよね。タイニー・ティムが思い当たるくらいで。 「タイニー・ティム! ♪Tiptoe through the tulips...」
――ウクレレを手にしたきっかけは?
「必要に迫られて。手を怪我してからうまくギターが弾けなくなってしまってね。でも曲作りは続けたかったから、前から弾いていたウクレレで書くことにしたわけ。ハッピーで明るいサウンドとして使われてきた楽器だけど、僕はちょっと違う使い方をしたいんだ。〈WHITE HORSE〉ではハープみたいな音を出しているよ」
取材・文/高岡洋詞(2009年7月)

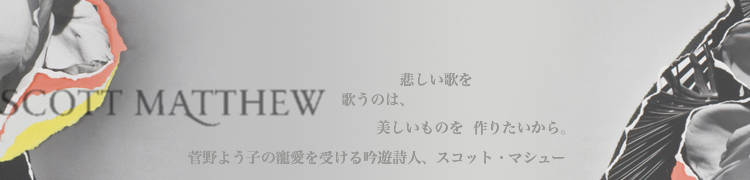



 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。