“キング・オブ・ロック”ブライアン・セッツァーの
果てなきロックンロールの追求
パンク / ニューウェイヴの時代に
ロカビリーを蘇らせたストレイ・キャッツ

ロックンロールは大好きだ。しかし、時折使われる日本語の“ロケンロー”という言葉というか表記は――たとえ、それが英語の発音に忠実だったとしても、あまり好きになれない。なぜなら、大好きなロックンロールが貶められているように感じられるからだ。ロケンローなんて言ってしまうと、まるでロックンロールが軽薄で、単純な音楽のように聞こえはしないか?
もちろん、ロックンロールは極めてシンプルな音楽であり、シンプルであることが最大の魅力と言ってもいい。しかし、だからと言って、ロックンロールが馬鹿の一つ覚えを繰り返していればそれでいい、単純な音楽だとは思わない。
もしロックンロールを、そういう音楽だと考えている音楽ファンがいるなら、ぜひ
ブライアン・セッツァーの作品を聴いてみてほしい。ロックンロールがいかに奥の深い音楽であるかがきっと理解できることだろう。ひょっとすると、リーゼントをはじめとするその50年代風のファッションから、セッツァーのことを、古き良き時代のロックンロール――つまりオールディーズを現代に継承しているミュージシャンと勘違いしている人もいるかもしれない。
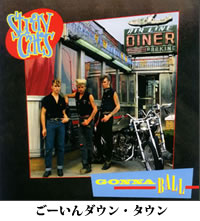
もちろん、彼が作る音楽には、そういう一面もあるし、そこが好きだというファンもいるだろう。しかし、30年に及ぶセッツァーのキャリアはロックンロールの伝統や様式美をしっかりと受け継ぎながら、常にロックンロールという音楽の可能性を追求するものだった。
なぜ、セッツァーが今、キング・オブ・ロックンロールと謳われているか? それは決して十年一日のごとくロックンロールを演奏しつづけてきたからではない。
ブライアン・セッツァー(ヴォーカル、ギター)が79年頃、ニューヨークで
リー・ロッカー(ウッド・ベース)、スリム・ジム・ファントム(ドラムス)と結成したトリオ、
ストレイ・キャッツは翌80年、イギリスでレコード・デビューを飾ると、パンク/ニュー・ウェイヴの時代にロカビリーを蘇らせ、ロック・シーンに衝撃を与えた。「涙のラナウェイ・ボーイ」「ロック・タウンは恋の街」「気取りやキャット」と次々にヒットを飛ばしていった彼らに多くのバンドが続き、それはネオ・ロカビリー・ブームに発展していった。

ストレイ・キャッツはロカビリーのリヴァイヴァルととらえられていたわけではなかった。それは彼らがロカビリーとは一緒にできないということで、ネオ・ロカビリー、あるいはパンカビリーと呼ばれたことからもわかるだろう。新しいタイプのロックンロール・バンドとして、幅広いリスナーに歓迎された彼らに
ローリング・ストーンズ、
クラッシュ、
エルヴィス・コステロら、多くのミュージシャンが羨望の眼差しを向けた。
そして、逆輸入という形で、本国アメリカでも大成功を収めた彼らは、頂点を極めたバンドの常なのか、やがてモチベーションを失っていき、
『涙のラナウェイ・ボーイ』『ごーいんダウン・タウン』『セクシー&セブンティーン』3枚のアルバム(と1枚目と2枚目を編集したアメリカ・デビュー盤『ビルト・フォー・スピード』)を残して、85年に解散してしまった。その後、ストレイ・キャッツ再結成、ソロ・デビュー、ストレイ・キャッツ再々結成を経て、セッツァーは92年、17人編成のブライアン・セッツァー・オーケストラ(以下BSO)を結成した。
ビッグ・バンド・スタイルの“オーケストラ”など
ロックの可能性を広げる、衰えぬ創作意欲

ロックンロール誕生以前のビッグ・バンドのスタイルでロックンロールを演奏してみたい――それは長年、温めていたアイディアだったそうだ。つまり、かつて自らのバックボーンであるロカビリーとパンクのビートを結びつけ、新しいロックンロールを生み出したセッツァーは、今度はロカビリーとスウィング・ジャズとジャンプ・ブルースを結びつけることによって、新しいロックンロールを生み出そうと考えたわけだ。
しかし、時代が早すぎたのか、この大胆なアイディアはなかなか受け入れられなかった。94年にリリースしたBSO名義の1stアルバム
『ブライアン・セッツァー・オーケストラ』、96年にリリースした2ndアルバム
『ギター・スリンガー』ともにセールス面では奮わなかった。それでも彼はあきらめず、BSOを率い、ステージに立ちつづけた。
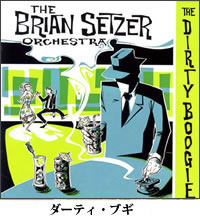
そして、98年。地道な活動がついに認められ、BSO名義の3作目となる
『ダーティ・ブギ』が全米チャートの9位に食い込む大ヒットになり、グラミーも受賞した。
80年代後半からサンフランシスコとロサンゼルスで胎動を始めていた新しいロックンロール――ネオ・スウィングが、ちょうどこの頃、全米規模のブームに発展したことも追い風になったにちがいない。いや、セッツァーの活動がネオ・スウィング・ブームを拡大させたと考えるべきか。いずれにせよ、起死回生とも言える『ダーティ・ブギ』の成功によって、再びロック・シーンの頂点を極めたセッツァーは現在もBSOとトリオをフレキシブルに使い分けたレコーディングおよびライヴ活動を精力的に続けている。

そんなセッツァーの創作意欲、ロックンロールの領域を広げるイマジネーションは衰えることがないようだ。たとえば、2007年にリリースしたBSO名義の
『ウルフギャングズ・ビッグ・ナイト・アウト』は、どうだ。
ベートーヴェンの「交響曲第五番 運命」ほか、クラシックの名曲の数々をスウィンギーにアレンジしたこのアルバムには、セッツァーの魅力を知り尽くしている昔からのファンも驚かされたにちがいない。
ストレイ・キャッツ〜BSOを通して、50年代のロカビリーのみならず、ロックンロール、ブルース、R&B、カントリー、スウィング・ジャズ、ジャンプ・ブルースなど、さまざまなジャンルの曲を取り上げ、豊かなバックグラウンドを開陳してきたセッツァーではあるけれど、まさかその興味の対象がクラシックまでだったとは!
取り組み方しだいでロックンロールはまだまだどんなふうにでも発展させることができる。セッツァーのアルバムを聴いていると、そんなことを思わずにいられない。無限の可能性を秘めた、そういう音楽を、“ロケンロー”などという軽薄な言葉で言い表していいわけがないだろう。

今年50歳になったセッツァーの最新作
『ソングス・フロム・ロンリー・アヴェニュー』は、BSO名義としては、2000年発表の
『ヴァヴーム!』以来9年ぶりとなる完全オリジナル・アルバムだ。
40〜50年代の暗黒映画のサウンドトラックをイメージして作り上げた、ある意味コンセプチュアルな作品ではあるけれど、ハードボイルドなストーリーを頭に思い浮かべながら曲作りしたせいか、オープニングの「トラブル・トレイン」から、ほぼ全編でセッツァーが弾きまくるアグレッシヴなギターは、新旧のファンを狂喜させることだろう。
ゴージャスなオーケストラ・サウンドとハード・ロッキンなギター・プレイの融合を実現させた最新アルバムは、ストレイ・キャッツ時代からセッツァーが追求してきた新しいロックンロールの集大成と言ってもいい。ちなみに全曲、セッツァーによるオリジナルというアルバムは、キャリア初だそうだ。
文/山口智男
 ロックンロールは大好きだ。しかし、時折使われる日本語の“ロケンロー”という言葉というか表記は――たとえ、それが英語の発音に忠実だったとしても、あまり好きになれない。なぜなら、大好きなロックンロールが貶められているように感じられるからだ。ロケンローなんて言ってしまうと、まるでロックンロールが軽薄で、単純な音楽のように聞こえはしないか?
ロックンロールは大好きだ。しかし、時折使われる日本語の“ロケンロー”という言葉というか表記は――たとえ、それが英語の発音に忠実だったとしても、あまり好きになれない。なぜなら、大好きなロックンロールが貶められているように感じられるからだ。ロケンローなんて言ってしまうと、まるでロックンロールが軽薄で、単純な音楽のように聞こえはしないか?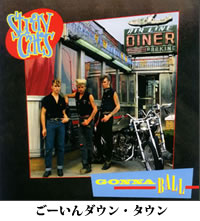 もちろん、彼が作る音楽には、そういう一面もあるし、そこが好きだというファンもいるだろう。しかし、30年に及ぶセッツァーのキャリアはロックンロールの伝統や様式美をしっかりと受け継ぎながら、常にロックンロールという音楽の可能性を追求するものだった。
もちろん、彼が作る音楽には、そういう一面もあるし、そこが好きだというファンもいるだろう。しかし、30年に及ぶセッツァーのキャリアはロックンロールの伝統や様式美をしっかりと受け継ぎながら、常にロックンロールという音楽の可能性を追求するものだった。 ストレイ・キャッツはロカビリーのリヴァイヴァルととらえられていたわけではなかった。それは彼らがロカビリーとは一緒にできないということで、ネオ・ロカビリー、あるいはパンカビリーと呼ばれたことからもわかるだろう。新しいタイプのロックンロール・バンドとして、幅広いリスナーに歓迎された彼らにローリング・ストーンズ、クラッシュ、エルヴィス・コステロら、多くのミュージシャンが羨望の眼差しを向けた。
ストレイ・キャッツはロカビリーのリヴァイヴァルととらえられていたわけではなかった。それは彼らがロカビリーとは一緒にできないということで、ネオ・ロカビリー、あるいはパンカビリーと呼ばれたことからもわかるだろう。新しいタイプのロックンロール・バンドとして、幅広いリスナーに歓迎された彼らにローリング・ストーンズ、クラッシュ、エルヴィス・コステロら、多くのミュージシャンが羨望の眼差しを向けた。 ロックンロール誕生以前のビッグ・バンドのスタイルでロックンロールを演奏してみたい――それは長年、温めていたアイディアだったそうだ。つまり、かつて自らのバックボーンであるロカビリーとパンクのビートを結びつけ、新しいロックンロールを生み出したセッツァーは、今度はロカビリーとスウィング・ジャズとジャンプ・ブルースを結びつけることによって、新しいロックンロールを生み出そうと考えたわけだ。
ロックンロール誕生以前のビッグ・バンドのスタイルでロックンロールを演奏してみたい――それは長年、温めていたアイディアだったそうだ。つまり、かつて自らのバックボーンであるロカビリーとパンクのビートを結びつけ、新しいロックンロールを生み出したセッツァーは、今度はロカビリーとスウィング・ジャズとジャンプ・ブルースを結びつけることによって、新しいロックンロールを生み出そうと考えたわけだ。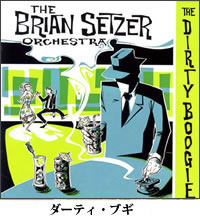 そして、98年。地道な活動がついに認められ、BSO名義の3作目となる『ダーティ・ブギ』が全米チャートの9位に食い込む大ヒットになり、グラミーも受賞した。
そして、98年。地道な活動がついに認められ、BSO名義の3作目となる『ダーティ・ブギ』が全米チャートの9位に食い込む大ヒットになり、グラミーも受賞した。 そんなセッツァーの創作意欲、ロックンロールの領域を広げるイマジネーションは衰えることがないようだ。たとえば、2007年にリリースしたBSO名義の『ウルフギャングズ・ビッグ・ナイト・アウト』は、どうだ。ベートーヴェンの「交響曲第五番 運命」ほか、クラシックの名曲の数々をスウィンギーにアレンジしたこのアルバムには、セッツァーの魅力を知り尽くしている昔からのファンも驚かされたにちがいない。
そんなセッツァーの創作意欲、ロックンロールの領域を広げるイマジネーションは衰えることがないようだ。たとえば、2007年にリリースしたBSO名義の『ウルフギャングズ・ビッグ・ナイト・アウト』は、どうだ。ベートーヴェンの「交響曲第五番 運命」ほか、クラシックの名曲の数々をスウィンギーにアレンジしたこのアルバムには、セッツァーの魅力を知り尽くしている昔からのファンも驚かされたにちがいない。 今年50歳になったセッツァーの最新作『ソングス・フロム・ロンリー・アヴェニュー』は、BSO名義としては、2000年発表の『ヴァヴーム!』以来9年ぶりとなる完全オリジナル・アルバムだ。
今年50歳になったセッツァーの最新作『ソングス・フロム・ロンリー・アヴェニュー』は、BSO名義としては、2000年発表の『ヴァヴーム!』以来9年ぶりとなる完全オリジナル・アルバムだ。
 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。