小島麻由美が帰ってきた! フレンチ・ポップス、ジプシー・ジャズ、ブルース、ロックステディ、昭和歌謡など、軽々とジャンルを横断し、ありきたりのロックには飽き足らない貪欲なリスナーを狂喜させてきた彼女は、1995年のデビューから長きにわたって在籍したポニーキャニオンを離れ、心機一転、インディ・レーベルへと移籍。このたび4年ぶりに発表された新作アルバム
『ブルーロンド』には、これまでとは一味違った開放的な彼女の姿が詰まっている。有象無象の凡百女性シンガーの追随を許さぬ15年選手、小島麻由美を新たなステージに駆り立てたものとは?
小島麻由美(以下、同)「ASA-CHANGはもちろん最高のドラマーなんだけど、それだけに、とにかく忙しいんですよ。残念ながら、もう少しスケジュールが押さえやすいメンバーじゃないと、このご時世、ソロ・シンガーは活動ができない(笑)」
――いざドラマーが替わってみて、最初の印象はどうでしたか。
「“すごい、ドラマーひとつでここまで音楽って変わるんだ!”って感じで、新鮮でしたね。熱いハートがあって、すごーいかっこいい。自分の中では最近、60年代っぽいものが流行ってたんですよ。八馬さんのドラム、
ビートルズっぽいじゃないですか? バタバタしてて、スウィンギンなASA-CHANGとは全然違う。パンキッシュというか、ロッキン」
 ――リズム面での変化は、曲作りにも影響を及ぼしたりしたんですか?
――リズム面での変化は、曲作りにも影響を及ぼしたりしたんですか? 「今回のアルバムの曲は、ほとんど全部、八馬さんのドラミングの影響を受けてますよ。今まで自分がやってみたいとイメージしていたのにできなかったタイプの曲が、スポーンって出てきた。気持ちよかったですね。ライヴでも、これまでは今ひとつ抜けの悪かった、ちょっと違和感のあった曲が、八馬さんが叩くことでドンピシャになる」
――ひょっとするとその辺り、小島さん自身の志向の変化も反映されているんでしょうか。
「思いがけず長い間音楽を続けてきましたけど、最近途端に、マイナー・スウィングみたいなものが、ハートに来なくなったんですよね」
――ジャンゴ・ラインハルトをはじめとするマイナー・スウィングは、小島さんの音楽性を語るキーワードとして頻繁に用いられます。 「ジャンゴとか、実際レコードを聴けば燃えるんですけどね。ただ、それを自分の音楽に反映させるとなると、今までの焼き直しみたいなものだという感覚からどうしても離れられない。ブンチャ、ブンチャっていう感じとか、ジンタとか、そういう音楽は、この前のアルバム
『スウィンギン・キャラバン』で結構やり尽くした気がするんですね。ちょうどそんな時、八馬さんのドラムを聴いたら、“うわっ、これだー!”って。1枚通して思うのは、ここまで声を張れる曲ばかりが集まったアルバムはなかったということですね」
――『ブルーロンド』のリリース日は、当初の予定から3度、延期を繰り返しています。
「もっと早くレコーディングが終わっているはずだったのに、終わらないまま夏のツアーに入ったのが痛かったですね」
――曲作りに難航したとか?
「曲は割とすぐ書けるんですよ。やっぱり、歌詞の部分で苦労しました。今回は、アルバム全体を派手にしたいな、リズムを強いものにしたいなという気持ちがあったんで、どうしても歌詞が後回しになってしまう。バラードなら、割とすぐに歌詞が書けるんですけど、今回はアッパーな曲が多かったから」
――メジャーからインディに移籍したことで、何か具体的な変化はありました?
「何かね、フットワークが軽い気がするなあ。簡単な話し合いと電話連絡で次々進めていく感じが、ちょっと衝撃的でした。メジャーにいた時は、会議、会議の連続だったから(笑)」
――考えてみれば、小島さんのデビューから15年が経ちました。もう37歳なんですね。
「若い頃に見ていた
矢野顕子や
大貫妙子って、今の自分ぐらいの年齢だったんでしょうね。当時はすごいおばさんだと思ってたけど、自分がその立場になるとは……(笑)」
――同じ年にデビューしたアーティストには誰がいるんでしたっけ?
――デビューした頃、15年後に自分がシンガーを続けてるとは想像してました?
「全然! アルバム1枚ぐらいで終わりかと思ってました(笑)」
――最後に、久しぶりのアルバムを作り終えての感慨を聞かせてください。
「もう、すごい最高(笑)。今までのアルバムには、ちゃんと到達できなかったという悔いの残るものもあったんですね、ぶっちゃけ。例えば、トラックダウンなんかの些細なことで後悔して、やたらと周りの人に、“どう?”って質問したりとか。そういう時は、インタビューも暗い(笑)。でも、今回はもう、すごい、ちゃんと仕上がったと思ってるんで、堂々と、聴いてくださいって言うだけですね」
取材・文/下井草秀(2010年1月)


 ――リズム面での変化は、曲作りにも影響を及ぼしたりしたんですか?
――リズム面での変化は、曲作りにも影響を及ぼしたりしたんですか?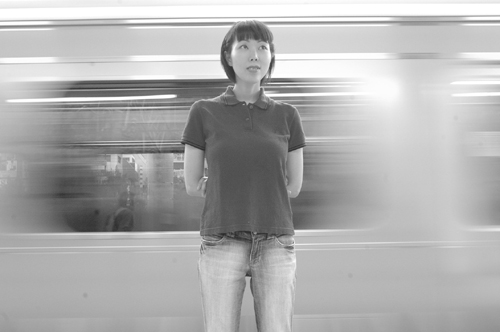

 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。