――まずは前作『Gloomy』を振り返っていただきたいんですが、今の志磨さんにとってどういう作品でしょう?
志磨遼平(以下、同) 「自分でも位置づけが難しい。僕はそれまで“人間=ロックンロール”というものに絶対的な信頼を置いて生きてきたんですけど、それに疑問を感じて何を歌っていいのかわからない状態になっちゃったんです。だから、音楽聴く気もない状態からいきなりスタジオに入ってなんでもかんでも録音していくっていう……。あのアルバムはある種のショック療法でした」
――リリース時にそういう状況を吐露されてましたね。
「皮肉なもので、それがこれまで以上に支持されて、たくさんの人から“すばらしい”と言うてもらえたりしたんですが、悪く言えば、自殺未遂を“死ぬ気マンマンでいいね!”ってほめられるような感じ(苦笑)。だから、作品というよりは“そういう時期があった”っていう記録みたいなところもあって。僕は“ジョンタマ状態”って言うてるんですけど(笑)、まさに
『ジョンの魂』の
ジョン・レノン、“世界平和!”じゃなくて、自分と自分の愛する人の小さい世界が平和でありますように……っていうものすごくささやかな音楽ですね」
――それが最新作『毛皮のマリーズ』の、言わば“ひらけた”感じに至ると。何があったんでしょう?
「『Gloomy』の曲順は練ったにもかかわらず並べてみたら作った順になってて、そこも記録っぽいんですけど、最後の曲が書けたときに、自分と音楽の関係性を把握できたんですね。音楽に例えようもないたくさんの感情が、自分にもみなさんにもある。だから、音楽を音楽として愛でるというか、音楽はそれ以上でもそれ以下でもない、と一気に裏返って全部が外に向いたんです」
――なるほど。“つきぬけた!”的な作品かと思ってたんですが、少し違うようですね。
「なんらかの“みそぎ”だったような気はします。それで、リリース前日のライヴで背中を骨折したと同時に肺炎も発覚しまして、寝たきりの状態で発売日を迎えたわけです(苦笑)。完全な受け身状態の中、いろんなお褒めの言葉が届いたりで、周りが急に動き出したんですね、自分は寝たきりなのに(笑)。そこに、
(忌野)清志郎さんが亡くなるってことがあって……。僕は清志郎さんの音楽にすごく救われてきたんですが、ふと気付けば僕が“『Gloomy』に救われました”とか言われるようになってる。じゃあ、と寝たきりの状態で毎日考えまして。そうして出た答えのひとつが、我々は“毛皮のマリーズ”って名前の──恥ずかしい言い方ですが──みんなの“希望”である、ということ。そんな大きな希望の音楽を作ろうっていうのがこの『毛皮のマリーズ』だったんです」
「なるほどなるほど! 僕も大好きです」
「そういう熱に浮かされたものがふっと落ちついた後は、自分の足下がちゃんと地に着いてることを確認するのかもしれませんね。プライマル・スクリームといえば、僕は勝手にシンパシー抱いてるんですけど(笑)」
――だから『毛皮のマリーズ』は“メンフィス詣で”アルバムだと思うんです。メンフィス行ってませんが(笑)。
「“希望”が見えた時点で、やるならぜったいスリー・コードのロックンロールだ!ってのは決まりました。それは礼儀というか、ずっと親しんで演奏してきた音楽ですから。20歳くらいの頃、こういうロックンロールをやってたんですけど、なかなか理解を得られなかった。僕らは、ちょっと背伸びをして古いロックをやりたい若いコたちで、今回のアーティスト写真はちょっとスゴいけど、実はその頃もこんな格好してまして。今思えばなかなか勘違いが多かったもんですから、うまく伝わらなくて悔しい思いをしたり」
――そうだったんですね。
「そこで当時、年相応のことをしないと悪意をもって斜に構えて見られる、ということが分かりまして。それが本当に不本意だったので、“じゃあ若者らしい肉体性のある音楽を演ろう!”と
ストゥージズや
MC5、ニューヨーク・パンク、グラム・ロックなんかをごちゃ混ぜにしてワーワーやったところ──僕らは“パンク化”と呼んでますけど──注目されるようになりまして……。そこからの原点回帰というか」
――これまでのどの作品よりもロックンロール濃度、とくに“ロール”成分が濃いですね。“ロック”するのは、テンション上げれば簡単と言えば簡単ですけど、ロールするのは実は簡単じゃない。
「ロックンロールは筋肉というか、アキレス腱が要りますからね」
――正直、これまでの毛皮のマリーズのテンションを愛してた人にとって最初は“?”かもしれないですけど、何回も聴いてるうちに腰にくる、そんな作品だと思います。
「もしくは一回あきらめて10年後くらいに中古盤で買い直してもらうとか、4〜5年後に引っ越しのときにひょっこり出てきてもう一回聴いてもらうとか(笑)。“あれ? これ当時わからんかったけど、いいなー”ってなると思う。若い子がどんだけ反応するんやろなあと楽しみですね」
取材・文/フミヤマウチ(2010年4月)

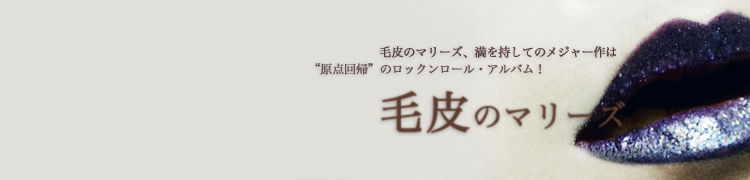



 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。