――“弾き語りが多めな作品に仕上がるんじゃないか?”って予想をみんなが持っていたと思うんですけど。
蔡忠浩(以下、同) 「だろうと思ってました。来年はbonobosが結成10周年で、その前にワンクッション置くというか、違うアクションを起こしたいと考えていて。以前、大学時代の友人の個展のためにTENORI-ON(テノリオン)とか電子楽器を使って抽象的な音楽を作ったりしたんですが、そういう感じのソロ・アルバムをひっそり出すのもいいな、と。そしたら、スタッフから“歌え!”と言われまして(笑)」
――ソロの構想は前々からあったんですか?
「(キッパリと)いや、なかったです。歌詞やメロディを作っている段階で、どこまでbonobosと差別化できるのかって悩んでいたんですけど、意外とうまくいったかな。アレンジは、いつもそうなんですけど、ハマッていくとやり過ぎてしまうことがあって。ただbonobosの場合、現場に持っていくとプレイヤーのスタイルの関係で、できる / できないってことがすぐハッキリするから、徐々にカドが取れていくんですけど、今回はカドを取ってくれる人がいなかったから(笑)。歌詞の面でも、誰も僕を止める人がいなかったし、書きながら“ちょっとヤケクソになってるかも”って思っていたりしてました。でも、ま、いいやって」
――ヤケクソに向かう要因って何かあったんですか?
「まぁ、自然とそうなったんでしょうね。bonobosの枠から外れて、いろいろ整理されてない状況でヤケクソになりながらも、そこでの高揚感が新鮮で気持ち良かった。だから、bonobosをやっているときはリミッターがかかっていたんだなって改めて気付きました」

――シンガー・ソングライター的なアルバムですね。蔡忠浩というシンガー・ソングライターのデビュー作っていうニュアンスが強い。
「あぁ……意識してなかったですけど、そうかもしれない。普段は“歌”とメンバーの“演奏”という二本柱を意識して作業してるから。でも今回は両方がぐちゃっと混ざった感じになったというか」
――じゃあヤケクソなところから出発したけど、結果セルフ・コントロールがうまくいったって自信はあります?
「うん、そうですね。昨年末から曲を作り始めて、弦や管を入れてなるべくアンプラグドな感じにしようとイメージしていて、自宅で打ち込み作業をしながら、奥行きのあるアレンジができたらいいなあと試行錯誤していたんです。そうそう、春ぐらいに
シガー・ロスの
ヨンシーの
ソロ・アルバムを聴いたんですが、弦や管のアレンジがすごく良くて、刺激を受けましたね。あと曲作り自体ではそんな難しいことはやっていない。例えばbonobosのときは、マイナーセブンのフラットファイヴってコードをけっこう使うんですよ。それを使うとムードが出るんですが、少し甘くなるところもあって、取り組み始めのころはそういうのを極力使わないようにしようと制約を設けたりしましたね」
――それは何故に?
「やっぱり半音の微妙なコード進行だと綺麗になるけど、シンプルな力強さが薄れたりすると前々から思っていたから。今回はそういうものじゃないところで、違ったメロディが出てくればいいなと思ってました」
――それはやっぱりソロだから、って意識が働いて?
「うん、ソロだから、ですね。曲でいえば<空豆ひるがえったら>とか僕の中のフォーク的な要素が基本になっているというか、今回はまず“歌”という強いものが念頭にあって、弦や管で奥行きを出すというイメージをどんどん具体化させていったんです」
――それは頑丈なものを作りたいって意識だったんですかね。
「頑丈というか、無骨なものといったほうが合っているかも。小さいスタジオで録っていたことに加えて、弾ける楽器はなるべく自分でチャレンジしようと思っていたから絶対粗くなることはわかっていたし、そういうイメージがありましたから」
――歌詞がいつになく映像的に感じになっているのがまた印象的で。
「ええ。昨年ぐらいから
小沢健二さんの1枚目(『犬は吠えるがキャラバンは進む』)をひさびさに引っ張り出して聴いたりして、<天使たちのシーン>とかすごくいいなと思えて。ここ何年か短歌を勉強したりしながら、内容ではなくどういった表現を行なうかってことを試行錯誤していました。その過程でオザケンさんや
友部正人さんの歌詞に改めて触れて、感銘を受けたりしたんです。つねづね“てにをは”を飛ばしたりせず、言葉としてもしっかりと成り立つ、強度を持った歌詞にすることにこだわっているんですが、今回はその作業を推し進められたんじゃないかなと手ごたえは感じてます」
――で、来年のプランってもう固まってます?
「少しづつ祝っていこうかなと。で、2011年はデビュー10周年なんで、そこでドカンと行こうって考えてます。何やるかはまだアレですけどね」
取材・文/桑原シロー(2010年10月)
![蔡忠浩 - たまもの from ぬばたま [CD] [紙ジャケット仕様] 蔡忠浩 - たまもの from ぬばたま [CD] [紙ジャケット仕様]](/image/jacket/large/411009/4110090129.jpg)


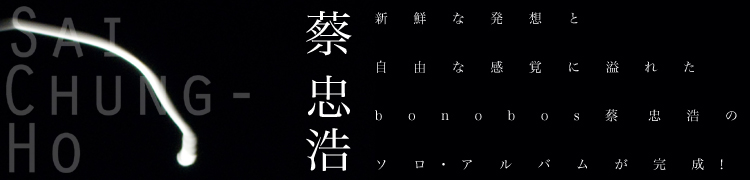
 ――シンガー・ソングライター的なアルバムですね。蔡忠浩というシンガー・ソングライターのデビュー作っていうニュアンスが強い。
――シンガー・ソングライター的なアルバムですね。蔡忠浩というシンガー・ソングライターのデビュー作っていうニュアンスが強い。
 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。