1990年のデビュー以来、特定のムーヴメントに属することなく、マイペースながらも、豊富な音楽的バックボーンと妥協のないクリエイティヴィティでオリジナリティ溢れるサウンドを送り続けてきた
リトル・クリーチャーズ。CDJournal.comでは、そんな彼らのデビュー20周年を祝し、バンドの足跡を4週連続で辿るヒストリー企画『The Story Of Little Creatures』をスタートします。第1回目となる今回は、バンド結成に繋がる
青柳拓次(vo、g)と
栗原務(ds)の出会いから、今となってはあまりにも意外すぎる『イカ天』出演時の裏話、そしてメジャー・デビューに至る経緯など、今まで語られることのなかった初期の貴重なエピソードをたっぷりお届けします。

デビュー・ミニ・アルバム『Little Creatures』発表時(90年)
――今年デビュー20周年を迎えるリトル・クリーチャーズの結成は1987年。それ以前に3人は通っていた同じ中高で出会ったそうですが、もともとは青柳さんと栗原さんのお母様同士がお知り合いだったそうで。
栗原務(ds、perc etc…/以下、栗原) 「そうです。というか、俺と青柳が最初に会ったのは中学の受験会場なんですよ(笑)。そのとき、親も付き添っていたんですけど、その親同士が昔仕事をしたことがあったようで、“ああ、久しぶり!何やってるの!”って盛り上がって」
青柳拓次(vo、g etc…/以下、青柳) 「で、子供たちもお互い音楽好き、特に
ビートルズ好きってところで意気投合して、“試験が終わったら、うちに来なよ”ってことになって、親子ともども(笑)。しかも、その時点で合格かどうか分からなかったので、どちらかが落ちてたら、その出会いが一回きりになってた可能性もあったという(笑)」
栗原 「幸い、2人とも合格。しかも、同じクラスだったということで、リトル・クリーチャーズの今がある(笑)」
――そして、中学時代にリトル・クリーチャーズの前身にあたるバンドが結成される、と。当時、楽器の心得はあったんですか?
栗原 「青柳はおじいちゃんもお母さんもクラシック・ギターの先生っていうギター家族に生まれ育ったので、すでにエレキ・ギターも弾いてたんですけど、俺の場合は、青柳と別の同級生との3人でバンドを始めた時点で一からドラムをスタートした感じですね。そのバンドではビートルズのカヴァーを2曲くらいやって、あとは青柳が作ってきたオリジナルをやってたんですけど、当時の音楽性は60年代の英国バンドの影響が強かったよね?」
青柳 「そうだね。あとはパブ・ロックとかネオアコとか、そういう時代だったよね」
――リトル・クリーチャーズが結成される87年以前の音楽シーンは確かにそういう流れがありましたけど、中学生にしては音楽の趣味が恐ろしくいいですよね。
栗原 「85年くらいって、シンセ・ポップが全盛だったと思うんですけど、そういう音楽には興味がなくて、ギター、ベース、ドラムっていう編成が好きだったというか、いわゆるロックっぽい感じが好みでしたね」
――そして、2人がエスカレーター式に上がった高校に受験で正人さんが入学するわけですが、その出会いというのは?
青柳 「最初に正人が音楽をやってることを認識したのは、高校1年生のときにみんなが仲良くなるために学校主催のキャンプがあって、そのときの出し物だったと思うんですけど、MTRで作ったオケの上で正人がギターをガンガン弾いてたんですよ」
鈴木正人(b、key etc…/以下、鈴木) 「(笑)。え、そんなことしてたっけ?」
青柳 「しかも、プレイが結構ブルージーだったりして(笑)。なんか、一人でやってる!って思ったのは覚えてますね」
鈴木 「ただ、2人とはクラスも違ったし、仲良くしてたわけでもなかったんですけど、ある日、“5組の青柳っていうんだけど……”って電話がかかってきて(笑)。“バンドでコンテストに出ようと思ってて、ベースを探してるんだけど、弾いてみない?”ってことだったんで、“ああ、いいよ、いいよ”って。それでリトル・クリーチャーズが始まったんです」
青柳 「と同時に、一流ベーシストに通ずる長く険しい道もね(笑)」
鈴木 「(笑)。ホントはドラマーになりたかったんですけど、栗原がいるし、じゃあ、ベースをやってみようかなって。それっきりベーシストになってしまったっていう(笑)」
青柳 「まぁ、でも、正人がギター弾いてるのは知ってたし、ギターが弾けるならベースも弾きやすいんじゃないかって思ったんでしょうね。ただ、最初、正人はベースを持ってなかったので、俺のを貸しました」
――青柳さんと栗原さんは、一緒に音楽をやりたいと思う何かを、正人さんから感じられたんですか?
青柳 「正人は、なにせブルージーなギターを弾いてたくらいなので(笑)、ジャズとかブルースみたいなブラック・ミュージックが好きなんだなっていう印象があって、その点では間違いなかったし、それ以前にバンドをやってた人たちは音楽的な人たちじゃなかったというか。一方で正人はピアノもやってたし、クラシック・ピアノが弾けると同時にドラマーになりたいとか、バンドがやれるとか、そういう音楽的な人間ってなかなかいなかったんですよ」
鈴木 「ピアノねー、クラシック・ピアノの練習はホントいやだったなー。だから、練習は全然せずに、勝手に好きな曲を弾いてたんですけど、中学生になると“バンドやらない?”ってことになるじゃないですか。うちの親はヴァイオリンを教えてたり、ちょっとした練習部屋があったんで、そこにバンドの連中が楽器を置いていくんですよ。で、その楽器をちょこちょこいじってるうちになんとなくできるようになっていったんですけど、当時はアメリカン・トップ40とか、LAメタルの曲をカヴァーしてたくらいなのに(笑)、高校入ったら青柳がみんなの前でオリジナルを演奏していて、“うわ、スゴいな。こんなやつらがいるんだ!”って思ったのを覚えてます」
栗原 「基本的には生徒主体というか、何かを決めるときは生徒が集まって決めるのが和光の一番の特色で、文化祭でも自分たちがやりたいからってことで、みんなの前で演奏したり、必然的にバンドもほぼコピーだったりするんですけど、数はめちゃめちゃ多くて」
青柳 「中学と高校が同じ敷地のなかで繋がってたこともあって、それこそ小山田くんとか、そういう先輩たちの演奏を中学1年の頃から観て、センス的なことや音楽的なことを教わったというか」
鈴木 「俺の場合、公立の普通の中学から入ったんですけど、みんな、俺の知らない音楽を聴いてるんですよ。例えば、向こうのスケーター・カルチャーとつながってる
ミスフィッツとか、普通の中高生には意味が分からないような音楽を聴いてて、なんかスゴいところに来ちゃったなって思いましたね」
栗原 「しかも、高校は3人とも違うクラスだったんですけど、それぞれのクラスにいる音楽好きの間で“こういう曲を見つけてきたぜ”ってことで回し聴きしていたし」
青柳 「放課後にラジカセから音楽がかかっているのが学校で当たり前の光景だったので、隣のクラスへ遊びにいくと、知らない音楽がかかってて、そこでもレコードの貸し借りがあったり。そうやって音楽を聴いてるうちにいろんなジャンルの音楽に触れていった」
栗原 「だから、ひとつの音楽だけじゃなく、そうやって同時にいろんな音楽を聴いてきた体験が僕らのルーツにはあるんですよ」

同じく、デビュー・ミニ・アルバム『Little Creatures』発表時(90年)
――そして、80年代後半から90年代前半にかけてのバンド・ブームを後押しすることになるテレビのバンド・オーディション番組『三宅裕司のいかすバンド天国』(略して“イカ天”)に90年4月、リトル・クリーチャーズは18歳で出演。当時は、若さもさることながら、ジャズやソウルといったブラック・ミュージック、UKインディーズのギター・バンドから受けた影響をオリジナリティに昇華した作風が大反響を呼びましたけど、その映像をYouTubeで観ても、経年変化を感じさせない音楽性には驚かされます。
鈴木 「いやいや、やってる本人たちからすれば、とんでもないですよ(笑)。YouTubeの削除依頼をいつ出そうかと思ってるくらいなんですけど(笑)」
栗原 「(笑)。そういうバンド・コンテストって中学時代に青柳たちとよく出ていたんですけど、正人が入ってから出てなかったので、友達から教えられた『イカ天』にデモテープを送ってみたら出演の連絡がきたんです」
鈴木 「ストーンズって、
ミック・ジャガーみたいに青柳の唇が厚いだけじゃないの?とも思うんですけど(笑)」
栗原 「ノブさんも最初は怒られましたけど、そのあと、すごいよくしてくれましたよ(笑)」
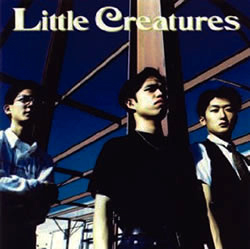
デビュー・ミニ・アルバム『Little Creatures』(90年)
青柳 「テレビに出てたときは毎週のように新曲を作ってはアレンジを仕上げて練習して、翌週の収録に向けて必死だったんですけど、その一方で、俺たち、これからどうなっちゃうんだろうって話したりしてて」
栗原 「で、番組を観てたいろんなレコード会社がわーっと来たんですけど、その頃には青柳も正人も海外留学が決まってたので、“留学はしますよ”ってことと“歌詞は英語でやりますよ”っていう契約条件で、結局、MIDIと契約することになったんです」

ビデオ作品『is there more?』発表時(91年)
――当時の音楽状況を考えると、英語詞でメジャーから出たのは
フリッパーズ・ギターの1stアルバムくらい。英語詞の作品リリースを認めてくれるレコード会社って、ほぼなかったんじゃないですか?
青柳 「そうですね。ほぼゼロだったんじゃないかな。当時は楽器の音色を選ぶように言葉を選んでいて、その言葉のリズム感が大事だったし、僕らは洋楽リスナーだったこともあって、それを日本語に置き換える作業を敢えてやろうとは思わなかったんです。それに当時の日本の音楽シーンにしても、自分たちと関係があるとは思えなかったし……」
栗原 「音楽シーンってことで言えば、その後、2人が留学したこともあって、バンド同士の横の繋がりがなかったし、友達がいなかったこともあって(笑)、気付いたら孤高の存在になっていたという」
鈴木 「何年か前に『別冊宝島』で渋谷系特集の号が出たんですけど、俺らも出てるんだろうなと思ったら、一言も出てこなくて、やっぱり渋谷系じゃなかったんだって再認識すると同時にさびしい気持ちになりましたよ(笑)」
――という半ば冗談でもありつつ、3人がシーンと距離を置いた活動を意図したからこそ、リトル・クリーチャーズは流行に回収されないオリジナルな立ち位置を獲得したのは間違いないですよね。
鈴木 「そういう意識はありました。“誰かと似たことをやってもしょうがないんじゃないの?”ってことは3人とも思っていましたよ。それは性格的に昔から変わらないですね」
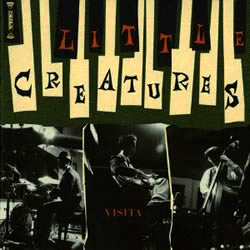
1stフル・アルバム『VISITA』(91年)
――そして、91年に1stフル・アルバム
『VISITA』がリリースされるわけですが、この作品は、アコースティック楽器のシンプルなアレンジを基調に、ソウルやジャズ、ギター・ポップやアイリッシュなど、いろんな要素がミックスされていますね。
青柳 「僕はイギリスに留学していたので、
ハウス・マーティンズみたいなギター・バンドとかアイリッシュ・トラッドみたいな音楽も好きでしたし、当時はアシッド・ジャズが盛り上がり始めた頃だったので、ジャズであったり、モッズ的な音楽であったり……そういうニュアンスは1stアルバム『VISITA』にも表れてますよね」
栗原 「あと当時はボブ・ディランとかすごい好きだったよね。だから、そういうフォーク・ロックの要素もあったし、UKのネオ・アコースティック系が一段落して、グランジ以前の
R.E.M.みたいなアメリカのカレッジ・ロックが面白くなって、そういう音楽を出発点にカントリーだったり、アイリッシュなんかを聴くようになったり」
――ただ、当時のクラブ・カルチャーは今とは比較にならないくらいアンダーグラウンドなものでしたし、初期のリトル・クリーチャーズのミックス感覚にはDJ的な感覚が希薄ですよね。
青柳 「デビュー以前、通ってた高校にはDJをやってる友達が沢山いたんですけど、当時、ラガマフィンとかジャマイカものをかける人がDJって言われていたんです。だから、自分でもそういうことはやってたんですけど、わーっとレコードを買ってDJになるっていう時代はもっとあとですし、音作りはバンドらしいよね」
栗原 「うん。のちの、どの作品にしても、ベーシックはほぼ一発録りでやってますからね。そういうバンド感はリトル・クリーチャーズから失われたことはないと思います」
取材・文/小野田 雄(2010年11月)
<LITTLE CREATURES 20th Anniversary LIVE>●日時:2010年12月17日(金)
●会場:ラフォーレミュージアム六本木
●開場 / 開演 18:00 / 19:00
●料金:¥3,900【サンキュー!!】(前売/自由席/整理番号付)
【チケット取扱】
チケットぴあ 0570-02-9999(P:117-084)
ローソンチケット 0570-08-4003(L:77334)
イープラス
※客席が出演者を360°囲むセンターステージで実施
※お問い合せ:SMASH 03-3444-6751
■リトル・クリーチャーズ オフィシャル・サイト
http://www.tone.jp/artists/littlecreatures/
![リトル・クリーチャーズ - ラヴ・トリオ [CD] リトル・クリーチャーズ - ラヴ・トリオ [CD]](/image/jacket/large/411010/4110101633.jpg)



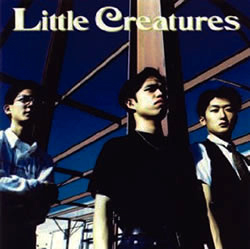

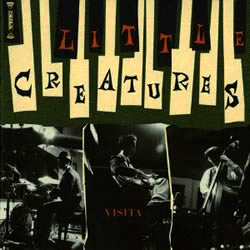


 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。