
アラゲホンジ
“たからかぜ”
アラゲホンジの新作
『たからかぜ』が凄い。秋田県湯沢市出身の齋藤真文(ヴォーカル / ギター)を中心に2007年に結成されたこのバンドは、東北を中心に日本各地の民謡〜民俗芸能を取り入れたお祭りロックで全国を席巻中。特に祝祭感溢れるライヴ・パフォーマンスが話題を集めている彼らだが、新作にはライヴバンドとしての彼らの凄みが凝縮されている。レコーディング / ミキシング・エンジニアを担当しているのは、
LITTLE TEMPOなどで活動してきた日本屈指のエンジニア、
内田直之。90年代に
SOUL FLOWER UNIONが切り開いた地平をさらに突き進みつつ、2000年代の感覚もしっかりと盛り込んだそのサウンドは、海外でも驚きを持って受け止められるのではないだろうか。そんな新作『たからかぜ』や自身の音楽観について、リーダーの齋藤真文に話を聞いた。なお、アラゲホンジには以前本ウェブの連載
『THE NEW GUIDE TO JAPANESE TRADITIONAL MUSIC』でもインタビューをさせていただいたが、そちらの続編として読んでいただければ幸いだ。
――2011年に1stアルバム『アラゲホンジ』を制作した段階ではメンバーが流動的でしたが、それ以降でメンバーが固まりましたよね。メンバー間で共有してる感覚ってなんだと思いますか。 「幼児性というか、プリミティヴな感覚を大事にしてるということですね。みんな素直な感じ、無垢な感覚を大事にしてるんだと思う。論理的な思考よりも無意識の状態を重要視してるというか。(音楽の)作り方そのものは論理的にやってるつもりなんですけど、最終的なジャッジは肉体的な感覚、無意識の部分でやってますね」
――前作以降で楽曲のレパートリーも増えましたよね。特に震災後は被災地の楽曲もカヴァーするようになって。
「震災によって考えたことはたくさんありましたね。根本は変わってないつもりなんですけど、当時は“何かしなきゃいけないんじゃないか”っていう切迫した気持が今以上にあって……僕はどうもリリカルに表現したいという気持ちがあって、自分ができることは何か、ずっと考えてました。それで“被災地の歌を自分なりにやる”というのが一番力を発揮できることなんじゃないかと思ったんです。民謡にはそこに住んでいた人の感情とか記憶まで冷凍保存されてると思うんですよ。そういう歌を歌うことで受け継いでいけること、伝えていけることってあると思うんです。こういう美しいものがあったのか、こういう美しい風景が失われてしまったのか。そういうことを保存していかないといけない。それで、〈斎太郎節〉(宮城県民謡)や〈相馬盆唄〉(福島県民謡)をカヴァーするようになったんですね」
――実際にやってみてどうでした?
「〈斎太郎節〉は自分のものになるまですごく時間がかかりましたね。自分のキャラクターとちょっと違うというか……〈エンヤートット〉とかやるほうじゃないので(笑)。〈斎太郎節〉は宮城の民謡ということになってますけど、太平洋一帯のソウル・ソングだったそうで、やりがいもあるし、モノになるまでやってみようと思って」
――昨年、岩手の陸前高田でライヴをやりましたよね。そのとき「斎太郎節」のリアクションは?
「“これは俺らの歌だ。歌ってくれてありがとう”って言ってくれた方もいて、強い反応をいただきました。そのとき、三陸の方たちにとって大事な歌だということが分かって。なので、礼儀として、自分のものにしたい・するべきだと思ったんです」
――礼儀として?
「自分にしかできない形でやることで、オリジナルに対して筋が通る気がするんです。僕も模倣だけのものを聴いてグッとこないですし……」
――まるで宮城出身みたいな顔をして「エンヤートット」とやることは“礼儀がない”と?
「どうも恥ずかしくなっちゃうんですよね、僕の場合。で、恥ずかしいと思うことをやるのは無礼な気がするんですよ。ましてや民謡は地元の人がやるのが一番いいわけで、僕は自分にしかできないことをやりたい。そこは常に自分のなかのキモとしてありますね」
――そもそも齋藤さんはアラゲホンジ以前からブラジル音楽にのめり込んでいた時期もあったにも関わらず、ポルトガル語を習得してブラジルに移住するような方向にはいかなかったわけですよね。
「ことごとくいかないですね(笑)。音楽のフォーマットが重要なのか、自分の美意識が重要なのか、そこは常に考えていますね」
――そこは美意識なのかもしれないけど、倫理観な気もする。その土地の人が長い時間かけて作り上げてきたものに対し、どう向き合うかという倫理。
「人の道というか……そういう部分と直結してる話かもしれませんね、確かに」
――秋田の歌についてはどうですか? さっきの「斎太郎節」の話で言えば、“これは俺の歌だ”という認識があるんですか。
「実は……あまりないですね、そういう気持ちは。秋田の歌が自分の身体にフィットしていることは分かるんです。でも、“これが自分の歌だ”とは思えないですし、岩手の歌のほうがしっくりくることもあって。僕の場合、子供の頃から民謡を歌っていたわけじゃないんで、どの歌に対してもフラットなんです。ただ、秋田の歌を聴いてると親や兄弟と話してるような感覚にはなります(笑)」
――言葉の響きも影響してる?
「いや、民謡の歌詞ってそんなに訛ってるものって多くないじゃないですか。歌の部分は平板化されているものが多いので、そんなに方言が入ってない。だから、どうも歌詞とは違う部分に親しみを感じるみたいなんです。秋田の歌は自分の性格と似たところがある気がするんですよ。めんどくさい感じがあって……(笑)。ポイントが見えづらいというか、バンド・アレンジしにくいような歌が多い。僕の性格そのままなんです(笑)」
――なるほど(笑)。あと、アラゲホンジは東北や北陸の歌はカヴァーしてますけど、西のものはやってないですよね。
「なぜか取り上げようという気にならないんですよね。今のところ自分のなかでフィットしないんです」
――確かに齋藤さんが河内音頭を歌ってる姿ってイメージできないかも(笑)。
「僕も想像できなくて(笑)。河内音頭って平野で歌われてる感じがするんですよ。東北の歌のなかには山が描かれてるイメージというか、独特の暗さと内に向かっていくエネルギーがある。そこがおもしろいんです。あと、東北は“(戊辰戦争などで)負けた人たち”の歴史があるので、その感覚が一種の暗さとして残ってる気がする」
――今回のアルバムに関してなんですが、最初からイメージしていたものはあったんですか。
「とにかくライヴの雰囲気をパッケージングするということですね。それもあって内田直之さんにお願いして。前回は各パートをバラバラで録ったんですけど、あのやり方ではライヴのグルーヴは出せないだろうと思っていたので、次はライヴの勢いをそのまま出そうと決めていました。今回は半分ぐらいの曲は歌も含めて一発で録って。〈斎太郎節〉と〈相馬盆唄〉にいたってはワンテイク目を入れることにしたんです」
――オリジナル曲には民謡ぽくないメロディのものもたくさんありますよね。そこをどうやってどうアラゲホンジのカラーに染めていくんですか。
「曲作りについてはまず7割ぐらいの全体像があって、最初に歌詞を完成させちゃうんです。昔はメロディを最初に作り込んでいて、今みたいなイメージで曲を作っていたにも関わらず、人からは“
山下達郎みたいな曲だね”って言われることもあって。でも、そこに“七・七・七・五”っていう都々逸(註)の形で歌詞を現代語で乗せていって、それをベースに崩していったらうまくハマったんです」
註:都々逸 / 都々逸坊扇歌を始祖とする俗曲・寄席芸で、“七・七・七・五”という形式で歌われる。なお、甚句と呼ばれる民謡の形式も同じ“七・七・七・五”。
――なるほど。
「だから、アラゲホンジの最初のころに作った曲は全部都々逸の形式なんです。最近は違った形式の曲も増えてきましたけど。やっぱり言葉が一番大事だと思うんですね。言葉の意味というより、言葉の音が」
――「トーキョー・ネイティブ・タイム」には秩父屋台囃子(註)のビートが入ってますよね。
註:秩父屋台囃子/ 埼玉県秩父市で行われる秩父夜祭りにおいて、屋台(山車)のなかで演奏される囃子。
「あの曲は
ジョー・クラウゼルの〈Gbedu1〉(註)っていうアフロビートの曲が元ネタだったんです。そこに秩父屋台囃子ぽいリズムを入れたらおもしろいんじゃないかっていうイメージがあって。でも、ライヴでやるようになってから少しずつメロディが変わってきて。ライヴで作り込んだ曲ですね」
註:Gbedu1 / ジョー・クラウゼルがグベドゥ・レズレクション名義で99年に発表した12インチ収録曲。
――「さみどりの丘」は西馬音内盆踊(註)の囃子がモチーフになってるとか。
註:西馬音内 / 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内(にしもない)で行われている盆踊りで、“がんけ”“音頭”という2種類の囃子が演奏される。
「
矢野顕子の〈ふなまち唄〉っていう曲をライヴでやってたんですけど、最近になって、あの曲は青森のねぶた囃子に歌詞を付けたものなんだって気づいたんですよ。その衝撃から、自分も〈ふなまち唄〉に対するオマージュとして曲を作りたくなって。それで西馬音内盆踊の“がんけ”で使われる笛のメロディに歌詞を付けるというコンセプトが出てきたんです。あと、僕の地元である湯沢市が合併する前の市民歌が昔から大好きで、その歌の出だしが“早緑(さみどり)の丘の彼方に”というフレーズだったんですね。歌詞に関してはその市民歌をモチーフにしてます」
――『たからかぜ』というアルバム・タイトルにはどういった思いが込められているんですか。
「“たからかぜ”というのは秋田の〈生保内節〉のなかに出てくる言葉なんですけど、“この風が吹いてきたら豊作になる”っていうおめでたい言葉なんですね。〈たからかぜ〉っていう曲のなかでも“痛み悲しみ哀れみをどこか遠くへ吹き飛ばせ”と歌ってて、そうやって痛みが流れてしまえばいいのに……という思いと、聴いた方に吉兆が訪れるような音楽でありたいという思いを込めました」
――岩手民謡の「外山節」のカヴァーでは馬喰町バンドなど近年競演を重ねているバンドのメンバーが参加していますよね。馬喰町バンドしかりTURTLE ISLAND、滞空時間、コロリダス、島音流など、ここ最近アラゲホンジが競演しているバンドには共有しているものがある気がするんです。それまで一匹狼みたいに活動していた人たちが繋がり始めているというか、ひとつのシーンのようなものが生まれ始めたいるんじゃないかと。 「それは大きいですよね。“自分が何者なのか”ということをみんな正面から見てるんだと思う。どこから来て、どこに行くのか。そこを突き詰めることが音楽表現と重なっているんだと思います。僕も彼らから刺激を受けてるし、そのなかで自分たちの立ち位置がはっきりしてきた気がする。原発のこともそうですけど、いろいろ意識的になってきてるんでしょうね。どう生きていくべきか、そういう美意識に対しては僕らも頑固にやっていこうと思ってます」

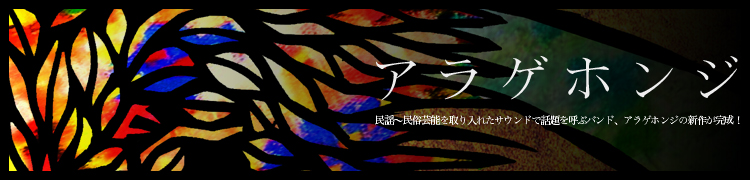


 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。