これは日本の新世代ソウル・ミュージックの萌芽である。フロントマン、山本剛義のもったりとメロディに絡み付くようなヴォーカルは天性の素質である。そして、多くの人に突き刺さる音楽を作るために、自らの変化をも厭わない姿勢は実に潔い。中高が一緒だったというベースの阪口晋作と山本が結成したミラーマン、改め
ボールズ(Balls)は、
ceroや
森は生きているとも相通ずる、現代的な感覚でルーツ・ミュージックをアップデートした若き才能の塊といって過言ではない。その核にはなにがあるのか、インタビューで迫った。
――山本さんは中高時代を大阪で、大学時代を京都で過ごしてきたんですよね?
山本剛義(以下、同) 「そうですね。中高一貫の学校だったんですけど、ベースの阪口とはずっと一緒に通っていました」
――ライヴのMCでおっしゃってましたけど、男子校だったそうで。かなり音楽を掘っていた青春時代だったんじゃないかって感じがしましたけど。
「めちゃめちゃ聴いていましたね」
――そのときは、どのようにして音楽を掘っていたんですか?
「毎週水曜日とか、新譜が出るときは、学校の帰りに通学路にあるタワレコに行くんです。あと、土日はHMVとかのサイトを見て、“この音楽が好きな人はこの音楽がオススメです”っていう作品を大量にメモしてました。名前だけチェックしておいて、気になったのを休みの日に片っ端から中古CD屋で買うんです」
――山本さんの青春時代って、ネットが全盛ですよね?
「そうなんですよ。だけど、僕YouTubeを知らなくて、使ったことがなかったんです。だから、どんな音楽かっていうのは2ちゃんねるで調べていました」
――(笑)。そのなかで、ひっかかったのはどういう音楽だったんですか。
「サイケみたいなのが多かったですね。
ハッピー・マンデーズ、
ソフト・マシーンみたいな音楽ばかり聴いていました。日本の音楽も好きで、山下達郎さんとか
大瀧詠一さんとかも聴いてましたし、
ROVOとか、ちょっとトランス感があるものもよく聴いていました。セクシーなものも好きで、
プリンスとハッピーマンデーズだけしか聴いてない時期もありました。めちゃくちゃ気持ちいいんです、聴いていて」
――そんな山本さんがバンドをはじめたのは、高校を卒業してからのことで、しかもノイズをやっていたそうですね(笑)。
「
山本精一さんが好きやったんですよ。ただ、山本さんとか
灰野敬二さんって、ちゃんと独自のロジックがあって気持ちよく聴かせていると思うんですけど、僕らは単純にライヴがしたかっただけで。しかも、できることは打ち込みとギターくらいだから。いま聴いてもひどいんですけど、30分ずっとノイズを出してました」
――それこそ大学で音楽サークルとかに入ることは考えなかったんですか。
「考えはしたんですけど、閉塞感がある感じがしてちょっと苦手だなって思ったんですよ。限られた価値観でお互いを褒め合っているみたいな。それだったら、友達2人でやったほうがいいなと思って」
――大学に入ってからは、どういう形で音楽を続けていったんですか。
「とにかくライヴをしたくて、山本精一さんのいる難波ベアーズに、どんな場所かも知らずに音源を送ったんです。30分ノイズがビーって鳴っている音源だったんですけど、ベアーズの黒瀬さんから電話がかかってきて、“ええやん、出えや”“なんかすごい伝わってくるもんあったよ”って言われて“絶対思ってないやろ!! ”と思って」
――(笑)。
「ライヴに出るのに慣れてないから“緊張する”って言ったら、“お前ら、寝るときとか緊張しないやろ?パジャマでライヴしたら?”って言われて。この人信用できるなと思って。それで他のライヴハウスに音源を送っていったら、いろんな場所に出られるようになっていったんです。その間、ベアーズにも出ていて、黒瀬さんに“バンドでやってみたら?”って言われたのがきっかけで、ドラムとギターを入れてバンドを組んでみたんです」
――なんだかんだ言っても恩人なんですね(笑)。メンバーはどこからみつけてきたんですか。
「最初は、同じ高校で唯一ドラムを叩けるヤツがドラムを叩いていたんです。でも、なんでも倍で刻んでくるし2バスなんで、ノイズじゃない!! と思って。あと、歌ってみたい気持ちがでてきて、
ソニック・ユースみたいな曲を作るようになっていって。それでmixiで募集していくうちに、いまのドラムの谷口がみつかったんです。
フィッシュマンズとか
七尾旅人が好きだっていうので、入れてみようって」
――そこで、ドラムがみつかり、歌ものに寄っていくわけですね。
「そうですね。オルタナティヴっぽい曲を作っていたときは全曲暗い曲だったんで、明るい曲が1曲あったら他の曲も映えるんじゃないか?って阪口が言ったんです。それがきっかけで、前のアルバムに入っている〈ばんねん〉って曲を作ったり、曲が増えてきて、この路線でいったほうが楽しくやれるんじゃないかと思うようになりました。そのとき初めてポップ・ミュージックを作る楽しさみたいなのを感じたんです」
「確かに『ニューシネマ』はそんな感じでした。ただ、今って90年代USインディっぽい音楽をやっている日本のバンドが多くて。そういう状況を見たら、やりたくなくなってきて。今作はよりポップスに傾倒した作品になったと思っています」
――作るときから前作とは違うものを意識していたわけですね。
「僕は天邪鬼なので、『ニューシネマ』を好きだって寄ってくる周りのバンドとあまり仲良くしたくなかったんです。サークルの話とも通じるんですけど、閉塞感を感じるというか。仲がいいから褒めてくる、オレも気まずいから褒める、みたいなところに違和感を感じていたんです。アンチじゃないんですけど、彼らとは違うバンドになりたいって、不特定多数のバンドを見て思っていました」
――ボールズの最大の特徴というか武器は、山本さんの声だと思うんですね。メロディにねっとり絡み付くようなヴォーカルは天性の才能といってもいいと思います。自分の声に対してはどう思ってますか?
「実は、ずっと意識してなかったんですけど、どっかで気づいたんですよね。声で得しているってことを。音程を少し外してもバレなかったりとか(笑)、ただコードをなぞっているだけでも、すごくいいメロディって言われたり。それがわかってからは、バンドをやるのがだいぶ楽になりましたね」
――楽になったっていうのは気持ち的な部分ですか。
「そうですね。前は、ほんまはこのメロディがいいけど、ありがちやし、もっと考えたほうがいいんじゃないかとか、すっと出てきたものに対して抵抗があったというか。ぱっと出てくるものも自分のなかでより受け入れやすくなったというか、自分のなかでいいなと思える範囲が広くなりました」
――本作に収録されている曲は『ニューシネマ』のあとに作った曲が多いですか?
「実は〈メルトサマー〉は、19歳のときユニバーサルに目をかけてもらって、東京に何回かライヴに行っていたときに、ちょっと売れる曲を作ろうってことで作ったんです。そのとき以来やってなかったんですけど、久しぶりに聴いたらいい曲だなと思って、夏に出すから入れてみようって。だから、これをユニバーサルから出せるっていうのは、個人的なことなんですけどグッときています」
――それはグッときますね。京都とか関西って今、若くていいバンドが続々と出てきているじゃないですか。同世代の関西のバンドに対してはどう感じていますか。
「うーん。音楽的に素晴らしい、好きなタイプのバンドが多いんですけど、ぶっちゃけていうと、みんな集客で苦戦しているんです。僕は人が入らないバンドにはなりたくなくて。そこが少し気になりますね」
――天邪鬼でありつつ、人がいるところでやりたいっていうのがおもしろいですね。
「同業者的なところに対して、負けず嫌いなんですかね。僕も前までは人がいなくてもカッコよければいいと思っていたんですけど、負け惜しみを言っているように感じてきて。正直言うと、わからないヤツが悪いって思っていたこともあるんですけど、すごくみじめな気持ちになって、情けなかったんです。そのとき、どうやったら観に来てくれる人が増えるんやろうとか、阪口と話して試行錯誤して、ようやく動員が増えてきたり、いろんなイベントに呼んでもらえるようになってきたんです。だから集客に対してこだわりがないバンドに対しては、どんだけ音楽がよくても、ちょっと疑問に感じるというか、手放しでめちゃくちゃいいとは思えないです」
――明確に音楽で飯を食っていくって意思があるんですね。
「そうですね。僕はそうしたいんです」
――山本さんがすごいなと思うアーティストはどういう人ですか。
「
UVERworldとか、自分の感覚的にヤバいと思います。あと
ONE OK ROCKとかも、歌を聴いていてヤバいって思うんです。僕は
玉置浩二さんがめちゃくちゃ好きなんですけど、
安全地帯とUVERworldってすごく似てると思っていて。言葉で説明できないんですけど、圧倒的で、全員のキャラ強すぎみたいなところは本当にすごいなって。あと、
aikoさんの新譜聴きましたか?」
――聴きましたよ。
「あれ、すごくなかったですか?声もいいし、歌もいいし、歌唱力も高いんですけど、それ以上のものがライヴでも音源でも表現されていて。売れている人って、聴いたら納得させられるんですよね。僕らみたいなインディっぽいシーンで、それをやったバンドっていないんで、それをやりたいんですよね。そこにトライしたい」
――ボールズの楽曲からはその意思が伝わってきます。大きくなることによって、何を成し遂げたいんでしょう。
「自分が広く受けいれられたら、少なくとも今よりは多くのバンドが受け入れられる雰囲気が広まるんじゃないかと思っていて。僕らはずっと大阪で活動してきて、先輩も後輩もカッコいいバンドを知っているので、そういうバンドがみつけられずにいるのが悔しいんです。他のバンドもフックアップできるくらいの影響力を持てるようになりたいです」
――ちなみに今、目をかけているバンドはいますか?
「京都のバンドなんですけど、本日休演っていうバンド知ってます? 20歳そこそこなんですけど、かなりヤバいです。まだ音源しか知らないんですけど、京都やったら次に来ると思います。もし僕らが自分たちだけででっかいところまでSOLD OUTさせられたら、彼らを呼べると思うんです。それで、そこに来てくれた人たちがそのバンドを好きになってくれたらって。理想論かもしれないんですけど、一番美しい形、自然な形ってそうやと思うんです。例えば、僕らはゴッチさん(後藤正文 /
ASIAN KUNG-FU GENERATION)にチャンスをもらったりして、大なり小なり先輩にやってきてもらったことなんで、自分がいいと思う後輩のバンドにしっかり返していきたい気持ちが最近強いんです。同世代に対しては負けず嫌いな気持ちがあって、全員蹴落としたいですけどね(笑)。同世代の成功は心から喜べないんです。本当は喜びたいんですけど、悔しいんですよね。だから、大きくなるための一歩が本作にかかっています」
――かなりの自信作なわけですね。
「そうですね。ただ、マスタリングが終わって1週間くらいすると、次の作品を出したくなくなってくるんですよ」
――どういうことですか?
「どうしてもリリースまで時間があくじゃないですか。その間に曲ができて、次のモードにいくんです。これを作ったときは自信満々でしたけど、僕らはこれを消化して次に来ているので、本当はすごく不安なんですよ。でも自信満々でもある」
――(笑)。
「僕は、サブカルあがりインディあがりのバンドが、日本の音楽シーンを動かしていくみたいなところに、すごくロマンを感じるんですよ。そういうバンドがでてきた後には、いいバンドがたくさん出てくるので、僕らがその世代の最初でありたいです。だからけっこう焦ってますね。でも、難解なことをやるよりも、多くの人たちの心をつかむ曲を書けるほうに魅力を感じています。もちろん、僕らはもっと上手くならないといけないんですけどね(笑)」

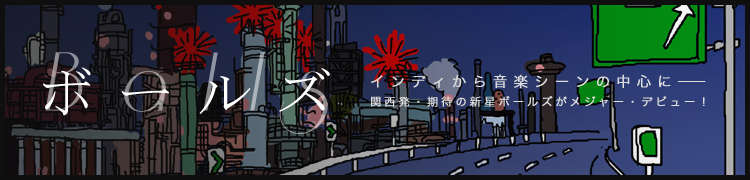


 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。