2014年11月30日で没後60年を迎える
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(Wilhelm Furtwangler)。そのアニヴァーサリー・イヤーに際し、フルトヴェングラー指揮による音源4タイトルが日本盤先行にて一挙リリースされます。気になる発売日は、
『ヒトラーの第九』(KICC-1158 2,000円 + 税)と
『ウィーン芸術週間の第九』(KICC-1159〜60 3,400円 + 税)、
『モーツァルト:歌劇《ドン・ジョヴァンニ》全曲』(KICC-1161〜3 5,400円 + 税)の3タイトルが11月26日(水)、
『ルツェルンの第九』(KIGC-17 3,500円 + 税)が12月3日(水)です。
『ヒトラーの第九』は、ついに陽の目をみる国内初出音源(VENEZIA原盤)。1942年4月、戦況の悪化のなか、国民統合の象徴として総統誕生日祝賀演奏会でフルトヴェングラーに指揮させることを画策した宣伝大臣ゲッベルスの圧力の前に、それまでほかに演奏スケジュールを入れ要請を断っていたフルトヴェングラーもついに屈服。ナチス党旗を前に指揮する羽目に陥りました。この日の演奏は、ドイツ全土はもとより世界に向けて放送されたため、エアチェック録音が遺ることに。演奏の終楽章一部はナチスの宣伝用ニュース映画に撮られました(YouTube等でみることができます)。フルトヴェングラーとしては不本意ながらの指揮であるはずなのに、戦時下、ナチス党幹部を背にしての極限状態のなかで行われた指揮は、“メロディアの第九”をも凌ぐ激しさ!あたかもヒトラーに対する怒りが爆発しているかのような、まさに凄絶を極めたいわくつきの演奏です。
『ウィーン芸術週間の第九』は、ウィーン・フィルをふった巨匠の第九として、筆頭に挙げられる名演を収めたもの。音源としては目新しいものではないものの、日本フルトヴェングラー協会の原盤を使用して音質の大幅刷新が行われており、市販盤としては過去最高の音質と言える仕上がりです。1969年12月に設立された日本フルトヴェングラー協会は、日本でもっとも歴史のあるフルトヴェングラー研究団体。初代会長は近衛秀磨が務めました。会員を対象に全世界ルートから集めた秘蔵音源の復刻頒布をしてきましたが、プレス先が消滅してしまい、本ディスクは廃盤のままヤフオク等でプレミア値段がつくほどの貴重盤となっていたもの。演奏前、楽章間のインターバルもそのまま収録され、臨場感もたっぷりにウィーン・フィルの弦が生々しく響きます。第3楽章「アダージョ」は、あのバイロイト盤をもしのぐ感動を与えてくれることでしょう。
『モーツァルト:歌劇《ドン・ジョヴァンニ》全曲』は、完全収録・世界初出の協会盤が最新リマスターで復活するもの。フルトヴェングラーによる『ドン・ジョヴァンニ』は、1950年、53年、54年と3種のザルツブルク音楽祭ライヴが存在しますが、音の良さ、歌手陣の出来を含め、最晩年のこのライヴは圧倒的です。いままでの正規EMI盤はフィナーレの6重唱の欠落を53年録音で補い修復していましたが、2005年に日本フルトヴェングラー協会がこのライヴ完全収録音源(オープンリール・テープ)を探し出し、完全収録・世界初出CDとして会員に限定頒布。現在では入手困難のため、プレミアつきの人気となっています。冒頭のチャイムからはじまり、音楽祭開演のファンファーレ、曲紹介のアナウンス、そして拍手のなか巨匠の登壇、と当時欧州各国に生中継された歴史的放送記録は、いまもなお生々しい臨場感をもっています。場内の雰囲気、巨匠の息づかいや歌手陣の熱演ぶりまで感じとられ、「シャンパンの歌」をうたったシエピへの2分間に及ぶ拍手、「お清めの六重唱」のあとの大団円の盛り上がりなど、聴いていて思わず60年前にタイム・スリップしてしまう仕上がりです。
『ルツェルンの第九』は、フルトヴェングラーの最後かつもっとも音の良い第九として有名なもの。これまで仏ターラ盤がフルトヴェングラー夫人の許諾を得た正規盤としてロングセラーを続けてきましたが、今回は放送局のスタジオに機材をもちこみ、門外不出で保管されていたオリジナルテープから、ダイレクトにデジタルマスタリングが施されました。ピッチの変動やノイズ成分も厳しくチェックされた入念なマスタリングにより、最高音質の第九がついに完成。楽章間のインターバルもそのまま収録され、聴いていてその場に居合わせているかのような臨場感に満ちています。オリジナル・ブックレットには、ルツェルン音楽祭アーカイヴから集めた巨匠の“リハーサルでの指揮”“本番での指揮”など5点の写真が掲載。日本語解説には当時の資料(この演奏を聴いた日本人・大村多喜子氏の手記)も掲載され、ファン垂涎・充実の内容です。
今回リリースされる4つの音源は、どれも大変貴重かつ非常にクオリティの高いものばかり。フルトヴェングラーのファンの方のみならず、いままであまりフルトヴェングラーの録音をじっくり聴いたことのない方にもオススメです!没後60年という記念年、あらためてフルトヴェングラーの音楽に触れてみてはいかがでしょうか。
![ルツェルンの第九(SACDハイブリッド盤) フルトヴェングラー - PO [SA-CDハイブリッドCD] [廃盤] ルツェルンの第九(SACDハイブリッド盤) フルトヴェングラー - PO [SA-CDハイブリッドCD] [廃盤]](/image/jacket/large/411409/4114092563.jpg)
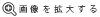
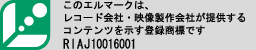
 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。