注目タイトル Pick Up
朴葵姫がギターの弦を弾くときの微妙なニュアンスを聴く文/長谷川教通
いまクラシック・ギター界でもっとも注目度の高い若手といえば、まず朴葵姫(パク・キュヒ)を挙げるべきだろう。1985年韓国生まれ。3歳のとき横浜でギターを始め、東京音大を経てウィーン国立音楽大に学ぶ。在学中から数多くの国際ギター・コンクールを総なめにした強者だ。現在ハイレゾの配信では96kHz/24bit音源で4枚のアルバムが入手できる。スペイン音楽がいいなら『スペインの旅』。有名な「アルハンブラの思い出」で、彼女のトレモロを聴いたらビックリするだろう。これほど滑らかに弾けるなんて……。タレガの「前奏曲」のしっとりとした情感に浸っていたら、アルベニスの「アストゥリアス(伝説曲)」で強靱な音色がググッと迫ってくる。でも、あくまでしなやかに歌う。そこが朴葵姫の魅力。演奏ノイズが少ないのも驚きだ。『最後のトレモロ』では有名なバリオスの「大聖堂」やピアソラの「天使のミロンガ」など中南米への旅。『Saudade(サウダーヂ)−ブラジルギター作品集−』はヴィラ=ロボスをはじめ多彩なブラジル音楽だ。
そして最新の『Harmonia−ハルモニア−』では、現代のギタリストたちが書いた曲ばかりを弾いている。中でも渡辺香津美の「ペガサス」と押尾コータローの「ハルモニア」は彼女のために書き下ろした作品。新たな地平を追い求めたアルバムとなっている。テクニック、表現とも超一級。ぜひハイレゾで聴いてほしい。CDに比べるとS/Nの良さが効いてきて、空気感はもちろん弦を弾くときの微妙なニュアンスが聴きとれ、人の指が奏でているんだ! とゾクッとされられる。
1971年、クラウディオ・アバドはまだ30代。スカラ座の指揮者として活躍していた頃、ロンドン響を振った名演だ。とにかく歌手陣が凄い。ヘルマン・プライの明るくてコミカルなフィガロがいい。テレサ・ベルガンサのロジーナの多彩な表情もすばらしい。アバドはロッシーニ=イタリア・オペラという常套的なイメージにこだわってはいない。むしろ、このオペラが持っている開放的でエネルギッシュな音楽の魅力を引き出そうと懸命に努力する。歌手もオケもそれぞれが自発的に個性をぶつけ合ったときに生まれる化学反応を、指揮者として引き出すこと。その意味では主役の2人はそのままでスカラ座と収録した映像作品よりも、彼の音楽作法がハッキリと見える。指揮者が絶対の発言力を持ってオケを引っ張るのではなく、純粋に音楽的なアプローチを重視しながら奏者たちのさまざまな意見を聞く。そういうプロセスを経て音楽を作る……まさに指揮者とオケの新しい関係を作ろうとしたマエストロだった。彼は、いかにもイタリア的という過剰な感情表現や凄惨なストーリーに感情移入することを憚ったのではないだろうか。プッチーニやヴェリズモ・オペラを避けてきたのも分かる気がする。録音は1970年代初頭のアナログ録音としては最上の音質。アバドは、同年ロンドン響と「チェレネントラ」を録音しており、さらには最高の評価を受けたウィーン・フィルとの「アルジェのイタリア女」など、ロッシーニの魅力に光を当て再興させた立役者の一人としての功績は大きい。

80歳を超え体調も万全とは言えない小澤征爾だが、音楽への情熱はいささかも衰えていない。2017年、水戸芸術館でマルタ・アルゲリッチと共演したライヴ。音楽ファンにとっては夢のようなコンサートだったに違いない。ベートーヴェンのピアノ協奏曲第1番。巨匠2人による親密な語らいと腕利き揃いの室内オケによる活気あるアンサンブルが聴きものだ。アルゲリッチがステージに登場しただけで会場の雰囲気がいっきに変わり、弾き出した途端に彼女の音色に引き込まれてしまう。ハンマーのフェルトをいくぶんソフトに調整しているのだろうか、低音から高音域まで金属的な音はまったくしない。一粒一粒がまろやかに磨き上げられ、それらがみごとなまでに美しく連なっていく。強音でも響きが粗くなることなく、あくまで自然で澄み切っている。小澤の指揮するオケも溌剌として、とても新鮮な音楽が奏でられている。
当日はサイトウ・キネン・オーケストラの録音も担当するデッカの技術者が来日して録音したようだが、腰の据わったバランスと厚みのある響き、高音域を少しプッシュして艶やかさや華麗さを演出するなど、これを伝統のデッカ・サウンドというのだろう。
現代音楽で注目される女流ヴァイオリニスト、リーラ・ジョセフォヴィッツのために作曲されたジョン・アダムズの意欲作。ジョセフォヴィッツといえば、BBC2017のミルガ・グラジニーテ=ティーラ指揮するバーミンガム市響との共演で弾いたストラヴィンスキーのヴァイオリン協奏曲の映像にぶっ飛んだ人も多いのではないだろうか。自由奔放な弾きっぷりと笑いあり鬼気迫る表情あり……身体全体から音楽を奔出する姿にもう釘付けだ。
「シェエラザード2」はジョン・アダムズがパリのアラブ・インターナショナル・インスティチュートで展示されていたシェエラザードの物語に啓発されて作曲した作品。抑圧された女性の困難と、それを克服して自由を獲得する姿は現代にも通じるテーマだとして、ヴァイオリンに主人公を投影させソリスト的に扱う。2015年に初演。世界各地で演奏され、日本では2017年に初演時の指揮者アラン・ギルバートが都響を振って初演している。ソロはもちろんジョセフォヴィッツだ。このアルバムは作曲者とも親しいデイヴィッド・ロバートソンとセントルイス響による2016年の録音。
ジョン・アダムズはミニマル・ミュージックというイメージがあるが、ここではミニマルをはるかに超えた壮大なスケールと後期ロマン的な雰囲気も漂わせている。曲は4つの部分から構成されており、第2部の愛のシーンでは、どこかベルクの影響を感じさせる。第4部。宗教裁判にかけられ、そこから逃亡し最終的に聖域へと飛翔する……その音楽を私たちはどう聴くべきなのだろうか。ジョセフォヴィッツの壮絶なヴァイオリンと、その傍らで奏でられるツィンバロンの音色に耳を傾けたい。
2009年にブザンソン国際指揮者コンクールで優勝。それから10年も経たないのに山田和樹の飛躍が目覚ましい。ちょうど半世紀前の1959年に小澤征爾が優勝して以来、何人もの日本人優勝者が出ているが、2016/17年のシーズンからモンテカルロ・フィルの芸術監督兼音楽監督を務め、2018/19年のシーズンからはバーミンガム市響の首席客演指揮者に就任する山田和樹には、ぜひとも小澤の壁を乗り越えてほしいと思う。
このアルバムはスイス・ロマンド管を振った2015年ジュネーヴでの録音だ。嬉しいのはドビュッシーに加えてルーセルとプーランクが聴けること。2017年まで首席客演指揮者を務めていたオケとの呼吸もピッタリで、さすがフランス語圏で評価の高い山田ならではの素晴らしいリズムの感覚だ。「牝鹿」の冒頭、軽快だけれどもあざとさとは無縁の上質さ。ウィットに富んだ感覚の鋭敏さ。それが彼の武器であり、フランス近代の作品には不可欠の感覚なのだ。
録音はホールトーンを取り込んだ雰囲気のあるもので、位相特性の優れたスピーカーで再生すると、弦セクションや管楽器セクションが重なり合うように響いているのが聴こえてくる。ペンタトーンらしい優秀録音だ。
板起こしの384kHz/24bitで聴く“ヒゲダンス”文/國枝志郎
おお、これは懐かしのザ・ドリフターズ、しかも“ヒゲダンス”(まあオリジナルはテディ・ペンダーグラスなんですが)じゃねーか! クラスの男子全員が振りコピしてたよなあ……なんて考えながら驚き喜んだ熟年ハイレゾ・マニアが100万人はいるんじゃないだろうか(笑)。もちろん筆者もそのひとりなわけだが。で、さっそくダウンロード……と思ったらあれ? なんか2種類あるんですけど……。
今回このザ・ドリフターズだけでなく、石川ひとみ、アグネス・チャン、植木等の4組のアーティストのシングル・ナンバーが配信されているのだが、これは渡辺プロダクショングループの渡辺音楽出版とe-onkyo musicのコラボレーションによる往年の名曲のアナログ盤ハイレゾ化企画“アナログ・レコード再生”プロジェクトの第一弾となるものという。しかも、単なる復刻ではない。“懐かしのドーナッツ盤レコードを、超ハイエンドなターンテーブルとカートリッジで再生し、高品位にハイレゾ化。アナログの魅力を最新のデジタル技術で余すところなく引き出した、新しいハイレゾの楽しみ方をご提案いたします”というもの。簡単に言えば“板起こし”なんだけど、よく海賊盤なんかで使われる“板起こし”につきまとうネガティヴなイメージじゃないわけ。超ハイエンドなオーディオ機器を使用するのは当然のこととして、“今回のアナログ盤ハイレゾ化企画では、数多くのオーディオ系雑誌を出版する株式会社音元出版の協力により、普段ではなかなか試聴することのできないハイエンドなオーディオ機器を使用。「プランA」と「プランB」の2系統を用意し、カートリッジの違いによるサウンドの変化の聴き比べがお楽しみいただけます”ということなのだ。ワクワクするでしょうこれ。ターンテーブルはTechDASのAir Force III(税別180万円)を使用するのは共通で、カートリッジはひとつめがMCカートリッジ(My Sonic / Signature Gold、税別65万円)、ふたつめが光電管カートリッジ(DS AUDIO / DS-W2、税別40万円)を使った再生音を記録したもの。ふたつのヴァージョンを聴き比べれば違いは歴然。MCカートリッジと超珍しい光電管カートリッジ(その違いはググってね)の音質の違いは、どちらがいいとか悪いとかではない。この違いを楽しむのが“趣味”ってやつだ。なんというぜいたく! ちなみに元データは384kHz/24bitで収録されており、一般的な192kHz/24bitのほかにこのオリジナルデータも配信されているので、より趣味が高じた方は両方試してみることをお勧めします。いやしかしとんでもないものを出しやがったなあ(笑)。

ジャズ・ヴァイオリニストとして右に出るもののない才能を持ったアーティスト、寺井尚子は今年2018年、デビュー(1988年)30周年、そしてCDデビュー(1998年、ビデオアーツ・ミュージックからの『Thinking of You』)20周年を迎えるという。活動年数を知るだけでも感慨深いものがあるが、この5月に出た2作が26枚目、27枚目のアルバム(ベスト・アルバム含む)になるというのだから、そのとどまるところを知らないエネルギーには首を垂れるしかない。しかも、である。寺井尚子はハイレゾ・マニアにとっても非常にありがたい存在なのはよくご存じと思う。現在e-onkyoで配信されている寺井のアルバムは新作2枚を含めて7枚。もちろんアルバムの枚数を考えればけっして多い数ではないだろう。だがしかし、2014年の『ヴェリー・クール』こそ96kHz/24bitのPCMのみの配信なのだが、2015年の『ホット・ジャズ』以降は、かならずDSDファイルの配信も行なってくれているのだから頼もしい。2017年の『Piazzollamor』からは、当時まだ珍しかったはずのDSD11.2という超高音質ファイルでの配信を実現してくれていたのは、当時まだそのスペックでの配信がそれほど多くなかったことを考えると、感謝してもしきれないほどである。そして今回の2作のうち、1枚は彼女のキャリアを俯瞰するような選曲(2002年のsomethin’ elseレーベル移籍後のアルバムからの16曲をセレクトした、メジャー・レーベルとしては初のベストである)で、すべて最新のリマスターが施されてあらためてフレッシュな魅力をまとった一枚となっており、寺井尚子の世界への入門編としても最適な作品となっている。しかしなんといっても昨2017年11月に出たばかりの『The Standard』からわずか半年でのお目見えとなったスタンダード集第2作『The Standard II』が抜群に素晴らしい。2002年以来、寺井尚子グループのピアニストとして参加し、また多くの曲も提供している北島直樹がアレンジャーとして起用された『The Standard』に続く『II』では、北島は寺井とともに共同プロデューサーとしても大活躍。ジャズの名曲だけではなく、スティーヴィー・ワンダーの「オーヴァージョイド」をはじめとするポップスの名曲も寺井尚子の世界にうまく引き寄せられている。その上質で多くの倍音を含むサウンドは、DSD11.2の世界とおおいに親和性がある。

寺井尚子に続いて、ジャパニーズ・ロック・バンド、スーパーカーもアルバム・デビュー20周年か! ジャンルの違いがあるとはいえ、そう言われても感覚的にはだいぶ遠い印象があったけどそれは思い込みってやつですね。青森出身の4人組スーパーカーがシングル「cream soda」でデビューしたのは1997年。ノイジーなギターに男女のヴォーカルが乗るということでマイ・ブラッディ・ヴァレンタインやジーザス&メリー・チェインなどとの類似性を持ったギター・ロックであった彼らはその後エレクトロニクスとの親和性を高めていき、元電気グルーヴの砂原良徳やROVO(スーパーカーのエレクトロ化は、ROVOの影響があると言われている)の益子樹をプロデューサーに迎えてロックを超えた新次元に突入したのにもかかわらず、2005年のライヴをもって残念ながら解散。2011年にはメンバーの中村弘二によって“redesign”されたアルバム『RE;SUPERCAR』と題された“再構築”アルバムが2枚リリースされたり、解散後もいくつかの曲がテレビCMやアニメ、ゲーム音楽に使用されたりしていたが、昨2017年9月にシングル・デビュー20周年を記念したオリジナル・アルバム5作のアナログレコード化が実現したことで、再度彼らに注目が集まるようになった。ただし、ハイレゾ的にはなかなか微妙で(笑)。2016年7月に4作目『HIGHVISION』(2002年)と5作目『ANSWER』(2004年/ラスト・アルバム)があいついでハイレゾ(どちらも48kHz/24bit)で配信されたあと、2017年10月にデビュー・アルバム『スリーアウトチェンジ』がハイレゾ(96kHz/24bit)で配信されたのだが、このアルバムのハイレゾ版のリマスターはおそらくアナログと同じくバーニー・グランドマンによってリマスタリングされた音源を使っていると思われる。アナログはアルバム5枚すべてリマスターで出ているので、当然そのマスターを使ったハイレゾ版が順次すべて出るものだと思っていたら、どういうわけかオリジナル・アルバムのハイレゾ化はその後続行されず、代わりと言ってはなんだけどこの新しく編成されたオールタイム・ベスト盤が登場したという次第なのである。配信のフォーマットは統一されておらず、すべて24bitながらサンプリングレートは44.1、48、96kHzが混在しているという不思議なものなのだが、全体を通した聴感は悪くない。曲順は時代順ではない(いや、なんせラスト・シングルが1曲目に来ているんだから……笑)が、その分いろいろな妄想ができる曲順とも言えそう。ひたすら気持ちいいハイレゾ・リスニングを楽しめる。

プロツールス・システムによるPCM192kHz/32bitとPyramixシステムによるDSD11.2で無編集一発録音された井筒香奈江の最新作……もうこれを知った段階でハイレゾ・マニアなら涎が垂れてしかたないだろう。かくいう筆者もそうである(今回これ2回目)。井筒香奈江といえばそのアルバムはどれも音楽的に素晴らしいのと同時に、オーディオファイルをうならせる高音質録音で有名なシンガーであり、別名“オーディオ・イベントの女王”と呼ばれているらしい。2011年にその第1作が出た『時のまにまに』は、以後第4集までシリーズ化され、続いては新たに『リンデンバウムより』を2016年にリリース。それらはCDだけではなく、ハイレゾ配信もなされたが、特筆すべきなのは最初から24bitデータだけではなく、より高品位な32bitデータも配信されていたことだ。ただし、これらのもともとのデータの基本は96kHz/24bitであり、それ以上のデータは“Eilex HD Remaster”という技術を用いてアップサンプリングされて作成されたものであった。アイレックス社が開発した“Eilex HD Remaster”も非常に優れた技術であり、事実それを用いてアップサンプリングされたデータの音質は素晴らしいものであったのだが……しかし、今回の井筒香奈江(より詳細に言えば、彼女のトリオであるLaidback名義なのだが)によるこの『Laidback2018』は、待望の“初めからスーパーハイレゾ”による録音なのである。素晴らしい空間、素晴らしいマイクロホン、素晴らしいコンソールを誇る乃木坂のSony Music Studioで、名手・高田英男のエンジニアリングによって、井筒の美しいヴォーカル、藤澤由二の伸びやかなピアノ、小川浩史の深々と沈み込みながら躍動感を失わないベースを中心に名手たちをゲストに迎えてカヴァー・ナンバーから井筒のオリジナルも3曲加えて、修正なしの一発録音という、名手がやれば音楽的にも音質的にも最高の方法で収録された音楽がここにある。192kHz/32bitのおそろしくディープな音響にはとにかくひれ伏すしかないが、こうなるとDSD11.2での配信もぜひいつか実現してほしくなるのはぜいたくな悩みかもしれない。
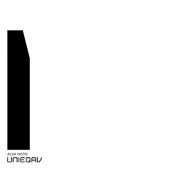
アルヴァ・ノト、本名カールステン・ニコライ。ドイツはベルリンを拠点に活動する電子音楽家である。いわゆるグリッチと呼ばれるノイジーなエレクトロニカ・サウンドを追求し続けている彼は、とくに日本では坂本龍一との共作(2018年5月現在、5枚のアルバムがリリースされている)で知られており、2016年の映画『レヴェナント:蘇えりし者』(アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督)の音楽を坂本龍一、ブライス・デスナー(アメリカのロック・バンド、ザ・ナショナルのメンバー)と共同作曲し、グラミー賞やゴールデン・グローブ賞などにノミネートされていることでも話題を呼んだ。そんな彼の最新作が『UNIEQAV』である。本作は第1作『UNITXT』(2008年)、第2作『UNIVRS』(2011年)のコンセプトを発展させた“UNIシリーズ”三部作を締めくくる完結編となる作品で、なおかつシリーズとして初のハイレゾ(44.1kHz/24bit)作品となるものだ。アルヴァ・ノトの作品としては比較的ダンス・フロアよりのリズム・オリエンテッドな“UNIシリーズ”は、彼が以前に東京は代官山にあるクラブ“UNIT”にブッキングされたことをきっかけとしてスタートしたシリーズである。昨年末に東京の草月会館で坂本龍一をキュレーターとして開催された、クラシック界の異端児であり死後もその作品に注目が集まっているピアニスト、グレン・グールド生誕85周年を記念したイベント「グレン・グールド・ギャザリング」に坂本、クリスチャン・フェネス、フランチェスコ・トリスターノとともに参加して独自の解釈でグレン・グールドの世界を拡大してみせたのに続き、この4月にはこのアルバムを引っ提げての来日公演もおこなっているので、その作品がやっとハイレゾとして登場した今こそがアルヴァ・ノトというアーティストを知るには絶好の機会かもしれない。本作は彼の作品としては比較的なじみやすい曲調ではあるので、ここからその深遠なエレクトロニカ/グリッチ・シーンを掘り下げていくのもいいだろう。この作品はカールステン曰く「音響的に潜水を表現している」ということで、とくに深々となる低音が肝となる作品であり、それはハイレゾでこそリアルに再現できると断言したい。

 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。