注目タイトル Pick Up
60歳を超えたシュモロ・ミンツの“生成り”のイザイ文/長谷川教通
シュロモ・ミンツといえば1980年代にさっそうと登場し、バッハの「無伴奏ヴァイオリンソナタとパルティータ全曲」やパガニーニの「24のカプリース」、メンデルスゾーンやブルッフ、プロコフィエフ、シベリウスのヴァイオリン協奏曲など有名曲を立て続けに録音し、鮮やかなテクニックと音色の美しさで音楽ファンを魅了した。
57年のモスクワ生まれで2歳の時にイスラエルへ移住し、幼少の頃からピアノとヴァイオリンを始め、アイザック・スターンに認められて11歳でアメリカに渡り、ジュリアード音楽院ではドロシー・ディレイに師事という英才教育を受け、20歳代で世界的なスターとなったのに、30歳代前半で録音活動をほとんど休止してしまった。もちろん音楽活動は続けたし、指揮活動や有名な国際コンクールの審査員もつとめるほか、後進の指導にも熱心に取り組んできた。そんなミンツも60歳を超え、芸術的にも人間的にも円熟の度を増してきたいま、イザイの「無伴奏ヴァイオリン・ソナタ全曲」を録音したのだから、これは大注目だ。
6曲を録音するにあたって、オリジナルの楽譜からも多くのヒントを得たようで、虚飾を排して作品に直に向き合おうとする姿勢が際立つ。けっして表面を美しく仕上げようとした演奏ではない。いわば生成りの質感で、ざらつきや毛羽立ちがあってもあえて化粧はしない。あくまでイザイが楽譜に込めた意志にかぎりなく迫って、それを多くの人と共有したい……そう考えたに違いない。何度も聴き込んでほしい演奏だ。
アルテミス・カルテットが結成されたのは1989年。北ドイツのリューベック音楽大学の学生4人で結成され、すでに30年。アルバン・ベルク四重奏団やラサール弦楽四重奏団、エマーソン弦楽四重奏団、ジュリアード弦楽四重奏団といった一流のカルテットの指導を受け、96年のミュンヘン国際コンクールで第1位、97年イタリアのプレミオ・パオロ・ボルチアーニ国際弦楽四重奏コンクールでも第1位を獲得。ベルリンを拠点に世界最高峰のカルテットとして活躍してきたが、その間に何度かのメンバー入れ替えを行なって、そのたびに新しい方向性を見出しながら進化してきた。
2007年にはヴィオラ奏者が家庭の事情で離脱してフリーデマン・ワイグルが加わり、またヴァイオリン奏者の一人も腕の故障でグレゴール・ジーグルに交代。さらに2012年には第一ヴァイオリンがラトヴィア生まれのヴィネタ・サレイカに代わり、新生アルテミス・カルテットがスタート。その最初の録音がメンデルスゾーンだ。3人の男性陣に一歩も引けをとらないエネルギッシュな演奏がすばらしい。そして、このメンバーとしての最後の録音がブラームスの「弦楽四重奏曲第1番、第3番」だ。サレイカの溌剌としたヴァイオリンをチェロのエッカート・ルンゲを中心に3人の男性陣が深みのある響きで支え、第2番もこのメンバーで……と期待したのだが、ヴィオラのワイグルが病に倒れて死去。
そこで第二ヴァイオリンのジーグルがヴィオラを担当し、新たにアンシア・クレストンを迎える。こうして再スタート。その第1弾に選んだのがショスタコーヴィチだった。まず「ピアノ五重奏」から聴こう。この作品はピアノの印象的なソロから入る。だからエリザーベト・レオンスカヤがどう弾くかで、演奏のコンセプトが決まると言っても良い。ショスタコーヴィチには戦争の恐怖や独裁体制への反抗など重苦しく激しい作品が多いが、このピアノ五重奏は違う。1941年にスターリン賞をとったことで社会主義リアリズムへの迎合だと非難されることもあるが、レオンスカヤが弾きだしたとたんに“それは違う”と感じるだろう。彼女ならではのリリシズム。そこに弦のアンサンブルが寄り添う。ショスタコーヴィチの心の声を聴こうとする。叙情的で哀しさや穏やかさなどが融け合いながら流れている。弦楽四重奏曲第5番、第7番の充実した燃焼度の高い演奏もみごと。
おそらくアルテミス・カルテットは新しいメンバーで弦楽四重奏曲全曲録音へと進んでいくだろうし、それをぜひとも期待したい。もちろん作品によって表情は変化するとしても、現代カルテットならではの完璧な技術と緻密でエネルギッシュなアンサンブルをベースにしながら、政治や社会背景を超えた人間ショスタコーヴィチの内なる声を引き出そうとするアプローチは貫き通してほしいと思う。
ヴァレンティーナ・リシッツァといえばYouTubeを思い起こす人も多いだろう。おそらくYouTubeを使ったプロモーションで世界的な知名度アップに成功した初のクラシック音楽家と言ってもいい。リシッツァは1973年ウクライナのキエフ生まれ。3歳からピアノを始め、1年後にはソロ・コンサートを催したというから早熟の天才肌。キエフ音楽院ではアレクセイ・クズネツォフと出会い、マレイ・ドラノフ国際2台ピアノコンクールで優勝する。1992年にはアメリカに渡って、同年クズネツォフと結婚。そして2006年にクズネツォフが制作した「Valentina Lisitsa Chopin Etudes」をYouTubeにアップしたところ、これが大人気。いまやリシッツァのチャンネル登録数は50万人以上というからすごい。
2012年にはデッカと契約し、いよいよ世界の人気ピアニストとしての階段を駆け上がっていく。そんな彼女の最新作だ。2017年12月~2018年4月にウィーンでセッション録音されたCD10枚分にも及ぶチャイコフスキーの『ソロ・ピアノ作品全集』だ。最初期のピアノ作品から24曲からなる「子供のアルバム」やクズネツォフも加わった4手のための「50のロシア民謡集」、晩年の小品集など、ほどんど聴いたことがない作品を通してチャイコフスキーの素顔を発見させてくれる愉しさ。もちろん「四季」や「くるみ割り人形」「スラブ行進曲」「序曲1812年」のピアノ・ソロ編曲版といった有名作品も収録されている。これだけの曲数を4~5ヵ月の期間で集中的に録音するというきわめて野心的な録音だ。
リシッツァは、まろやかな音色で一曲一曲を愛おしむように弾き、随所に彼女らしいチャーミングな表情を折り込みながら、感性の赴くまま、心から素敵な作品を奏でているんだという想いが伝わってくる。「くるみ割り人形」で聴かせるキラキラと飛び交うような高音域がすばらしい。作品72の「18の小品」では、最晩年のチャイコフスキーがこんなにも魅力的な感覚をピアノに注ぎ込んでいたんだと感動させられる。
NHK交響楽団のチェロ奏者でチェロ四重奏団、ラ・クァルティーナのメンバーとしても活躍する桑田歩のソロ・アルバムだ。ショパンには室内楽曲が4曲、うちチェロとピアノのための作品が3曲ある。もう1曲のピアノ三重奏曲もまるでチェロのためのような作品なので、ショパンと言えばピアノがすべてと思われがちだが、チェロへの愛着も深かったのだ。「序奏と華麗なるポロネーズハ長調」「マイヤベーアの歌劇『悪魔のロベール』の主題による協奏的大二重奏曲」は20歳前後の作品だが、チェロ・ソナタは生前に発表・出版された最後の作品となった。チェロ・ソナタでは、旋律の美しさはショパンの面目躍如だが、チェロとピアノが絡み合いながら進行する音楽は、きわめて高度な作曲技法が駆使されており、演奏者にとってはけっして簡単な曲ではない。
最近ではチェロとピアノのための3曲をまとめて録音するチェリストも多くなっているが、このアルバムではそれに加えて「ポーランドの歌」が収録されている。これがいい。もともとは17曲からなる作品74の歌曲集で、その中からチェロが映える5曲を選んで、桑田自身がチェロ用に編曲したもの。美しくって、優しくって、哀しくって……そんな旋律。歌詞を知ればなおさら心惹かれてしまう。チェロの音色がまろやかで素敵だ。
チェロをどう録音するかは録音家、演奏者にとってとても重要なこと。マイスターミュージックはワンポイント録音にこだわる。デトリック・デ・ゲアールの真空管ハンドメイドのマイクをL/R各チャンネル1本で録る。ところが、チェロからどの距離で、どの向きで録るかで音色の印象が変わってしまう。桑田歩の意図する表現は、ショパンが愛着を持つチェロの音色にどんな感情を込めようとしたのか、ポーランドへの愛惜や内なる心の奥底にある想いに限りなく寄り添おうとするもの。外へ向かって大声でアピールしたり聴き映えを意識することではない。
では、桑田の表現をどう録ったのか。8年前のソロ・アルバム『メロディー チェロ小品集』と比較してみると、録音の条件は似通っているはずだが、今回のほうがより繊細でまろやかで低音域の響きも豊かだ。表面の照りを抑えたつや消しの味わい。超高音質のサンプリング周波数384kHzで録ることでマットな質感が生きるし、ほんのわずかなニュアンスの変化も逃すことはない……という狙いだろう。384kHzなら鮮やかで生々しい音色では? と先入観を持っては意図に反する。ふくよかで、きめ細かく、豊かな響きが聴き手を包み込むような、きわめて音楽的な録音だ。
2019年1月24~27日のロサンゼルス、ウォルトディズニー・コンサート・ホールのライヴ録音が96kHz/24bitでハイレゾ配信された。もちろんグスターボ・ドゥダメル率いるロサンゼルス・フィルハーモニックの来日公演に合わせたリリースだ。NHKホールでもジョン・ウィリアムズ・プログラムで盛り上がる。
ロサンゼルス・フィルハーモニックといえば1970年代、ズービン・メータが音楽監督で活躍した時代にはスペクタクルなサウンドで「スター・ウォーズ組曲」などを演奏し大人気。あれから約半世紀。ドゥダメルという超ホットな指揮者とともに“あの時代の熱気”を! なんて書くと、“いやいや、ドゥダメルを迎えてもう10年。あの時代を超えて今が絶頂期でしょ!”と叱られてしまいそう。
輝かしくてパワフルなファンファーレ……華やかなホールの雰囲気が伝わってくる。「未知との遭遇」から「ジョーズ」「ハリー・ポッター」と続き、ピアニシモからグーンとアクセルを踏み込むと吹き上がる音圧感とブラスのぶっとくて強靱な鳴りがすばらしい。ライヴ録音だが、ダイナミックレンジが圧巻で、鮮度も高く厚みのある音で録れている。ヘッドフォンで聴くと音数の多さに驚かされる。響きは明るく痛快だ。「シンドラーのリスト」や「さゆりのテーマ」で聴かせる旋律の巧さ。オケの奏者にたっぷりと歌わせるあたりがドゥダメルらしい。ジョン・ウィリアムズによるお馴染みの音楽が次々とあふれだしてくる。お待ちかねの「スター・ウォーズ」からも4曲。スピーカーからハリウッド伝統のゴージャスなサウンドが飛び出してくる。やっぱりロサンゼルス・フィルハーモニックにはスクリーン・ミュージックがよく似合う。エンディングの「スーパーマンのマーチ」が終わると盛大な拍手と「ブラボー」の嵐。さすがドゥダメル人気はすごい!
ロンドンの伝統を受け継ぐ新世代ジャズ・ユニット、コメット・イズ・カミング文/國枝志郎

ロバート・グラスパーやカマシ・ワシントンといったアメリカの新世代ジャズ・ミュージシャンの目の覚めるような活動で、いまジャズという言葉はまったく新しい文脈で語られ始めているわけだが、アメリカに対抗してイギリスだって負けてはいない。むしろイギリスは昔からソウルやR&Bやハウスやテクノやヒップホップといった多ジャンルの音楽にジャズを混在させていくことに長けていた。とくにロンドンという街においては、その折衷的で雑食的な音楽文化を象徴するように90年代の終わりにブロークンビーツというシーンがあり、ジャズ・サックス奏者コートニー・パインなどがジャズ、ヒップホップ、ハウス、テクノ、ドラムンベース、レゲエ、アフロ、ファンクなどを立体的に融合したブレイクビーツ=ブロークンビーツのシーンを確立していたことをいまさらのように思い出す。そして今、その延長線上にシャバカ・ハッチングスというサックス奏者の存在がある。1984年、ロンドン生まれのシャバカは幼くしてカリブ海西インド諸島の国バルバドスに移住、そしてふたたびイギリスに戻り、ロンドンを拠点に活動を繰り広げている。その影響力はとてもこのスペースでは書ききれないが、シャバカはいくつかのユニットで活動していて、それがいずれも現代のジャズ・シーンにあって非常に重要なものであるのと同時に、ハイレゾで手に入るということは特筆すべきだろう。シャバカ・アンド・ジ・アンセスターズ名義でのアルバム『Wisdom Of Elders』(48kHz/24bit)は2016年にUK音楽シーンの最重要人物ジャイルズ・ピーターソンのレーベル、ブラウンズウッドから、そして同じ年にはツイン・サックスを擁するメルト・ユアセルフ・ダウンのセカンド・アルバム『Last Evenings On Earth』(96kHz/24bit)をLeafから、またサンズ・オブ・ケメット名義でのセカンド『ユア・クイーン・イズ・ア・レプタイル』(96kHz/24bit)をメジャーの名門インパルス!から2018年にリリースしており、いずれも聴き逃せないものではあるが、ここで注目すべきはインパルス!から2019年に発表されたばかりのコメット・イズ・カミング名義でのセカンド『Trust In The Lifeforce Of The Deep Mystery』(96kHz/24bit)だ。それは伝統的なジャズとエレクトロニカがクラッシュしたようなサウンドであり、その壮大さはコズミック・ソウルと呼びたいところ。やはりハイレゾでリリースされているファースト『Channel the Spirits』(96kHz/24bit)とともにまずは揃えてお聴きいただきたい。
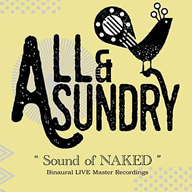
これはハイレゾ遊び心をくすぐるリリースだ。バイノーラルである。ダミーヘッドを使って立体的な音響を収録するという技術は古くから知られているものであるが、ヘッドフォンでの聴取がその効果を知るにはもっとも適しているということもあり、この技術を応用したくなるひとがいるのは当然だ。とくにハイレゾが一般的に広まってきた背景には、大掛かりなシステムよりもむしろデジタル・オーディオ・プレイヤーとヘッドフォンによってハイレゾを気軽に楽しむということが一般化してきたという事実があり、既存音源をヘッドフォン・リスニングに特化させるHPL(Headphone Listening)というエンコード技術を使ってより立体的で自然な音楽定位を実現したハイレゾ音源もいくつかリリースされている昨今、こうした試みは歓迎したいところである。All & Sundryは、名古屋でジャズ・シンガーとして活動してきた鈴木尊子と、シンガー・ソングライターとして演奏活動を行なってきた砂辺佳春がとあるライヴ・イベントで意気投合、2012年に結成されたヴォーカル&ギターのデュオ。2014年10月に発売されたAll & Sundryのファースト・アルバム『Sound of NAKED』は、もともとバイノーラル技術を使ってライヴ・レコーディングされていたとのことで、今回ようやくその本来の響きを収めたハイレゾ配信が実現したというわけである(聴き比べてみたかったけど、オリジナルは現在入手困難のもよう)。“バイノーラルアート作品は繊細な非言語コミュニケーション情報を最大限に生かすため、 マスタリング工程における音圧向上のためのコンプレッサー処理やEQ処理は行っていません”ということが謳われているが、実際にヘッドフォンで聴いてみると非常に自然な音質で、臨場感あふれる立体音響が楽しめる。しかもハイレゾとしては最高品位のデータ(192kHz/24bit)での配信であり、生々しいギターの弦の響きと豊かなヴォーカルが心を躍らせてくれる素晴らしい作品だ。

ポスト・クラシカルというジャンルの成熟ぶりはここ数年目をみはるばかりである。ことヨーロッパにおけるこのジャンルのもてはやされかたはなかなか日本にいては見えにくいものではあるのだが、ここでとりあげるフランスのアーティスト、クエンティン・サージャックのようなアーティストがとくに日本で長いこと紹介され続けているのは素晴らしいことだ。scholeという日本のレーベルの偉業を称えたい。クエンティン・サージャックはフランスの作曲家/ピアニスト。2010年に『La Chambre Claire』でデビュー。その後2013年にフランス映画のサウンドトラックでもあるセカンド・アルバム『BRIGHT DAYS AHEAD』、2014年には、2012年に来日した折に東京で録音された通算3枚目となるアルバム『Piano Memories』を発表している。印象派ふうの美しいピアノの響きに、クエンティンがアメリカ留学時代に培ったミニマル音楽などからの影響も感じさせる、音響彫刻的な響きが素晴らしいこれらのアルバムはぜひハイレゾで聴きたいと思わせるものがあるのだが、残念ながらここまでの作品はハイレゾが出ていない。今後の発売に期待したいところだが、これ以降の作品のほとんどは幸運なことにハイレゾで手に入るので、ぜひその静謐というだけにはとどまらない豊かな響きをハイレゾで楽しんでいただきたい。ピアノのみだった前作から一転してマリンバ、ヴィブラフォン、グロッケンなどのパーカッションが加わって多彩な響きを聞かせる2016年の『Far Islands and Near Places』、2015年に英リーズ出身のアンビエント・ユニット、ダコタ・スイートとともに来日した際に日本で録音された『Wintersong』(2016年、実は2014年にもこの両者のコラボレーション・アルバム『there is calm to be done』が発売されているが、こちらはハイレゾ未配信)、そして2019年の最新作『COMPANION』はすべて96kHz/24bitという高音質での配信が実現していてありがたい。最新作は以前の作品に比べてエレクトロニクスの比重が増え、リズムのバラエティも格段に豊かになっている。ハイレゾでこそ生きるカラフルな響き。

何の前情報もなく、ただザッピング的に今月発売のハイレゾ音源を聞いていてトラック・サーチボタンを押す手が思わず止まったアルバムがこれ。サクソフォンのソロ、バックに流れるかぎりなく透明なハーモニー。これはすごいハイレゾ向き! と興奮した。アルバム情報を見てみる。テナー・サックス・プレイヤー川嶋哲郎の、初リーダー作から20年、通算30枚目のアルバムだという。それにしても素晴らしい響きだ。もともとカルテットのような小編成でのパフォーマンスが多かった(まあそれが普通でしょうが)川嶋にとって、初の大編成アンサンブルをバックにした作品とのことだが、そのアンサンブルがとても変わっている。フルート6(ピッコロ持ち替え含む)、クラリネット5(バスクラリネット、サックス持ち替え含む)、サックス6(フルート、クラリネット持ち替え含む)、ピアノ、パーカッション、そして川嶋のテナー・サックス、ソプラノ・サックスおよびフルートという編成。そう、トランペットやトロンボーンといった金管楽器がいない木管アンサンブルなのである。金管がいないとどうなるか。木管は金管に比べたら鋭いアタックが出しにくい(出せるけど金管にはとうていかなわない)。そのかわり、リード楽器ならではの清澄なハーモニーを聴くことができる。清澄なだけではない。最高音のピッコロから低音のバスクラリネットまでそろったリード楽器が織りなすハーモニーは時にオルガンのような分厚さも持ち合わせているのだ。とくに1曲目の「CRESTA PRELUDE」から2曲目の「CRESTA」で聴かれるハーモニーの美しさはどうだ。まさにアルバム・タイトルから想起されるような、澄んだ水の流れを思わせる響き。なかでも「CRESTA」の、川嶋のテナー・ソロが終わった3分すぎあたりから曲終わりにかけての、フルートを中心とした白玉のロングトーン・ハーモニーと、合いの手のようにさしはさまれるサックスの重奏の幻想的な美しさは比類がない。ラストの「WATER OF TEARS」では、バスクラリネットの低音を効果的に生かしたたっぷりとしたハーモニーが、得も言われぬ余韻を残す。倍音のすべてをとらえるようなハイレゾ(96kHz/24bit)の響きに包まれる幸福感は筆舌に尽くしがたい。ずっと浸っていたいと思わせる美しさ。

『あまちゃん』以降、とにかく劇伴で大友良英の名前は見ない日がないほどの大人気となった観がある。かつて高柳昌行に弟子入りして即興演奏やノイズ、フリー・ジャズなどで独自の道を切り拓いてきた大友良英が、まさかここまで人口に膾炙する存在になろうとは……。しかし考えてみればノイズにせよ即興演奏にせよ、それはあるひとつのジャンルを指すものではなく、あらゆる表現を内包したジャンルレスなものと考えれば納得もいくかもしれないが、それにしても大友の制限を設けないその音楽性の豊かさは、テレビや映画で音楽にそれほど興味を持たないひとまで魅了してしまったのだ。なんと素晴らしいことだろう。そんな大友の最新サウンドトラックは宮藤官九郎脚本のNHK大河ドラマ『いだてん~東京オリムピック噺~』。こちら現時点では前編がハイレゾ(48kHz/24bit)で配信されているが、あえてここでは同時に配信が始まったオムニバス・アルバムのほうをご紹介。冒頭からいきなりドライヴィンなサックスのソロの「白洲次郎メインテーマ」が超絶しびれる。2009年にNHKテレビで放映された番組で、この番組の高評価がのちに大友に『あまちゃん』のヒットをもたらしたきっかけとなっていることは間違いないだろう。もちろんその『あまちゃん』のオープニングテーマも収録されているし、資生堂マキアージュCMソング「LADY-EMBELLIE」も入っている。この、映像を伴ったサウンドトラックとしての大友の音楽を集めたアルバムは、ほのぼのとした曲調のものもあれば、大友のかつての即興時代を思わせるような荒々しいギターの一閃が聴けるものもあり、と非常にバラエティ豊かなものだが、そのいずれからも大友ならではの人懐っこさともいえるトレードマークのような響きがかならず聴こえてくる。こうしたかたちで大友の音楽家の一側面をハイレゾ(48kHz/24bit)でまとめて聴ける喜びは大きいな。

 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。