高音質放送i-dio HQ SELECTIONのランキング紹介番組『「NOW」supported by e-onkyo music』(毎日 22:00〜23:00)にて、この連載で取り上げたアルバムから國枝さんが選んだ1曲を放送します。今月の放送は9月4日(水)の「ROCK'N'POPS NOW」から。
注目タイトル Pick Up
フレーミング・リップスのめくるめくサイケデリック・ワールド文/國枝志郎


Helios(ヘリオス)の2006年と2008年リリースのアルバムが今年になって相次いでハイレゾリリース! ヘリオスはボストン在住のKeith Kenniff(キース・ケニフ)によるユニットである。キース・ケニフはアメリカはペンシルベニア州出身で、その後ボストンの名門バークリー音楽大学へ進んで打楽器を専攻。卒業後はAppleやFacebook、Googleといった今をときめく企業のコマーシャル音楽や映画のスコアを手がける売れっ子音楽家となった。試しに彼のウェブサイト(
http://unseen-music.com/)を訪れてみるといい。ものすごい数の映像と音楽に圧倒されること間違いなしだから……。そのいっぽうでキースは少年時代からバンド活動を行なっていた延長として、自身の音楽を追求するためのペルソナをいくつか持っている。エレクトロニカ路線のHelios、ピアノや生楽器をフィーチャーしたポスト・クラシカル路線のGoldmund(ゴールドムンド)、シューゲイザー路線のMint Julep(ミント・ジュレップ/奥方であるホリー・ケニフとのデュオ)など、名義やジャンルを器用に使い分け、数多くのリリースを行なってきた。そんな彼のペルソナの中でメインとなるのがこのヘリオスだ。同名義では2004年のファースト・アルバム『Unomia』でデビューし、2018年リリースの9作目(ミニ・アルバムとリミックス・アルバム含む)となる『Veriditas』が現時点での最新作。2019年の初頭に2006年発表のセカンド『Eingya』が、坂本龍一やデヴィッド・シルヴィアンなどといったアーティストとのコラボレーションでも知られるニューヨークのアーティスト、テイラー・デュプリーによるリマスターで突然CDリイシューされてファンをびっくりさせたのだが、同時にハイレゾ(44.1kHz/24bit)配信も実現したのにはほんとうに驚かされたものだ。しかし事件はそれだけでは終わらない。4枚目のアルバム『Caesura』がまたしてもデュプリーによる素晴らしいリマスタリングを施されてCDとハイレゾ(44.1kHz/24bit)で登場してしまったのだから……。この2枚の名盤はいずれもイギリスのTypeからのリリースだったもの。ポスト・クラシカルとかアンビエントとかのジャンルを超越したこれらの超絶美麗音響工作でこの夏は乗り切れってことなんでしょう(笑)。しかしこのサウンドを聴いていると、最新作『Veriditas』も含めてヘリオス、いや、それだけではなくゴールドムンドなど、キース・ケニフのハイクオリティなサウンドを可能ならすべてハイレゾで届けてほしくてたまらなくなります……。

アメリカの伝統的なフォークやカントリー・ミュージックを、モダンでオルタナティヴに更新してポストロックの装いをより幅広い層にアピール、インディ・ロック・ファンだけではなく多くのリスナーを魅了してきたバンド、ウィルコのリーダー、ジェフ・トゥイーディの最新ソロ・アルバムがハイレゾ(44.1kHz/24bit)で登場……と思ったんだけどちょっと待って。ジェフの最新ソロは『Warm』だったよな……2018年の暮れに出てたよな……あれそういえばジャケットもちょっと違うな……そうなんです。『Warm』じゃない。『Warmer』なんですな。実はこの『Warmer』、2019年4月、レコード・ストア・デイ(RSD)のみの限定アナログ・レコードとして発表されたもので、『Warm』と同じレコーディング・セッションで録られた音源を集めたスピンオフ作品。『Warm』は、ウィルコのスタジオとしてファンにもよく認知されているシカゴのTHE LOFTでレコーディングされ、ジェフ本人がレコーディングからプロデュースまでを手掛け、ジェフの息子でありトゥイーディのメンバーであるスペンサー・トゥイーディやウィルコのドラマーであるグレン・コッチェ、そしてウィルコやジェフの作品も手がけているプロデューサー/エンジニアのトム・シックなども参加して作られたとてもインティメイトなオリジナル曲ばかりの佳作であったが、それはこのスピンオフ作品である『Warmer』でも変わりはない。実はバンドとしてのウィルコの作品はその多くがハイレゾで配信されており、また2017年にリリースされたジェフのソロ『Together At Last』(44.1kHz&96kHz/24bit)、そして息子スペンサーとのユニット、トゥイーディのアルバム『スーキーレイ』(44.1kHz/24bit)もまたハイレゾでの配信が行なわれているので、当然『Warm』もハイレゾ配信されてないとおかしいという思うはあるし、この7月には『Warm』と『Warmer』をカップリングした限定2枚組CDがリリースされたばかりなので、よけいに一緒に配信してくれたらなという思いはあるけど、しかしこの『Warmer』単体でも素晴らしい作品であることは間違いないので、これを聴きながらいつの日か『Warm』もハイレゾで聴けることを心待ちにするのも悪くない。
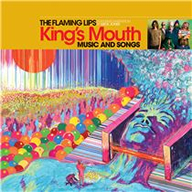
アメリカはオクラホマ州で1983年から活動を続けている長寿バンド、フレーミング・リップスの最新作。実はこの作品もジェフ・トゥイーディの『Warmer』と同じく、レコード・ストア・デイで2019年4月に限定4,000枚のみのアナログ・レコード(カラー・ヴァイナル:gold vinyl仕様)としてリリースされたアルバムである。彼らにとって通算15作目となる作品はこの7月に正規リリースされ、同時にハイレゾでも配信が開始された。『Warmer』よりもハイスペック(96kHz/24bit)であるところも高評価だけど……はい、スペックの度合いが作品の評価には直接的には繋がらないとおっしゃる方もおられましょうが、このコーナーではやはりハイスペックこそ高評価になるというのも事実なのです(笑)……このアルバムはこれまでのフレーミング・リップスのカラフルでサイケデリックなサウンドをさらに推し進めた壮大なサイケデリック絵巻になっているのだが、なにより驚くのがナレーションで参加しているのがクラッシュ〜ビッグ・オーディオ・ダイナマイトのミック・ジョーンズであるという点だ。アルバムはフレーミング・リップスの頭脳、ウェイン・コインによる12の“サイケデリック・インスタレーション”に基づくという。資料によれば「高さ3メートル以上もある巨大なクロムメッキ製の頭部像を中心としたこのインスタレーションで、観る人はその頭部像の口の中へ入り、フレーミング・リップスの音楽とLEDのライト・ショウを楽しめる仕掛けになっている」というもので、このインスタレーションはすでに、American Visionary Art Museumや、Pacific Northwest College of Art、Rough Trade NYCなどで展示され、高い評価を集めているらしい。で、そのインスタレーションの世界を音楽で表現したものがこのアルバムだ。たしかにこの作品はこれまでのリップスの多くの作品を凌駕するめくるめくサイケデリック・ワールドを体現していると感じるが、ミック・ジョーンズの(歌ではない)ナレーションが意外なほど冷静で、現実と非現実をうまく接着させる役割を果たしていると思える。ちなみにリップスもウィルコと並ぶくらいハイレゾ配信作品が数多いので、この最新作にはまれたらぜひ過去の作品にも遡っていただきたいと思います。

うわーこれはあざといわ! でもはまるわ! ここは基本的にハイレゾ・レビュー・コーナーなわけですが、まずこのジャケット! はい、エルヴィス・コステロですね。『ディス・イヤーズ・モデル』ですね〜(笑)。で、なんですか収録曲……いきなりザ・フーみたいな「ファズる心」! 「メロトロンガール」! イモ欽トリオ(あえて言いますが作詞は松本隆、作曲は細野晴臣)「ハイスクールララバイ」の高速スカ・カヴァー! あとなに、フランス・ギャル「Zozoi」! うーむ……これが初めてのSOLEILのハイレゾ(48kHz/24bit)でして、実は私、これでSOLEIL初めて知ったわけなんですが……これがSOLEILにとって3枚目のアルバムなんだそう。しかもこれまでにアルバム、シングルあわせてかなりの数のアナログ・レコードもリリースしていて、売れてるそうです。このSOLEILというのはヴォーカルのそれいゆちゃんが中心なのはもちろんなんですが、実はもとファントムギフト〜les 5-4-3-2-1のサリー久保田、ヒックスヴィルの中森泰弘によるトリオ・ユニットということなので、音に対するこだわり具合が半端ないのも当然といえば当然。しかも、作家陣もなんなのこれ状態。TWEEDEESの沖井礼二と清浦夏実、カーネーションの直枝政広、のん(!)、元GO-BANG'Sの森若香織、元ピチカート・ファイヴの高浪慶太郎、マイクロスターの佐藤清喜、フレネシ……なんなのこの豪華さ。しかもである。この60年代ブリティッシュ・ロック色強いサウンド、全編モノラルで録音されているというこだわりっぷりにはもう脱帽するしかないし、これを15歳(!!)の美少女に歌わせてるんだからもう……これはやられるしかないという感じでしょう。フランス・ギャルのカヴァーでのつたないフランス語もあまりに最高だし、のん作詞作曲による「トキメキ」はもう思わずステップ踏みたくなる佳曲。残念なのはこの作品を最後に中森が脱退してしまうということで、ラストに置かれた中森作によるインスト・トラック「なつやすみ」が胸にしみる。ちらっと聞こえるそれいゆのスキャットもたまらんよなあ……。

今年2019年は、ふたつの偉大なジャズレーベルの記念すべき年である。1939年、アルフレッド・ライオンによってニューヨークで創設されたブルーノート・レコードは創立80年、また69年に西ドイツ(当時)のミュンヘンでマンフレート・アイヒャーが立ち上げたECMレコードは創立50年だ。どちらもジャズというよりあらゆる種類の音楽に大きな影響を与えたレーベルである。このふたつのレーベルの多くの作品は、今ではハイレゾ配信でもかなりの枚数が入手可能であり、ジャズ・ファンのなかにはLPやCDとも違うハイレゾ配信によってさらにこれらのレーベルの音楽の良さを味わっている方も多くおられるに違いない。今回もその中から紹介しようとも思ったのだが、しかしここではそれらの旧作の紹介ではなく、新たにこれらの偉大なレーベルが生み出してきた新しい音楽を継承するようなグループ、それもここ日本からのそれを紹介したい。その名も「land & quiet」。伊藤ゴロー(g)、佐藤浩一(p)、福盛進也(ds)からなるトリオのデビュー作である。Moonや原田知世のプロデュース(どちらもハイレゾ配信あり)や坂本龍一、菊地成孔などとの共演、そして新しいボッサの世界を追求するような音楽でハイレゾとの親和性も非常に高い伊藤、自己のグループ「Melancholy of a Journey」をはじめ、Bungalow、rabbitoo、Cool Jazz Projectなどでもクオリティの高い音楽を聴かせる佐藤、本欄でもECMからのデビュー盤(日本人のECMアーティストは菊地雅章に次いで二人目)を紹介した福盛の3人が生み出す音楽は、期待をはるかに上回る静かな衝撃だ。冒頭からエレクトロなサウンドが静かに流れ始めるところからすでになにか新しいものが生まれそうな予感がビンビンするわけだが、生ピアノとドラムスが入ってくるともうそこは別世界に。パーカッショニストでありヴォーカリストとしても最近脚光を浴びつつある角銅真実(とくにトラック6「雨」におけるヴォーカルはすごい)、伊藤ゴロー作品には欠かせないチェリスト、ロビン・デュプイの参加も奏効しているし、またハイレゾを熟知したエンジニア、奥田泰次の手腕も光る。ラストに置かれたシックの名曲のカヴァーは、シックというよりはロバート・ワイアットの名カヴァーを思い起こさせるような崇高さがある。ハイレゾのスペックは48kHz/24bitで、もちろん素晴らしいサウンドだけど、こういう音楽ならやはりDSDでも聴いてみたくなります。それにしてもこれはいつまでも浸っていたくなる音楽だし、ECMの音楽につけられたキャッチコピー“静寂の次に美しい音”というのをそのままつけたくなるサウンドであることは間違いない。
清楚な声の持ち主、アンナ・ルチア・リヒターのソロ・デビュー作がすごい!文/長谷川教通
2015年10月、ハイティンク指揮するロンドン交響楽団の来日公演で、マーラーの交響曲第4番のソロを歌ったソプラノ。まだ20歳代のアンナ・ルチア・リヒターが聞かせた清楚な声に驚いた音楽ファンも多かったのではないだろうか。2018年9月にはパーヴォ・ヤルヴィ指揮するNHK交響楽団でも同曲を歌った。広いホールでも隅々にまで浸透していく彼女の声の魅力と情念まで感じさせる表現力。彼女は2012年のシューマン・コンクールで優勝しており、これはすばらしいリート歌手が現れたと期待されていたのだ。
アンナ・ルチア・リヒターが「PENTATONE」レーベルへのソロ・デビュー・アルバムでシューベルトを歌った。これは聴かねば!! 「月に寄せて」D259からスタート。シューベルト18歳の愛らしさあふれる逸品だ。彼はすぐ後にゲーテの同じ詞に曲を付けている(D296)が、あえてD259を歌ったあたりがリヒター流。彼女の声の魅力全開だ。清楚で、低音域にはまろやかさがあり、高音域まで艶やか。プログラミングもよく考えられている。2曲目3曲目と盛り上がりを見せて、「ただあこがれを知る者だけが」でフッとトーンを変える。何という伸びやかな声だろうか。ヴィブラートを抑えた旋律線の美しさも際立っている。高音域への飛躍でも、ポルタメント的な小細工を使うことなく、スッと正確な音程で移行する。すごい!
後半のプログラムもみごとで、「エレンの歌」の3曲目「アヴェ・マリア」から「この世からの別れ」D829。この作品はピアノ伴奏付きのモノドラマで、リヒターは静かに心を込めて「Leb' wohl,du schone Erde!(さらば美しき大地よ!)」とプラートベーフェラの詩を朗読する。この声が意外にも低い。そうか、リヒターの声が低音から中音域にかけての表情がきわめて多彩で、高音域でもヒステリックになることなく、どこまでも伸びやかなのは、持って生まれた声帯の幅広い音域とともに共鳴体としても……まさに天からの授かり物。プログラムの最後は「岩上の羊飼い」。ピアノは控えめだが、クラリネットとソプラノが繰り広げる迫真のバトルに息を呑む。クラリネットがノンヴィブラートで歌い上げるとリヒターもそれを上回る声で応える。中間部の悲痛な表情から「Der Fruhling will kommen(春が来ようとしている)」と表情を変え、強靱で輝かしいまでのクライマックス……すばらしい!
これは最高度に洗練されたとびきり上質な演奏。往年の大家から現代の若手まで、あるいはモダン楽器による演奏から古楽器演奏まで、いったい何種類の録音があるのだろうか。演奏スタイルも表現方法も多様化する中で、ヴァイオリニストとしての“個”を主張するのは並大抵の努力では叶わない。有名なコンクールで上位の成績を獲得しても、その後伸び悩み“二十歳すぎればただの人”になってしまうことも少なくない。佐藤俊介の新録音を聴いて、フッとそんなことを思ってしまった。すばらしい音楽家になっている。
彼は1984年生まれだから、まだ30歳代半ば。2013年にヨーロッパの古楽シーンを牽引する名門古楽演奏団体オランダバッハ協会でコンサート・マスターに抜擢され、同時にコンチェルト・ケルンでもコンサート・マスターをつとめた。現在はオランダバッハ協会の芸術監督だ。もちろん最初からバロック・ヴァイオリンを勉強したわけではない。幼い頃にモダン・ヴァイオリンを習い始め、4歳で家族とともにフィラデルフィアに移住し、ジュリアード音楽院のプレカレッジにも学んでいる。当時から彼の才能は際立っていたようで、2000年のニューヨークでのリサイタルでは絶賛されている。その頃から、楽譜に込められた時代背景や奏法までも分析し、演奏に反映させていくプロセスを大切にし、それがバロック音楽や古楽器奏法への関心を高めていった。2009年からミュンヘン音楽・演劇大学で研鑽を積むことになるが、すでに自分自身で古楽器奏法の研究も開始しており、翌年7月にライプツィヒで行なわれたJ.S.バッハ国際コンクールでヴァイオリン部門の第2位と聴衆賞を受けている。この時26歳。
それから10年足らずで世界のトップにまで駆け上がってしまった。オランダバッハ協会では2013年からバッハの全曲演奏と収録を行なう“All of Bach”を続けており、それが佐藤俊介の進化が深化に繋がっていくことにどれほどの意味を持っていたかわかるだろう。彼はバッハの書いた音符の一つひとつをどういう音色で、どう発音するべきかを徹底的に研究する。今回の無伴奏の録音でもバロック・ヴァイオリンと弓、ガット弦で弾いていて、紛れもなく古楽奏法なのだが、ギスギスと尖ったところがない。じつに柔軟なボウイング。ありきたりな奏法とは次元が違う。どの音をどれだけ長く保つか、どこで切るか、どうアクセントを付けたらバッハの意図する発音にできるか、とことん考えて弾いている。その音色は、まるで“呼吸する声”であるかのようだ。ほんとに美しい。トラック数31、通しで聴いても約2時間半。魅入られるように演奏に浸ってしまった。
オランダ、ハールレム・ドープスゲジンデ教会で、2017年の録音だ。ヴァイオリンだけを生々しく録ろうとせず、楽器の表情を十分にとらえながら、堂内に放射される響きが震わせる空気感とのバランスが、絶妙なマイクロフォンセッティングで表現されている。
| トラック01〜04. | 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第1番ト短調 BWV1001 | | トラック05〜12. | 無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第1番ロ短調 BWV1002 |
| トラック13〜16. | 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第2番イ短調 BWV1003 |
| トラック17〜21. | 無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番ニ短調 BWV1004 |
| トラック22〜25. | 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第3番ハ長調 BWV1005 |
| トラック26〜31. | 無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第3番ホ長調 BWV1006 |
『SKAZKI』のタイトルは、ロシア語の“おとぎ話”のこと。アルバムに収録されている作品35と作品42の題名からとったもの。ロシアの作曲家ニコライ・メトネルのピアノ作品集だ。あまり馴染みのない名前かもしれないが、1880年ドイツ系ロシア人の両親のもとモスクワで生まれた。1900年にモスクワ音楽院を最優秀の成績で卒業後、ロシアの名ピアニストとして活躍すると同時に、作曲活動も開始。1916年には作曲活動が評価されグリンカ賞を受けている。しかしロシア革命が勃発し、親しかったラフマニノフの後を追うように祖国を離れる。ヨーロッパやアメリカで精力的に演奏活動を行なったが、ストラヴィンスキーやプロコフィエフなどが活躍するパリの前衛的な風潮にはなじめなかったようだ。
最近になってようやく再評価されるようになり、演奏や録音される機会も出てきているが、ラフマニノフとカップリングされるアルバムが目立つように、彼の作風はラフマニノフにも通じるロマンティックな雰囲気があり、そのメロディを聴くと心の奥底にしまってあった幼い時代への素朴な郷愁が呼び覚まされる気がする。それってメトネルならではの個性。日本でも、もっと弾かれ、もっと愛されていいんじゃないだろうか。
「2L」レーベルの最新録音がそのきっかけになってくれたら嬉しい。演奏はノルウェーのベテラン、グンナー・サマ。メトネルのスペシャリストと言われている。2ch、5.1chともに352.8kHz/24bit/DXDで収録されている。e-onkyo musicのサイトでは2chでは88.2kHz/24bitから352.8kHz/24bitまでのflacファイル、2.8MHz/1bitから11.2MHz/1bitまでのDSFファイル、さらに352.8kHz/24bitのMQAファイル。5.1chでは96kHz/24bitと192kHz/24bitのflac、WAV、Dolby HDの各ファイル。これだけ多様なファイル形式で音源が用意されているのは「2L」がトップだろう。リスナーの再生環境によって選べばいいが、オリジナルが352.8kHz/24bitで録音されている以上、音質最優先で行くなら352.8kHz/24bitのflac、好みでDSF11.2MHz/1bitになるだろうが、192kHz/24bit/5.1chで聴くのも捨てがたい。何しろ2気筒のエンジンがいっきに6気筒になるわけで、厚味のある音場感とピアノの音の伸びが圧巻だ。
ヤニック・ネゼ=セガンによるモーツァルト・オペラ・シリーズ最新作は『魔笛』だ。このシリーズは2011年の『ドン・ジョヴァンニ』でスタートし、以後2012年の『コジ・ファン・トゥッテ』、2014年の『後宮からの誘拐』、2015年の『フィガロの結婚』、2017年の『皇帝ティートの慈悲』と続き、いずれもドイツ・グラモフォンによって収録されている。『魔笛』は、その第6弾として2017年のバーデン=バーデン祝祭劇場で行なわれた演奏会形式のライヴ録音だ。
毎回のことだが、まずはビッグネームをズラリと揃えた歌手陣は圧巻としか言いようがない。パパゲーノをロランド・ヴィラゾン、パパゲーナは『フィガロの結婚』でもバルバリーナを好演しているレグラ・ミューレマンが歌う。彼女はまだ30歳代前半だが、モーツァルトはもちろん、バロック・オペラからロッシーニも得意。軽やかで鮮やかなテクニックと清冽な表現力、舞台映えする容姿も兼ね備え、いまや欧米で引っ張りだこのソプラノだ。さらに夜の女王には、これも注目株のアルビナ・シャギムラトヴァ、パミーナにはクリスティアーネ・カルク、タミーノにはクラウス・フロリアン・フォークト……など、もう最高のキャスティング。
これだけの歌手陣を率いるネゼ=セガンは1975年モントリオール生まれ。2018年9月にニューヨーク・メトロポリタン歌劇場の音楽監督に就任。フィラデルフィア管の音楽監督も兼務するというのだから、まさに飛ぶ鳥落とす勢いの躍進ぶりだ。彼の音作りは細部まで神経の行き届いた緻密さが際立っていて、それでいて音楽には活気がある。オケを意のままに操り、聴き手をググッと惹きつけるテンポの扱いやコントラストの表現がじつに快い。音楽が活き活きと鳴っている。
一方の歌手や合唱に対しては、それぞれに自由度を与えながら個性を巧く引き出してくる。何しろテノールのヴィラゾンがパパゲーノを歌うのだ。ちょっとおどけた感じでバリトンのいい味を出している。バリトンでもいけるんじゃないだろうか。個性ある歌手たちが緊張感を保ちながらも互いに掛け合いを愉しんでいるような素敵なステージだ。
ライヴとはいえ演奏会形式なので、録音は明瞭に録れるはず。オケはヨーロッパ室内管弦楽団だ。ヴァイオリンを左右に振り分けた配置で、中央の内声部がとてもクリアで、躍動する弦の動きが、溌剌とした音楽を牽引するエンジン役を担っていることがよくわかる。ヴァイオリンの高音域が意図的に強調されることもなく、解像度が高いのに素直で聴きやすい録音に仕上がっている。
『Une rencontre』というタイトル。“出会い”と訳せるだろうか。こういうアルバムに出会えるのもハイレゾ・サーフィンのいいところだ。まずはチェロを弾くマリー・イティエって? まだ日本ではほとんど知られていないと思うけれど、イティエのサイト(
https://www.marie-ythier.com/)でバイオグラフィを読むと、同時代の作曲家の作品を積極的に初演しているチェリストのようだ。写真を見ると若手と言っていいのではないだろうか。アルバムのコンセプトはフランスの現代作曲家トリスタン・ミュライユを取り上げ、シューマンとの出会いからミュライユの抒情的な側面に焦点を当ててみようというもの。
アルバムはシューマンの「民謡による5つの小曲集」からスタートする。チェロの定番曲としてあまりに有名だが、イティエの手にかかると「オッ」と耳をそばだるような強弱とアクセント。さすが現代音楽のスペシャリストらしく斬新で冴えた表現が聴きものだ。そしてミュライユの作品を挟んで「抒情小曲集」と続き、プログラムの締めはミュライユの編曲による「子供の情景」だ。これは面白い。チェロとピアノにフルートも加わった三重奏だが、ピアノがまるで鈴の音のような効果を出したり、ヴァイオリンとフルートが旋律を歌い継ぎながら色彩感を描いたり、チェロのピチカートをパーカッションのように使ってみたり、フルートにムラ息のような奏法をさせたり、とにかく多彩で遊び心がちりばめられていて愉しい。
トリスタン・ミュライユは1947年生まれ。バリバリの現代作曲家だが、オンド・マルトノ奏者としても知られ、サイモン・ラトル指揮バーミンガム市響によるメシアンの「トゥランガリーラ交響曲」の録音にも参加している。1973年に仲間とともに音楽の実験場としてアンサンブル・イティネレールという組織を立ち上げ、1977年に設立されたフランス国立音響音楽研究所でも学び、音波の倍音をスペクトル解析したり、理論的に倍音を合成する作曲の方法論をとるスペクトル音楽を発想してその方向性を見出したとされるが、難解すぎたり騒音のように感じるようなことはない。このアルバムに収録された作品からは、音の斬新さとともにキチンと音階も感じとれるし、彼がシューマンを料理するとこうなるのか……と、底流に流れる抒情的な出会いから意外な共通点を見出したり、聴き手にとっても刺激的なアルバムになっている。

 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。