注目タイトル Pick Up
20世紀初頭の音楽の意味を現代に投影する、ダニール・トリフォノフの超名演文/長谷川教通
オーボエのアレクセイ・オグリンチュクは、アムステルダムのロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団のトップ奏者。2005年から同楽団に所属して15年。木管楽器はオーケストラの音色にとっては決定的な役割を担うポジション。いまやオグリンチュク抜きでコンセルトヘボウの音色は語れない。フルートのエミリー・バイノンとともにオケの顔としてマリス・ヤンソンス時代のロイヤル・コンセルトヘボウ管を支えた名手といえるだろう。彼はオケのメンバーとしてだけでなく室内楽にも積極的で、最近では指揮活動も行なっている。そんな多彩な才能を持つオグリンチュクが、気心の知れたオケの仲間を率いてモーツァルトの「グラン・パルティータ」を録音した。
この作品、多くの人は映画『アマデウス』を思い起こすのではないだろうか。サリエリが初めてモーツァルトに出会うシーン。サリエリが譜面台に置かれた楽譜を見て第3楽章アダージョンの旋律を追いながら、どんな男なんだろうかと思いを巡らす。そこへ突然現れたモーツァルトが「ぼくの曲だ」と楽譜を持ち去る。サリエリは「えっ、さっきまで悪ふざけをしていた、あんな下品なやつがこの曲を?」と唖然。モーツァルトの並外れた才能は誰よりも理解できるという能力だけを与えられた凡庸さの哀しさ。これは神のいたずらか。
楽器編成はオーボエ、クラリネット、バセットホルン、ファゴットが各2本、ホルンが4本、それにコントラバスが加わるという、当時としてはめずらしいくらいの規模の大きさ。さぞ合わせるのが大変だろうなと思う。ところがコンセルヘボウの巧さ。息が合うなんて表現を使うのが恥ずかしいくらい。アンサンブルの一体感は言うまでもなく、何より響きが生き生きとして、メンバーそれぞれの自発性が音楽の躍動感を引き出している。全7楽章、演奏時間は50分もかかる大曲だが、いっきに聴き通せてしまう。これまでも名演と言われる録音は数多くあるが、この演奏はそれらに比べても最上位に掲げていい。彼らは演奏会でも聴衆から拍手喝采を受けているが、これはコンセルトヘボウ内の小ホールでのセッション録音で、音質は抜群。奏者が絡み合う多彩な響きの変化やグーンと伸びてくるクラリネットやオーボエの音色がリアルにとらえられている。
いま、もっとも勢いのあるピアニストをあげるなら、何人かの名前は浮かぶものの、絶対に外せないのはダニール・トリフォノフ。彼の新録音は『シルヴァー・エイジ』だ。ロシアの芸術がもっとも独創的だった時代に活躍した作曲家たちから、ストラヴィンスキー、プロコフィエフ、スクリャービンの作品を弾く。いずれも時代に先駆けて新しい表現を求めた作品が並んでいる。いかにもトリフォノフらしいプログラムだ。彼自身が作品の持つ先進性や革新性に光を当て、たんに伝統的であることで満足することなく、つねにそれを超えようと努力を惜しまないからだ。その身を削るようなプロセスが彼を進化させているのだ。2017年のドルトムントにおけるミハイル・プレトニョフ指揮マーラー室内管とのショパンもすごかった。プレトニョフ自身の編曲によるオーケストレーションで“新たなショパン像”を提示して話題となった。2018 / 2019年のシーズンにはベルリン・フィルのアーティスト・イン・レジデンスを務め、シューマンやラフマニノフ、スクリャービンなどで注目を浴びた。また、2020年9月にキリル・ペトレンコの指揮で弾いたベートーヴェンのピアノ協奏曲第3番での圧倒的な演奏も記憶に新しい。まさに鬼才!
アルバムには音楽ファンだけでなくオーディオ・ファンにも必聴の作品がずらり。ストラヴィンスキーの「ペトルーシュカからの3楽章」。疾走感の中で、テンポを緩める一瞬の面白さ。その音色にも刺々しさはない。ガガーンと鳴っても混濁感はなし。しかも高音域のタッチの抜けるような輝き。ピアニシモから響きが消え入るまでの美しい余韻。そのダイナミックレンジの広大さは驚異的だ。プロコフィエフのピアノ協奏曲第2番の冒頭では、シンプルな音型の1音1音に目一杯の情感を込めて弾くトリフォノフの集中力と燃焼度の高さは異次元だ。終楽章ではピアノに加え、ワレリー・ゲルギエフ指揮のマリインスキー劇場管が全開で迫ってくる。この圧倒的な音圧感はすごいとしか言いようがない。この中域から低域にかけての音の洪水をひずみなく再生できるだろうか。ピアノは猛烈なスピードなのだが、けっして荒々しくなることがなく、余裕さえ感じさせる。20世紀初頭。時代が激変する社会風潮を象徴するような音楽の意味するものを、100年経た現代に投影するような超名演だ。


最近クリスチャン・ヤルヴィへの注目度が上がってきている。彼の父ネーメはエストニア出身の重鎮指揮者。北ヨーロッパやロシアの近現代作品やチャイコフスキーをはじめとしたバレエ音楽の解釈には定評がある。長男パーヴォはご存じNHK交響楽団の指揮者としておなじみ。いま世界中でもっとも忙しい指揮者の一人と言われる。そして次男の指揮者クリスチャン。ちなみに姉のマーリカはフルーティストだ。クリスチャン・ヤルヴィはエストニアの音楽一家に生まれたのだが、じつは7歳で家族に連れられてアメリカに渡っており、音楽教育のほとんどはアメリカで受けている。どうやら優等生的ではなく、いわばやんちゃな弟といったタイプで、ニューヨークを拠点とする「アブゾリュート・アンサンブル」を結成したり、クラシック音楽の枠を超えた音楽活動を展開している。とはいえ、アルヴォ・ペルトやエルッキ=スヴェン・トゥールなど北ヨーロッパの音楽への傾倒を見れば、クリスチャンのルーツにエストニアの血が色濃く流れているのは間違いない。そんな彼がバルト海フィルハーモニックを率いるのは必然かもしれない。このオケはユース・オーケストラから発展した楽団で、20代を中心としたメンバー構成もあってとにかくフレッシュ。驚異的なテクニックで知られるチューリッヒ出身の若手デイヴィッド・ネーベルのヴァイオリン・ソロで録音した、フィリップ・グラスとストラヴィンスキーのヴァイオリン協奏曲でのエネルギッシュで弾けるようなアンサンブルがすばらしい。ネーベルのまったく乱れることなく疾駆するヴァイオリンの迫力はまさにスリリング。それをサポートするクリスチャンの躍動する指揮ぶりも聴きものだ。さらに最近のチャイコフスキー「眠れる森の美女」も注目だ。クリスチャン自身が再構成した凝縮版で「ドラマティック・シンフォニー」と銘打っている。バレエ音楽としての枠を取り払って、管弦楽曲としての魅力を引き出そうという狙いだ。全体に速めのテンポで、アタックの勢いもありコントラストを強調する。音楽が彩りを変えながらどんどんと流れていく。聴いて愉しい音楽に仕上がっている。録音も鮮やか。ダイナミックでドラマティックな「眠りの森の美女」だ。

1988年のスティリアーテ音楽祭におけるライヴ録音。2016年に亡くなったニコラウス・アーノンクールがヨーロッパ室内管弦楽団を指揮したシューベルトの交響曲全集だ。初のCD化であり、もちろんハイレゾ配信も初というレア音源だ。アーノンクールといえば、バロックや古典派音楽におけるオーケストラの演奏スタイルを激変させた中心人物。賛否両論あって当然だろうが、彼が1990年に録音したヨーロッパ室内管とのベートーヴェン交響曲全集が音楽界に与えた衝撃は大きかった。ところが、その2年前のシューベルトが聴けるというのだ。音楽ファンなら垂涎ものだろう。もちろんアーノンクールは後年ロイヤル・コンセルヘボウ管やベルリン・フィルとの名演も残していて、すばらしい成熟度を聴かせてくれるのだが、これは彼の主張がもっともストレートに表現された演奏と言える。小編成の見通しのよい響きとピリオド奏法による躍動感。それまでの巨匠たちが聴かせた「未完成」や「ザ・グレート」の偉大な演奏スタイルを根底から覆してしまったのだ。その一方で、アーノンクールの演奏によって初期の第1番や第2番が「こう演奏すれば、青年シューベルトの魅力が伝わるんだ」と気づき、既成概念という壁を見直した演奏家たちも多かったのではないだろうか。この全集はオーストリア放送協会(ORF)が所蔵していた音源をリマスターしたもので、リマスタリングには楽団員のクリスティアン・アイゼンベルガーが立ち会って、当時のサウンドを忠実に蘇らせたという。とてもクリアな響きで、各パートの細かな動きも克明に再現されているが、鮮烈なのにヴァイオリンを強調しすぎることもなく、刺々しさが抑えられていて美しい。低音部の機敏な演奏が明瞭にとらえられている。音楽ファン必携の全集と言えるだろう。
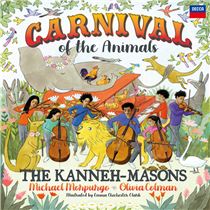
ザ・カネー=メイソンズのアルバムが楽しい。メンバーの中心は2018年ヘンリー王子のロイヤル・ウェディングで演奏し、いっきに人気沸騰したシェク・カネー=メイソンだが、彼の兄弟姉妹も楽器演奏に長けていて、11歳から24歳の7人で構成されたのが「ザ・カネー=メイソンズ」。このアルバムではピアニストの長姉イサタをはじめ、それぞれヴァイオリン、チェロ、ピアノを担当する7人に腕利きの助っ人が加わってサン=サーンスの「動物の謝肉祭」を弾く。緊張もするだろうが、ユーモラスだったり嬉しそうだったり、真剣な中にも楽しさがいっぱいの演奏を展開している。それぞれの曲のはじめにはナレーションが入るが、これは児童文学作家でもあるマイケル・モルパーゴの書き下ろし。担当するのは男声がモルパーゴ自身で、女声が女優のオリビア・コールマン。この2人のナレーションがとてもはっきりした英語なので、ちょっと慣れれば聴き取れるのではないだろうか。こういう演奏に下手な評論など必要ない。彼らが醸し出す雰囲気とか、音楽を通じて伝えてくるピュアなメッセージを受け取るのがいい。
謝肉祭の後は「戦火の馬」の著者でもあるモルパーゴによるクリスマス童話「Grandpa Christmas(おじいちゃんがのこしたものは…)」が続く。チャイコフスキーの「こんぺい糖の精の踊り」やグリーグの「小鳥」、バルトークの「44のヴァイオリン二重奏曲」から選んだ曲に「熊蜂の飛行」などの人気曲を選び、曲の間におじいちゃん役のモルパーゴと孫娘役の最年少マリアトゥのナレーションが交互に入るというプログラム。心温まるお話と楽しい音楽を聴きながら、家族いっしょのクリスマスを過ごしてはどうだろうか。アルバムの締めはシェクが大好きなボブ・マーリーの「リデンプション・ソング」だ。
グレン・グールド名義のアルバムからヒップホップ・ビートが聞こえる文/國枝志郎

2016年に当欄で取り上げたカフカ鼾(いびき)のアルバム『nemutte』を覚えていらっしゃる方がおられることを祈りながら今回、そのカフカ鼾(結成は2013年)のドラマーでもあった山本達久のソロ・アルバムを取り上げよう。ジム・オルーク、石橋英子とのトリオ、カフカ鼾のほか、石橋のバックを務めたバンド“もう死んだ人たち”にも参加、青葉市子(当欄で取り上げなかったが、2017年末に青葉、三宅純、渡辺等と山本のカルテットでハイレゾのアルバム『プネウマ』がリリースされている)、UA、七尾旅人、Phew、勝井祐二(ROVO)、ナカコーからジャズ・サックスの坂田明といったツワモノたちと共演してきたジャンルレスなドラマー / パーカッショニスト、山本達久。その彼が自身の名前でソロ・アルバムをリリースするのは案外めずらしいのだが、このコロナ禍でリアルな公演が難しくなっていた春先以降、山本はBandcampで毎月のように電子音楽のソロ・アルバムをリリースしてきた(4月に『shishushushuka』、5月に『mipyokopyoko / mupyokopyoko』、6月に『Stray Cymbals』、7月に『t.a.z.』、8月に『Mosaic modulations』)。それを受けて、10月に2枚のソロ・アルバムが登場。1枚は日本の電子音楽レーベルNEWHERE MUSICからの『ashiato』(足跡)、そしてもう1枚がオーストラリアのエクスペリメンタル・ギタリスト、オーレン・アンバーチ主宰のレーベルBlack Truffleからの『ashioto』(足音)である。石橋英子(p)と須藤利明(b)も参加した音響彫刻的とも言えるこの2枚は、山本曰く「ひとつの物語でふたつの映画を撮るように」作られたものだという。いわば一卵性双生児のようなものらしい。それをわざわざ違う国の違うレーベルから出すというのもユニークだ。デジタルも『ashiato』はハイレゾ(48kHz/24bit)、『ashioto』はCD音質(44.1kHz/16bit)というのも最初はなんで統一しないんだろう? という疑問を持ったりもするのだが、まずはハイレゾの『ashiato』を聴いてみてほしい。それで何かがあなたの心に残るようなら、『ashioto』(LP以外に、Bandcampでデジタルデータも購入可)にチャレンジしてみていただきたい。新しい世界が広がるはず。

これは問題作だ。基本的にはヒップホップなのだが、名義はグレン・グールドである。グレン・グールドといえばバッハの「ゴルトベルク変奏曲」でデビュー、若くしてコンサートをドロップアウトして、以後録音のみで世間とコミットした一風変わったクラシック・ピアニストで、1982年に50歳という若さで亡くなるも、いまだにクラシックの世界のみならず、さまざまなアートの世界に影響を及ぼし続けているアーティストである。ある日、ハイレゾ配信サイトにどう見ても写真がグレン・グールド(ただし加工されている)で、実際クレジットもグレン・グールド名義なのだが、これまで見たことのないジャケットのアルバムが登場してきたのに気が付き、早速ダウンロードして聴いてみると(48kHz/24bit)、聞こえてきたのはヒップホップ・ビートだった……。“グレン・グールド”“Uninvited Guests”でググってみたが、日本語のサイトはヒットしない。日本は世界でも有数のグールドシンパが多い国なのに、変だな……と思い、彼のアルバムを発売している日本のレコード会社のサイトを覗いてみるも、情報なし。もっと調べてみたところ、現在グレン・グールドの音源の権利を管理するPrimary Waveという会社と、Billy Wildというディレクターが率いるDivision88というプロダクションが、グレン・グールドの88歳(!)の誕生日を記念して制作したアルバムであることが判明。Chief Awuah、Your Hunni、AARYS、Ro Joaquim、Gabriel Pick、Kiki Rowe、DOPE FA$Eというプロデューサーたちをフィーチャーして(残念なことに僕は彼らをひとりも知らなかったが)、グールドの音源からバッハやブラームスやモーツァルトの曲をサンプリングし、MCを乗せ、ヒップホップ・マナーのビート(当然だがそれはさほど激しいものではない)をミックスして作られたこのアルバムは、うがった見方をすればグールドが生きていた頃に試みた“4組のマイクロフォンをさまざまな位置に配置し、8トラックのマルチ・レコーダーで収録して、編集段階でミキシングを細かくコントロールし作品にふさわしい響きにする「アコースティック・オーケストレーション」”の一種の発展系と捉えることも可能かもしれない。また、2017年末にグールド生誕85周年企画として坂本龍一をキュレーターとして日本で開催された「グレン・グールド・ギャザリング」との共振も間違いなくあるだろう。ヒップホップとグレン・グールド……まずは一度耳を傾けてみる価値は十分にある。ちなみにアルバム・タイトルは、「In the future, the audience will become the artist...they will become the uninvited guests at the banquet of the arts.(将来、観客はアーティストになる…彼らは芸術の宴の招かれざる客になるだろう)」というグールド自身の発言によるものである。

キース・ジャレットは永遠だと思っていた。無論、実際にそんなはずはないのだけれど……。彼の作品はコンスタントに出ているし、ECMレーベルのハイレゾ・リイシューも最近はすごい勢いで行なわれるようになってきて、近年のアルバムはほぼフィジカルと同時に配信も行なわれているということもあり、なんとなくそんな気がしていたのだ。それだけにコロナ禍がふたたび猛威をふるい始めた2020年の秋、キース・ジャレットが「脳卒中による麻痺で、公演活動に復帰できる可能性が極めて低い」というニュースが流れた時はショックだった。たしかに彼は2018年に2度脳卒中を発症し、3月のカーネギーホール(ニューヨーク)公演と9月のヴェネツィア(イタリア)公演をキャンセルしている。実際にはその前年2017年2月のカーネギーホールでのソロ公演を最後に活動休止状態となっていたのだが……。加えて2020年9月にはスタンダーズ・トリオのゲイリー・ピーコックが亡くなるなど、ファンにとっては悲しいことが続いているが、それでも音源は我々の元に届けられるのである。ファンはそれを聴きながら密やかに彼の帰還を待ち望むしかないだろう。2019年11月に出た『Munich 2016』に続く最新作『ブダペスト・コンサート』は、そんなキースから届けられた美しい贈り物である。彼の現時点での最新のソロ・ツアーのうち、ヨーロッパ・ツアーは2016年7月3日のブダペストを皮切りに、同月16日のミュンヘンまで5回の公演が持たれた。先に出たのが最終日のミュンヘンの記録で、こちらは96kHz/24bit。今回出たブダペスト公演は48kHz/24bitと、若干のスペックの違いがあるが、この圧倒的に素晴らしい音楽の下ではたいした問題ではないだろう。家族のルーツがハンガリーにあるというキースにとってみると、ブダペストという場所での公演は特別の意味があったのだろうと推測できる。ミュンヘンとブダペスト公演は、日にち自体はあまり開いていないし、演奏時間も両者ほとんど同じであるが、ミュンヘンの音楽はより明るく響くのに対し、ブダペストでのそれはより深い響きが印象的。このアルバムを聴けるという幸せを噛みしめながら楽しみたい。
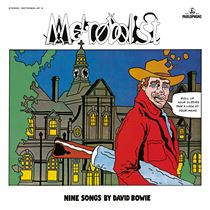
これはデヴィッド・ボウイの1970年代最初のアルバムであり、ミック・ロンソンとのコラボレーションの始まりとなったアルバムである……といえば、「それって『世界を売った男(The Man Who Sold The World)』では? 『Metrobolist』ってなんだ?」と言う人もいるだろう。それは正しい。が、この『Metrobolist』は、『The Man Who Sold The World』そのものなのだ。『The Man~』は、最初にアメリカのマーキュリー・レーベルで1970年11月に発売された(それ以外の地域では1971年4月)が、その時のアートワークはマイク・ウェラーによる漫画風のもの。背景にある建物はボウイの異母兄が入院していた病院であるらしい。『The Man~』のその後のアートワークは一般的に認知されている“ドレス姿で寝そべるボウイ”のものに差し変わるのだが、今回、その『The Man~』が発売から50年を迎えるということで、ジャケットがオリジナルふうに変えられて(オリジナルの吹き出しの中は空白だったが、今回は「袖を捲って腕を見せろ」というセリフが挿入されている)、リマスタリングを施されてのリイシューとなったのが本作だ。しかしこのタイトルは? と思われるだろう。筆者も知らなかったのだが、このアルバムのもともとのタイトルは『Metrobolist』というものだったらしく、マスターテープにもそのクレジットが残されているという(線で消されているようだが)。個人的にはやはりこのアルバムは『世界を売った男』のイメージが強いし、響きもそっちのほうがスタイリッシュだよなあとは思うけれど、まあそれはそれとして(笑)。肝心のサウンドのほうに注目してみよう。今回はこの50周年リイシューのためにオリジナル・プロデューサーのトニー・ヴィスコンティがオリジナルのマルチトラックからリミックスを施している。じつはさかのぼること5年前の2015年にも、このアルバムはトニー・ヴィスコンティによってリマスターされており、その際もハイレゾ配信(96kHz/24bitおよび192kHz/24bit。ちなみに2020年ヴァージョンは96kHz/24bitのみ)されていたので、聴き比べてみたところ、2020年マスターは圧倒的な音の実在感が際立つという感じを受けたことを報告しておこう。じつは1曲だけ、「After All」のみ前回の2015マスターが使われているが、これはヴィスコンティによって“このミックスは完璧”と認められた故だという。

コロナによる重苦しいムードの中、2020年という年が暮れようとしている。そんな時でもクリスマスはやってくるのだ。そう、せっかくだからクリスマスくらい楽しくやろうじゃないか。さあ、クリスマス・ソングを聴いてパーティだ! ……というそんな時期にちょうどリリースされたこのアルバムをさっそく聴いてみよう。1曲目はおなじみの「サイレント・ナイト」(きよしこの夜)だ。ピアノの美しい響きで「サーイレント・ナ~イト~ソーラソーミー♪」と聴き慣れた旋律が流れてくる。調性でいえばハ長調だ。ところが! 続く旋律は……「ラーミードーミーレシーラー」と、いきなりイ短調のマイナーキーになり、続く主旋律もまたマイナーキーの寂しげなメロディに変貌するのだ。思わずアルバム・タイトルを確認。“とても肌寒いクリスマス”??? 演奏しているのは……チリー・ゴンザレスか! カナダはモントリオール出身の作曲家であり、ピアニストであるチリー・ゴンザレス(本名:ジェイソン・ベック)はジャンル分け不可能な稀代のエンタテイナーとして活躍する天才音楽家。『ソロ・ピアノ』シリーズや、グラミー賞を受賞したダフト・パンクとのコラボレーション、iPadのテレビCMへの楽曲提供などで世界的に知られ、2018年にはその無限の魅力に迫るドキュメンタリー映画『黙ってピアノを弾いてくれ』も大いに話題となったことで知られる。そんなゴンザレスが作るクリスマス・アルバムだったら普通ではないことは当然だろう。ゴンザレス曰く「クリスマスは僕にとって熱烈な感情が交錯する時間だ。表面的な幸福に浮かれる時期ではあるけれど、自分を振り返り、一年に起こった悲しいできごとを悼む時間でもある。クリスマス・ソングを短調で奏でることは、クリスマスをより切実で現実に即したものに変えるんだ」とのこと。「サイレント・ナイト」をはじめ、「ジングル・ベル」など誰もが知っているクリスマス・ソングや、ワム!の「ラスト・クリスマス」、マライア・キャリー「恋人たちのクリスマス」といったポップ・ナンバーまで幅広く選曲され、ピアノの響きを中心に、ジャーヴィス・コッカー(パルプ / 2017年にはドイツ・グラモフォンから二人のデュオ・アルバムも出ている。ハイレゾあり)やファイストもゲスト・ヴォーカルで参加したこのアルバムを高音質なハイレゾ(48kHz/24bit)で聴きながら、この2020年という忘れられない1年を振り返るのは、悪くないクリスマスの過ごし方ではなかろうか。

 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。