注目タイトル Pick Up
“これはすごい…”演奏・録音ともに史上最高のニューイヤー・コンサート文/長谷川教通

2021年のニューイヤー・コンサートではホールに聴衆はいなかった。新型コロナウイルスのパンデミックが衰えを見せない中での開催であれば、全世界へのTV中継は無観客で行なうという判断はやむを得なかった。史上初のこと。テレビ中継はオーストリア国営放送が担当したようだが、日本での放送は地デジのEテレで、しかも5.1chのサラウンド音声だったので、思い切り音声データが圧縮されていても仕方ない。オーディオ・ファンにとっては物足りないだろう。一方、ハイレゾ音源の方はベルリンのテルデック・スタジオが受け持っている。当然ながら本番の演奏とともにゲネプロの音声も収録しているだろう。とはいえ、何しろ音源のリリースまでわずか1週間というハードスケジュールだ。データ・チェックとマスタリング作業で精一杯だろう。何か問題があれば手を加えることがあるにしても、おそらく一発録りだと思われる。そう期待して聴いてみる。これがすばらしいのだ。指揮は6回目のニューイヤーとなるリッカルド・ムーティ。ウィーン・フィルも気心の知れた仲とはいえ、お祝い気分とは異なる緊張感が漂っている。スッペの活気ある行進曲からスタートし、ヨハン・シュトラウス、ヨーゼフ・シュトラウス、さらにニューイヤー初登場のツェラーやミレッカーの作品も続く。弾けるような勢いがあって、それぞれのパートが極めて明瞭。ダイナミック・レンジにも不足はない。ムーティが指揮すると、ウィーン・フィルがこれほどまでに切れの良い演奏をするんだと驚いてしまう。後半に入って「バーデン娘」や「春の声」とプログラムが進むにつれて“これはすごい出来なんじゃないだろうか……”と確信する。「皇帝円舞曲」の堂々とした威厳のある響きとムーティならではのグーンと押し込んでくる迫力。指揮者の力量をまざまざと見せつけられた気がする。録音の良さも特筆もので、ライヴ録音とはいえ、ムジークフェライン・ザールでのセッション録音といってもいい好条件なのだ。非常に解像度が高く、金管楽器やシンバルが先鋭で、それでいてヴァイオリンの高音域にも無理にブーストしたような強調感はない。低弦も明瞭で量感があるのに明瞭度を失わない。打楽器群もくっきり。ムーティの要求に反応するオケの躍動が克明にとらえられている。演奏、録音とともに史上最高だ!

ナタリー・シュトゥッツマンを取り上げるとき、そもそも「コントラルトって何?」「アルトやメゾソプラノとの違いは?」などと疑問が出てくる。ちょっと整理しよう。“コントラルト”は“contra+alto”のことで、女声のアルトよりもさらに低い音域を指している。一方、男声がファルセット(裏声)で“テノール”よりも高い音域を受け持つ“カウンターテノール”もある。この両者の音域は重なっており、イギリスの聖歌隊ではソプラノパートをボーイソプラノ、アルトをカウンターテノールが受け持つことが多い。さて18世紀の初め頃には“カストラート”がもてはやされていて、これは男性を去勢することで声帯の成長を妨げて、いわゆる声変わりをなくしてボーイソプラノの声質と音域を維持させたもの。声帯は成長しなくても身体は成長するので、肺活量も胸郭も成人男性と変わらない。その結果、カストラートの声は野性的でありながらも美しく官能的だともてはやされた。現代ではカウンターテノールが歌うことが多いのだが、声質としては別物だ。ナタリー・シュトゥッツマンに言わせれば、当時の作曲家たちはカストラートとコントラルトを同等に考えていたと言う。ところが、優れたコントラルトはいたはずなのにカストラートの影に隠れてしまっていたのだ。現代最高のコントラルトと評されるシュトゥッツマンとしては何としてもコントラルトの魅力を伝え、18世紀の作品におけるコントラルトの復権を願って活動しているということなのだ。彼女は10年ほど前に古典楽器によるアンサンブル「オルフェオ55」を創設して、イタリアの古典歌曲やバロック期のオペラを取り上げ、女声の低音域の深々とした表現の魅力を伝えようと、みずから指揮もしながら歌っている。ピアノやヴァイオリンの弾き振りはよくあるけれど、歌手による“歌い振り”は少ない。オーディオ的に言うと、シュトゥッツマンのような女声の艶やかさを持ちながら幅があって深い響きを再生するのは、じつはとても難しい。太くすれば音像がぼけてしまうし、キリッと輪郭を立てると細身の声になってしまう。スピーカーの周波数で表すと600Hz~1kHzあたりの解像度が高いことと3kHz~8kHzあたりの倍音成分が素直に伸びていて、なおかつ聴いている位置でバランスがとれていることが不可欠。ぜひチェックしてほしい。思いのほかハードルが高いと気がつくに違いない。

このチェロは響きそのもので聴き手に訴えてくる。アニヤ・レヒナーは1961年ドイツのカッセル生まれの女流チェリストで、現代音楽のスペシャリストのように思われているが、音楽的なルーツはクラシックでハインリヒ・シフやヤーノシュ・シュタルケルにも師事している。1992年からはロザムンデ四重奏団のチェリストとして活動してきた。彼女の名がクローズアップされてきたのは、何と言っても2000年代に入ってECMレーベルで独自の感性を聴かせるアルバムをリリースしてからだろう。取り上げられる作品はウクライナのヴァレンティン・シルヴェストロフやアルメニアのティグラン・マンスリアン、エストニアのトヌ・コルヴィッツ……などの作品。現代音楽とは言っても、現在の都市空間や雑踏の中の人間性などをテーマにした実験的な作品とはまったく異なっており、シルヴェストロフの80歳を記念して制作されたアルバム『シルヴェストロフ:夜のヒエログリフ』では、彼が後期にたどり着いた望郷の世界がチェロの響きで静かに深く、瞑想するかのように描き出されている。「癒やされる」などと安易に言いたくはないが、何か心の奥底にある感情に共鳴するものがある。
レヒナーの追い求めるのものはクラシック音楽の枠にとどまることなく、他ジャンルのプレイヤーとのコラボにも意欲的だ。フランスのジャズ・ピアニスト、フランソワ・クチュリエと組んで2013年に録音された『グルジエフ、モンポウ、コミタス:モデラート・カンタービレ』は、アルメニアのコミタスやグルジエフ、カタルーニャのモンポウなど、ヨーロッパ音楽ではアウトサイダーといえる作曲家を取り上げ、そこから何という懐かしくて魅力的な音の世界を引き出していることだろうか。2019年の『Lontano』ではクチュリエのオリジナルあり、即興演奏あり、スローな響きから激しいアタックまで……その底流にあるのは“Lontano(遠くで、こだまのように、かすかに)”。心の深いところでこだまし、時を超え、場所を超えて人の心に響き合う音楽に国境はない、ジャンルもない。2016年の『シューベルト:夜』もぜひ聴いてほしい。シューベルトの作品をメインに、パブロ・マルケスのギターと演奏したアルバムだ。「夜と夢」「夜」とシューベルトの歌曲が穏やかで優しくて、懐かしくて、少し哀しげに響く。「辻音師」など、さりげない表現なのに深い情感が流れている。そう、シューベルトは余計な演出が見えたらいけないのだ。曲そのものに語らせないといけないのだ。言葉のないチェロがこれほど詩を奏でてくれるとは……。

北欧の名門「2L」と言えば、オーディオ・ファンには欠かすことのできないレーベルだ。ハイレゾが普及する以前から高音質録音へまっしぐら。つねに録音界のトップランナーのポジションを保ってきた。オーナーエンジニア、モートン・リンドベリの果敢なアプローチが録音界に与えた刺激は大きい。最近の「2L」録音はDXD352.8kHz/24bitで収録されており、このデータをベースに、現在リスナーが再生可能なあらゆるフォーマットで配信している。オリジナルの音源で聴きたいのはオーディオ・マニアの希望だろうが、とにかくデータ量が大きい。10分くらい録音したければ、ざっと1GBくらいは必要だ。一般ユースの再生機ではとても対応できないし、ネットでダウンロードするのも実用的とは言えない。そこでMQAエンコードの登場だ。MQAはイギリスのメリディアンで開発されたエンコード方式で、ハイレゾ音源なのにデータ量はCDと変わらない……という魔法のような話。デコーダーがMQAに対応していない場合でもCDと同等の44.1kHz/16bitで再生される。つまり基本のデータはCDなのだ。じつはCDフォーマットではノイズレベルとして使っていない領域があって、ここにハイレゾ音源ではこうなる! という情報を入れている。だからデータ圧縮とはまったく違う。最近ではMQA対応のプレーヤーやDAPもかなり発売されている。さすがに352.8kHz/384kHzまでカバーしている機器は少ないが、それでも172.4kHz/192kHzまで対応する機器となれば、ガクンとハードルは下がる。またDAPでも192kHzまでのMQAに対応するモデルは少なくない。Macを使っている人ならアプリの「Audirvana」を使えば96kHz/24bitまでならデコード可能だ。中華DACにこだわりがない人ならS.M.S.LやTOPPINGの384kHzまで対応のDACが使える。
さあ『2L-the MQA experience』の音質はどうなんだろうか。今回はiMac+S.M.S.LのM500、再生アプリはAudirvanaで聴いた。「違いますか?」という質問には「大違いです」と答えよう。ハイレゾに否定的な意見もあるのはよく知っている。「聴覚で感じ取れない20kHz以上が入っていても意味がない」とね。でも、それは周波数特性で考えるからで、音は空気の疎密波だということを忘れている。私たちは普段から周波数にもダイナミックレンジにも制限のない自然音の中で暮らしている。音楽もヴァイオリンもピアノもチェロも同様だ。微細に震える音の波を感じているのだ。この音の震えを耳に聴こえるはずがないからという理由で帯域制限したらどうなるか。微細な震えに変化が起きる。つまり音の波の形が変わってしまう。周波数特性上では可聴帯域外の情報をカットしただけのはずが、じつは肝心の可聴帯域の音波の形を変えてしまっているのだ。そのことを、このアルバムで確かめてほしい。ぜひわかってほしい。





江崎昌子の弾くショパンはポーランド的なのだろうか? グローバルな時代にそんな愚問を……などと言われるかもしれないが、江崎昌子を聴いていると、ふっとそんな気がしてくる。彼女は桐朋学園を卒業後ポーランドに渡り、ワルシャワのショパン・アカデミー研究科に学び、バルバラ・ヘッセ=ブコフスカやタチアナ・シェバノワ、セルゲイ・エデルマンなどショパンの名手たちから薫陶を受けて、数々の国際ピアノ・コンクールでも優勝している。そしてポーランドで家庭を持ち、演奏活動も続けてきた。2010年にはポーランド政府から外国人に贈られる文化勲章を受けるなど、とても評価は高い。日本では洗足学園音楽大学の准教授、日本ショパン協会理事を務める。録音も多く、ハイレゾ音源ではマズルカ全集、エチュード全集、ワルツ全集……と「TRITON」レーベルから次々とリリースされている。でも日本での評価はどうなんだろう? と気になる。もっと聴かれていいピアニストだと思うからだ。まずは日本人にとって難しいと言われるマズルカ。いやー、面白い。独特のリズム、巧みにテンポを揺らす。音を引っかけたり、ずらしたり……。これほど思い切った間の取り方ができるのはすごい。それでいてすべての音に気を配り、ていねいに弾いていく。「そう、この呼吸がマズルカの神髄なのよ」と言っているかのようだ。このマズルカをポーランドの家族に聴かせたら、ニコニコしながら「それでいいんだよ、それが君のマズルカなんだよ」と頷いてくれるんじゃないだろうか。さらに「ワルツ」も難しい。これもいい。テンポを上げても音楽が流れてしまうことがない。とくに和音を十分意識して鳴らしていることがよくわかる。これだけ細部の音を大切にできるのは、いかにも日本人なのかなーと感心してしまう。「バラード」も「ノクターン」もすべて聴いてみたくなる。期待を裏切ることはないだろう。少しボリュームを上げてみてほしい。録音の良さもあって、とてもダイナミックでピアノ全体の鳴りも十分。「江崎昌子のショパンはきれいなんだけれど、ショパンはもっと強靱でなきゃ」なんていう声などどこかへ吹き飛んでしまう。そんな彼女が、うれしいことに「ブルグミュラーの練習曲」を弾いてくれた。「ないしょ話」から始まって、ピアノを習った人なら誰もが聴いたことのある曲たちが、生き生きと演奏されている。タッチの強弱、音色の変化、ペダルの効果……など、これほど表情豊かに弾けるんだと新鮮な気分にさせられるに違いない。
欧州ジャズの橋頭堡、インタクト・レーベルのカタログ約100枚がハイレゾに文/國枝志郎


スイスはチューリヒで活動するジャズ・レーベル、インタクト・レコードの諸作がかなりの枚数ハイレゾで出ているということに今頃気づいた。ロンドンのジャズ・シーンで精力的な活動を続けるピアニスト、アレクサンダー・ホーキンスが、同じくロンドンを拠点にジャンルを問わないフレキシブルな音楽を取り上げる気鋭のグループ、ライオット・アンサンブルおよびブリストル出身のフリー・ジャズ・サクソフォン奏者エヴァン・パーカーをフィーチャーしたアルバム『Togetherness Music』、そしてベルリン在住でヨーロッパを中心に即興音楽活動を続けるピアニスト / 作曲家である高瀬アキにクリスチャン・ウェーバー(b)、ミヒャエル・グリーナー(ds)を加えたトリオ、Augeによるセルフ・タイトル・アルバム『Auge』という2枚のアルバムがハイレゾ(前者は96kHz/24bit、後者は44.1kHz/24bit)で小正月(1月15日)に配信リリースとなったのに気がつき、む? と思って調べたらこのインタクト・レコードのカタログが100枚近くハイレゾ配信されていたことがわかった次第。小豆粥を食べながらチェックしましたよ、ええ。1986年にスイスのジャズ・ピアニスト、イレーネ・シュヴァイツァーのライヴ・アルバム『Live at TAKTLOS』(タクトロスは1984年にチューリヒ、ベルン、バーゼルというスイスの3州において立ち上げられたジャズ・フェスティヴァルの名称)を最初のリリースとして始まったこのレーベルは、タクトロス・フェスを立ち上げたパトリック・ランドルトによってスタート。現在までに400枚近いアルバムをリリースしており、フリー・ジャズやインプロヴィゼーションをメインとした欧州ジャズのひとつの橋頭堡とも言えるレーベルである。イレーネ・シュヴァイツァーやロンドン・ジャズ・コンポーザーズ・オーケストラのバリー・ガイ、ベルリン・コンテンポラリー・オーケストラのアレクサンダー・フォン・シュリッペンバッハやサックスのイングリッド・ラウブロックなどが同レーベルから多くのアルバムをリリースしているが、ハイレゾ配信は2013年以降の作品に限られているとはいえ、上記アーティストやフレッド・フリス、エリオット・シャープ、ドン・バイロン、ジョーイ・バロンといった大御所のアルバムもある。これはステイ・ホームでゆっくり楽しみたい。

2020年のコロナ禍は音楽界にも大きな影響をもたらしたわけだが、表現者のアウトプットにおいてはむしろ以前より熱量が上がってきているように感じられる。目の前の大勢のオーディエンスに向かって叫ぶことはできないけれど、スタジオでの孤独な作業を経て生み出される作品は聴き手の心を揺さぶる素晴らしいものばかりと思えた2020年だった。その2020年のクリスマスはそう、恋人たちも街に繰り出せなかった前代未聞のクリスマスだったわけだが、そんな日に配信のみ(ハイレゾは48kHz/24bit)で曽我部恵一のソロ・アルバムがリリースされた(その後、CDとLPの発売も決定)。じつに80分以上に及ぶ大作である。CDなら間違いなく2枚組というヴォリューム。アルバム・タイトルは『Loveless Love』。愛なき愛、か……。間にサニーデイ・サービスとしての活動やライヴ・アルバム、シングルの発売などを挟みつつ、2018年の『ヘブン』『There is no place like Tokyo today!』以来2年ぶりとなるソロ名義でのアルバムには、曽我部恵一という稀有な表現者が今、おのれの持つ想像力をフルに絞り出したような気迫が込められている。そこには統一感よりもむしろ、混乱とも言えるヴァリエーションの豊かさがある。2020年5月にシングル・リリースされたじつに15分近くある長尺フォーク・ナンバー「Sometime In Tokyo City」、同年8月にリリースされたこれも10分近い流麗なハウス・チューン「永久ミント機関」、かつてサニーデイ・サービスが発表した「FUCK YOU音頭」の続編とも取れる「戦争反対音頭」(どちらの曲も、広島のジューク / フットワークDJでありトラックメーカーCRZKNYによる最高のリミックスも制作されている)というてんでんバラバラなシングル・ナンバーがすべて収録されているということもそうだが、他のナンバーもダウンテンポ、サイケデリック・ファンク、ダブ、ローファイ……音楽性はとにかく多岐に渡る。というか、あえてアルバムとしての音楽的な統一感は出さない方向で作られたのかも、とも。そんなトラックたちに乗せて紡ぎ出される曽我部の“ことば”はとにかくクールだ。が、しかし……それは今、自分たちが置かれている状況を冷静に観察したゆえのものなのだろう。インスタントな救済など薬にしたくもない。だが、ここで聴ける曽我部の音楽のクールさは聴き手を拒否するものではない。“愛なき愛”というこのアルバムが、かつては街中に“愛”が溢れていた(ように思えた)クリスマスにリリースされたことには最初アイロニーめいたものを感じなかったといえば嘘になるが、すべてを聴き終えてみると、ここにあるのは絶望ではない、ただほんの少しだが、それは希望なのだということがよくわかる。

曽我部恵一のアルバムに続き、このアルバムもヴォリュームたっぷり。じつに108分、全28曲という大作だ。SAKA-SAMA(サカサマ)は、いわゆるアンダーグラウンドなアイドルというジャンルに属するグループ。アイドルで2枚組のアルバムを出すというのはやはりレアケースだろう。こうしたアイドルのおもなCDの販売場所はライヴ会場であることが多いので、値段が上がる2枚組は敬遠されることが多いし、ましてこのコロナ禍で思うようにライヴができない日々が続くとなおさらフィジカルな製品を作ることを躊躇うことも多いだろうと思う。しかしSAKA-SAMAはむしろ2020年にものすごく攻めたイメージがある。ライヴも(もちろん細心の注意を払ったうえで)果敢に行ないつつ、リリースも8月にアルバム『Daydream』を、そして同じ8月から3ヵ月連続シングル・リリースを敢行し(ちなみにその第1弾となったシングルは「ダンスを止めるな」というタイトルだった)、一方でメンバーの寿々木ここねは同じく8月にソロ・アルバム『FEVER』、朝倉みずほもソロ・ユニットATOMIC MINISTRY名義のソロ・シングル「BIG LOVE」を11月にリリースするなど、その運動量はすごかった。しかも会場限定で販売された『Daydream』以外はハイレゾでの配信もしっかり行なわれたのも嬉しいところだったので、素晴らしい出来栄えであった『Daydream』のハイレゾ配信を心待ちにしていたのだが、なんとその期待を200%上回るリリースが今回の大ボリュームのアルバム『君が一番かっこいいじゃん』である。待望の『Daydream』全曲も収録されているが、曲順が大幅に変えられ、再録音もされているうえにハイレゾ(96kHz/24bit)なのでその聴こえ方もまったく新しい。このアルバムも曽我部恵一のアルバム同様、音楽性はドラムンベースあり、テクノあり、ミディアムなロックあり、ドリーム・ポップあり、ローファイあり(もともと2016年に結成された時、SAKA-SAMAは“Lo-Fiドリームポップ・アイドル”を名乗っていたのである)ときわめて幅広い。そのうえ制作陣はバラバラだが、どの曲もメンバーの寿々木ここねと朝倉みずほののほほんとしたキャラクターをうまく掴んだものとなっていて、とにかくふたりの日本語がしっかり聴き取れることがアルバムの印象をとても明快なものにしていて泣くほど素敵だ。同じレーベル所属のヘヴィ・ロック・バンドBorisの演奏で収められた知る人ぞ知るニューウェイヴ・バンドD-DAYのカヴァー「Heavenly Blue」や、ウルトラセブンのエピソードを思わせるカメラ=万年筆の佐藤優介による「ひとりぼっちの地球人」など、あちこちに意外な仕掛けもあって飽きさせない。

先日、大塚のライヴハウスから無観客配信された地下アイドル出演の「オンラインYOIMACHI」を見ていたら、アイドルたちに交じってヒカシューが出ていたので思わず画面を凝視してしまった。ヒカシューは以前にもゆるめるモ!や・・・・・・・・・(通称ドッツトーキョー)との対バンも行なっているので、アイドルと共演してもなんら不思議ではないわけだが(ちなみにそのライヴのヒカシューの前には・・・・・・・・・から発展したアイドルユニットRAYが登場したことも胸熱案件だった)、ちょうど2020年末に3年ぶりのオリジナル・アルバム『なりやまず』をリリースした直後ということもあって、これはヒカシューを知らないアイドルファンにもアピールするいい機会になったのではないだろうか。かわいい女の子がステージにいるわけではなく、得体の知れないオッサンたちが得体の知れない楽器に手かざしして(まあテルミンですけど)いつ終わるのかわからないような不思議なうねりを持った曲を延々(と言っても持ち時間は35分)演奏しているのだから痛快とも言える(笑)。さて、この新作『なりやまず』は、結成41周年目に入った巻上公一率いるヒカシューによるじつに24枚目のオリジナル・アルバムである。2020年3月、ヒカシューはツアーのためエストニアを訪れていたが、1公演を終えたところでコロナ禍によって残る公演がキャンセルになったために急遽現地でスタジオ入りして4曲を録音。日本に戻ってからさらに3曲を録音してできたのが本作。ちなみにジャケット写真は、観光客のいなくなったエストニアの首都タリン旧市街で撮影したものだという。いつものヒカシューのジャケットはペーソスあふれるものだが、今回のジャケットはコロナ禍という切迫した事態のなかにいるというムードをそこはかとなく漂わせ、これまでにない切迫感のようなものも感じさせる。全体的に長尺のナンバーが多いのは、これらの曲がある種の即興によって作られていることを示唆しているのだろう。ここのところヒカシューと関係の深いハイレゾ・マスター、オノ セイゲンのマスタリングにより、今回は初めてDSD11.2の超弩級ハイレゾデータも用意された(他にDSD5.6とPCM96kHz/24bitも)。音楽はいつまでも鳴り止まない。
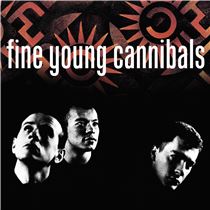
1980年代から90年代にかけて活躍したイギリスはバーミンガム出身の3人組、ファイン・ヤング・カニバルズのファースト・アルバム(オリジナルは1985年発売)が、リリースから35周年を迎えた2020年末、2枚組のデラックス・エディションCD発売と同時にハイレゾ(44.1kHz/24bit)で配信スタート。ファイン・ヤング・カニバルズと言えば、1989年にリリースされ、アメリカとイギリスでチャートの1位を獲得したセカンド・アルバム『The Raw & the Cooked』のほうが有名だと思うが(アルバム収録の「She Drives Me Crazy」と「Good Thing」の2曲が全米シングルチャートの1位を獲得した)、しかしそもそもこのファースト・アルバム(チャート・アクションはイギリス11位、アメリカ49位)収録の「Johnny Come Home」と「Suspicious Minds」(後者はエルヴィス・プレスリーのカヴァーで、ブロンスキ・ビートのジミー・ソマーヴィルがヴォーカルを取る)がヨーロッパを中心にヒットしたからこその成功であったことは間違いない。元ザ・ビートのアンディ・コックス(b)とデヴィッド・スティール(g)に、ローランド・ギフト(vo)を加えたこのトリオは、結局2枚のオリジナル・アルバムを残して解散してしまったが、今聴くと荒削りながら85年あたりのUKのポップ・ミュージック・シーンの空気をよく感じさせてむしろセカンドよりも時代に淘汰されていない感じがする。マンチェスターのファクトリー・レコードからデビューしていたア・サートゥン・レイシオを思わせるようなコールド・ファンク・スタイルをベースに、ローランド・ギフトのソウルフルでメジャー感満載のヴォーカルが成功の秘訣だったのだろう。セカンドよりもシャープなギターが活躍するこのファーストは、よりハイレゾ化の恩恵を受けているように感じる。なぜかCDヴァージョンよりも2曲少ないのだが、シングルのロング・ヴァージョンや、『John Peel BBC Session』『Janice Long BBC Session』といった当時のUK音楽番組でのライヴなどを含む全37曲(オリジナルは10曲)を収録。

 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。