注目タイトル Pick Up
還暦記念の新作は、ジャズから出発し近年はクラシックに挑む小曽根真の集大成文/國枝志郎

ジャズ・ピアニスト、小曽根真の還暦(!)記念ソロ・ピアノ・アルバムは音楽も音そのものもエクセレントの極みだ。ジャズから出発した小曽根は近年、積極的にクラシックのジャンルにも挑み、幅広い活動を繰り広げているのは周知のことだけれど、60歳というひとつの区切りの時期にリリースされたアルバムはCDでは2枚組で、1枚目にラヴェルやモーツァルト、プロコフィエフなどのクラシック作品を、2枚目には小曽根作曲によるジャズのオリジナル曲が収録された、小曽根真の集大成ともいうべきものとなっている。このアルバムにおいて当コラム的に注目したいのは、この録音がスタジオではなく、クラシックで使われるコンサートホールで行なわれたということだ。ジャズでもライヴ・アルバムならコンサートホールでの録音も珍しくないものの、セッション・レコーディングでのジャズは案外珍しい。会場として選ばれたのは茨城県の水戸芸術館コンサートホールATM。600席ほどの中規模なホールで、その響きの素晴らしさについては小澤征爾指揮する水戸室内管弦楽団のモーツァルトの交響曲シリーズと、同じシリーズ内で演奏された児玉桃によるモーツァルトのピアノ協奏曲(いずれもライヴ)、小菅優によるベートーヴェンのピアノ・ソナタ全集(セッション)などのアルバムで承知済みだ。小曽根は録音に際し、スタインウェイ(D型)とヤマハ(CFX)の2台のピアノを弾きわけているそうだが、スタインウェイは水戸芸術館の備品かなと思ったら、小曽根の自宅にあるスタインウェイをわざわざこの録音のために持ち込んだというから、彼のこの録音にかける意気込みもわかろうというものだ。2種の楽器の使い分けについては「スタインウェイでクラシック、ヤマハでジャズ」ということなのかなと思ったりもしたのだが、冒頭のラヴェルの「ピアノ協奏曲」からしてヤマハで演奏されているというし、また多重録音を行なっているパートすらあるというから話はやはりそう単純なものではなく、あくまでも曲に対する小曽根のイメージを具現化してくれる響きを優先したということなのだろう。レコーディング・エンジニアはベテラン、櫻井卓。96kHz/24bitのハイレゾ・サウンドはピアノという楽器を知り尽くし、ホールの響きそのものを完全に捉えようとする演奏家と録音家の理想を余すところなく伝えてくれる。前半のクラシック(特に小曽根が好んでいるというプロコフィエフの「戦争ソナタ」が素晴らしい)もいいが、ホールトーンをたっぷり聴かせてくれる後半のジャズがまた、豊穣の極み。幸せな響きに浸れる今月のハイレゾNo.1。
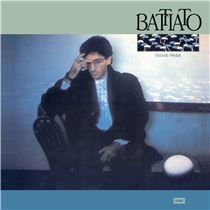
1970年代から活動を続けるイタリアのミュージシャン、フランコ・バッティアートは、2019年にオーケストラと共演したアルバム『Torneremo Ancora』をRCAからリリースしたのと時を同じくして引退を表明した。このアルバムのハイレゾ配信は残念ながら今のところ実現していないけれど、同じ頃に『L'Era Del Cinghiale Bianco(白イノシシの時代)』の発売40周年記念リマスター・アルバムのハイレゾ(96kHz/24bit)が配信されたことは間違いなくエポックメイキングな出来事だった。そしてその翌年の2020年末には、ボックス・セットとして2015年にリリースされたリマスター / リミックス・ベスト+新曲による52曲収録のアルバム『Anthology - Le Nostre Anime』、および2012年の作品『Apriti Sesamo』、加えて1980年発売の『Patriots』の40周年記念盤の配信(いずれも44.1kHz/24bit)も実現した。これらは旧EMIの音源の権利を持つユニバーサルミュージックからのリリースで、ということは遠からずEMI時代(80年代から90年代前半)のアルバム音源のハイレゾリリースもあるのでは……と踏んでいたらやはり来ました。バッティアートの活動は、前衛音楽的でプログレッシヴな作風を持った70年代(ドイツの前衛作曲家、カールハインツ・シュトックハウゼンに捧げられた4作目のアルバム『Clic』は早すぎたコラージュ・ミニマルの名盤だと思う)、レーベルをEMI(当時)に移してポップな作風に転じた80年代、映画音楽やオーケストラものを経てロックに接近した90年代と、その音楽性をかなり大胆に変化させてきたが、彼の「イタリアの歌い手」としての魅力はやはりEMI時代のアルバムにこそ大きく感じられると思うので、ハイレゾで初めてバッティアートの芸術に触れるにはうってつけじゃないだろうか。この春には13枚のアルバムが配信開始となったが、どれか1枚というのであればイタリアン・ポップとエレポップが絶妙にブレンドされた『Orizzonti Perduti(失われた地平線)』(96kHz/24bit)を推薦しておこう。可能であればぜひその物語性に満ちたイタリア語の歌詞の意味を汲み取りながら聴いてもらいたい。それとさらにもう1枚というのであれば、70年代の前衛性をさらに洗練させたアルバム『Joe Patti's Experimental Group』(Pino Pioschetolaとの共作/44.1kHz/24bit)もお勧めだ。

ロンドン・パンクのひとつの象徴とも言えるアーティスト、ジョー・ストラマーが亡くなったのが2002年だから、まもなく20年という年月が経とうとしている。ジョーといえばやはりクラッシュがまずは思い起こされるわけだが、クラッシュについては比較的早い時期にハイレゾ配信が実現していた。他のパンク勢に比べるとこれはかなり優遇されていると言ってもいいと思うけれど、残念ながらクラッシュ解散後のメンバーのソロ活動についてはほとんどハイレゾでは顧みられない状況が長く続いている。ミック・ジョーンズのBig Audio Dynamiteもまだハイレゾは配信されていないし、ジョー・ストラマーのソロやメスカレロス名義のアルバムのハイレゾ化もまだ全然実現していないのだ(ベーシスト、ポール・クックがブラーのデーモン・アルバーンらと組んだThe Good, The Bad and The Queenについてはハイレゾがあるがまあこれはちょっと番外か)。そんな中、ジョー・ストラマーのベスト・アルバムがジョージ・ハリスンの立ち上げたレーベル、ダークホースからリリースとなったのだが、うれしいことにCD、LPに加え、ハイレゾ(44.1kHz/24bit)での配信も実現。このアルバムはジョーのソロ、ジョー・ストラマー&ザ・メスカレロスとのアルバム、クラッシュ解散後の不遇の時期に製作したアレックス・コックス監督による映画『シド・アンド・ナンシー』のサウンドトラックからのトラックに、3曲の未発表音源(クラッシュでも取り上げていた「アイ・フォート・ザ・ロウ」「しくじるなよ、ルーディ(Rudie Can’t Fail)」のメスカレロスとのライヴ音源と、同じくクラッシュのアルバム『サンディニスタ』に収録されていた「ジャンコ・パートナー」のアコースティック・ホーム・レコーディング・ヴァージョン)が収められているのはファンにとってはうれしいことだろう。しかしこのアルバムの価値はそれだけでない。ジョー・ストラマーという音楽家が辿ってきた音楽的逍遙が、こうしてソロ・キャリアをまとめたベストを聴くことによって俯瞰できるのである。この幅広い音楽性こそ、今改めて聴くジョー・ストラマーのすごさと言えるのではないだろうか。ジョーのソロのハイレゾ化にも期待したいところだ。
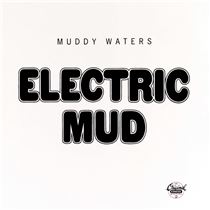
シカゴ・ブルースの父と言われるアメリカのブルース・シンガー、マディ・ウォーターズのハイレゾは、これまでセカンド・アルバムの『Folk Singer』(1964年)と、1977年のモントリオールでのライヴ・アルバム『Hoochie Coochie Man:Live at The Rising Sun Celebrity Jazz Club』、そしてボ・ディドリーとハウリン・ウルフとのセッションを収めた『The Super Super Blues Band』がリリースされていた。これがまたスペックがバラバラで、『Hoochie Coochie Man~』はリリースがちょっと前だったこと(2016年)もあるのか、44.1kHz/24bitだったけれども、『Folk Singer』は192kHz/24bitに加え、なんとDSD2.8というハイスペックデータもあってハイレゾ・マニアをあっと言わせたし、『The Super Super Blues Band』は96kHz/24bitでこの緊張感あふれるセッションのムードをリアルに伝えてくれるサウンドとなっていた。さて、それらのアルバムに続いてハイレゾ化されたのは……シカゴ・ブルースの文脈で言えばかなり異端とも言える4作目のスタジオ・アルバム『Electric Mud』(スペックは96kHz/24bit)だったのにはちょっと驚かされたというのが正直な思いでもある。なんせこのアルバム、マディ・ウォーターズのそれまでの音楽とは異なり、ジミ・ヘンドリックスやスライ&ファミリー・ストーンばりのファンク色の強いサイケデリック・ロックをやっているうえに、ギタリストでもあったマディがなんとギターを弾いていないアルバムなのだから……。ギターを弾いているのは当時チェス・レーベルのセッション・ギタリストだったピート・コージー(このアルバムの後、1973年にはご存知のようにマイルス・デイヴィスのバンドに加入することになる)やフィル・アップチャーチ、ローランド・フォークナー。当然のようにブルース・ファンを驚かせたこのアルバムは賛否両論となったが、その後のロック・シーンやヒップホップ・シーン(パブリック・エナミーのチャックDは本作に衝撃を受けたと語っている)にも大きな影響を与えた1枚として重要な作品であることもまた確かである。文字のみのシンプルなジャケットも印象的。

このアルバムは2021年春公開のSFミステリー映画『Doors』(ドゥガン・オニール監督)のサウンドトラックだが、その音楽を担当するジョン・ベルトランという名前を見てピンと来る人は年季の入ったテクノ・リスナーだろう。ジョン・ベルトランはデトロイト出身で1990年代前半から活動を続けるエレクトロニック・アーティストである。デトロイト・テクノではデリック・メイ、ホアン・アトキンス、ケヴィン・サンダーソンという3人のオリジネイターが有名だが、ジョン・ベルトランはカール・クレイグと並ぶデトロイト・テクノ第二世代としてオリジネイターが作り上げたエモーショナルな電子音楽の領域をさらに拡張し、現在に至るまで旺盛な創作活動を繰り広げている貴重な存在だ。ジョン・ベルトランの初期のリリースは、カール・クレイグが主宰していたRetroactiveというレーベルがベルギーのBuzzと共同で制作したエモーショナル・テクノの名コンピレーション・アルバム『Equinox / The Beginning / Nite & Da』(1993年)に収録されたPlacid Angles名義での「Aquatic」という美しいジャズ風のナンバーだった。カール・クレイグにせよジョン・ベルトランにせよ、デトロイト・テクノの第二世代はジャズやアンビエント、クラシック音楽などの要素をうまくその音楽に取り込み、音楽性の幅を広げることに成功しており、その音楽は映画のサウンドトラックにも絶対フィットすると思っていたが、このジョン・ベルトランによるスペイシーなSF映画のサウンドトラックは想像以上に素晴らしい出来栄えだ。残念ながらこの映画は僕が知るかぎり日本公開未定であり、僕も映画そのものは未見なので、この美しい電子音楽が映画のシーンの中でどのようなムードを生み出しているのかは想像するしかないのだけれど、シンセサイザーの深い響き、ときおり爪弾かれるピアノ、控えめだがけっして埋もれてしまうことのない柔らかなビートは、これまでジョン・ベルトランが作り出してきたオーガニックなエレクトロニック・ミュージックとシームレスに繋がっている。ジョン・ベルトランの作品としてはこれが初めてのハイレゾ(44.1kHz/24bit)になるのだが、この音楽はハイレゾという空間があってよりその真価を発揮するものであることは間違いないだろう。
外面的な効果より物語性を。ストラヴィンスキーの自作自演をモノラルで聴く文/長谷川教通
ストラヴィンスキーといえば、作曲家としてだけでなく、指揮者やピアニストとして活躍したことでも知られるが、とくに自作自演の録音は膨大だ。20世紀初頭の音楽界に激震を与えた名作を作曲家自身がどう指揮していたのか。音楽ファンなら興味があるのは当然だろう。それぞれの初演は「火の鳥」が1910年、「ペトルーシュカ」が1911年。そしてピエール・モントゥの指揮で行われた1913年シャンゼリゼ劇場の「春の祭典」初演では、嘲笑と怒号が飛び交ったという話は有名だ。とはいえ「春の祭典」も、その後20世紀を代表する作品とまで評価されることになる。1913年と言えばストラヴィンスキーはまだ30歳。こんな凄い作品を生み出した才能とエネルギー……まさに天才。
ストラヴィンスキーの3大バレエ音楽は1960、61年にコロンビア響を指揮したステレオ録音がよく知られているが、ここで紹介するのは1940年代にニューヨーク・フィルを指揮したモノラル録音。録音の良さではステレオ音源をとりたくなるものの、モノラル音源には原始主義と言われる初期の作品らしいエネルギー感や覇気があり、しかもニューヨーク・フィルによる名人芸が随所に聴かれて愉しい。指揮者ストラヴィンスキーの視点で作曲家ストラヴィンスキーの作品の魅力を引き出そうとした解釈が聴ける。現代の指揮者なら、よりリズムをダイナミックに、あるいは響きを洗練させたり、さらに鮮烈で色彩的だったりしたくなるかもしれない。ストラヴィンスキーの指揮では木管の表情が饒舌で、まるで木管にストーリーを語らせているような気がする。彼は外面的な効果よりも、作品のベースにある物語性をしっかりと描き出そうとしていたのだ。そこが面白い! 音源は44.1kHz/24bitだが、デジタルリマスターによってノイズが抑えられ、約80年前の録音としてはかなり聴きやすい。
今回の試聴では、メインで使っている高解像度&広帯域の2chシステムに加え、モノラル音源専用の1chシステムも使った。「モノラル録音はモノラルで聴く」という狙いだ。2ch→1ch用のラインケーブルは、LとRのプラス側にそれぞれ5.1kΩの抵抗を入れた上で合成するように加工し、モノラルの真空管プリメイン・アンプに接続。もちろんスピーカーもモノラルだ。2chではスピーカーの中央にできる虚像を聴くことになるが、響きが整理され洗練された印象にはなる。ところがモノラルシステムでは、オケの響きが一体となった実像感が生々しくて、音が聴き手にグッと迫ってくるではないか。この熱気がモノラルの醍醐味。80年前にタイムスリップだ。マニアックな話で恐縮だが、モノラルもいいもんだ!

ベルリン・フィルの首席オーボエ奏者、アルブレヒト・マイヤーによるモーツァルト作品集。こう言うとオーソドックスなプログラムをイメージするが、これがちょっと一捻りあるから面白い。まずはオーボエ協奏曲K.293。「えっ」と思う人もいるだろう。そう、K.314ではなく、K.293。モーツァルトが1778頃に作曲したと言われる未完の作品だ。そしてイングリッシュ・ホルンに編曲された「アヴェ・ヴェルム・コルプス」。マイヤーは指揮も兼ねて、指揮台の上で弦楽オケに向かって演奏する。穏やかで深々としたとっても良い演奏だ。長いフレーズをノンブレスで吹いている。映像も公開されているのでぜひ観てほしい。続いて「フルートとハープのための協奏曲」をオーボエとチェンバロ・ソロに編曲した版で演奏する。原曲の華やかさとは違って、オーボエの音色がキューッと聴き手の胸に迫ってくる。第2楽章のオーボエとチェンバロの掛け合いが絶品。後半はオーボエやオーボエ・ダモーレに編曲されたロンドやモテットが続くが、聴きものは「エクスルターテ・ユビラーテ」だ。オケをバックにソプラノのソロ・パートをオーボエ・ダモーレが吹き、これにオルガンが加わる。クライマックスの「アレルヤ」ではソプラノの華麗さにも劣らない鮮やかな演奏。巧いなー、ほんとに巧い。それにしてもモーツァルトの音楽って、編曲しても曲の生き生きとした魅力はまったく変わらないし、むしろ楽器によっては新たな発見もあって、やっぱり希有の才能なんだと思わせられる。録音は2020年7月6~9日、ドイツ北部のブレーメン州テディングハウゼン近郊のルンセンにあるSt. Damian und Cosmas Kircheで行なわれた。田園の景色が広がる中に赤煉瓦が美しく生えるネオゴシック様式の教会だ。オーボエの音色を中心に小編成のオケが明瞭な音像で録られている。空間情報も自然で、とても透明感のある音場が描かれている。

これはいい! アリアドネ・ダスカラキスがBISレーベルへ録音したシューベルトのヴァイオリン作品集。奏法はピリオドなのだが、とにかく音色がすばらしい。まさにリッチ・トーン。おそらく楽器のセットアップはモダン仕様だろう。協演は室内オケのケルン・アカデミーとピアノ・フォルテのパオロ・ジャコメッティ。シューベルトならではのシンプルな旋律がノンヴィブラートで紡がれていく。一つの音が次の音を予感させ、まだその次の音へとつながっていく。この歌わせ方がとても優しくて味わいがある。ヴィブラートをかけずに弧を描くようになめらかでニュアンス豊かに、しかも正確な音程で奏でるのは、ごまかしがきかないのでほんとに難しい。それなのにさりげなくてすがすがしい。
ところで「アドリアネ・ダスカラキスって、誰?」という音楽ファンは多いのではないだろうか。日本語の情報はとても少ないから、それも無理ないなー。彼女はアメリカ・ボストン生まれのヴァイオリニスト。名前からもわかるようにギリシャ系だ。ウェブサイトによれば、生年は「初の月面着陸」と「スター・ウォーズ」公開の間となっている。こういう機知に富んだ表現は素敵だ。おそらく50歳前後だろう。技術的にも音楽表現においても絶頂期にあると言えそうだ。これまでのディスコグラフィを見ると、バロック時代の作品に加えて、カリヴォダやラフ、リースといったベートーヴェンの次代を引き継ぐ作曲家たち、さらにはルトスワフスキーやシマノフスキーまでも取り上げていて、けっして派手なヴァイオリニストではないが、バロックからモダンまでの表現に対応できるスペシャリストであることがわかる。しかも音楽史の影に隠れた作品に光を当てようとしたり、現代の作曲家とのコラボにも意欲的。室内楽に熱心なほか、リーダーとして室内楽団を率いたり、後進の指導に当たったり、国際コンクールの審査員を務めたり……こんな実力者が音楽界を支えているんだなーと思う。


どうして北欧から歴史上に名を残すワーグナー・ソプラノが出現するのだろうか。1950年代のキルステン・フラグスタート(ノルウェー)、その後継者とも言われたビルギット・ニルソン(スウェーデン)は1960~70年代、そしていま注目されるのが若手のリーゼ・ダヴィドセン(ノルウェー)。1987年生まれだから、まだ30代前半だ。2019年のゲルギエフ指揮する「タンホイザー」のエリーザベトでバイロイト・デビュー。このときはゲルギエフのバイロイト・デビューでもあったから、注目が指揮の方に集まったようだが、公演後の話題はダヴィドセンに集中し、数十年に一度の逸材と評価するメディアもあったとか。それはそうだろう。この声を聴いたらしびれるよ。DECCAレーベルのデビュー・アルバム(2018年収録)では、エサ=ペッカ・サロネン指揮するフィルハーモニア管とワーグナー「タンホイザー」からの2曲とR.シュトラウスを組み合わせたプログラム。そういえばビルギット・ニルソンもR.シュトラウスを得意にしていたっけ。とにかく声が強いというか、圧倒的なパフォーマンス。まさにドラマティック・ソプラノなのだが、高音域にかけてビリビリするような倍音ののった声が伸びてくる。そしてセカンド・アルバムでは、ワーグナーの「ヴェーゼンドンク歌曲集」に加え、ベートーヴェンやヴェルディなど彼女にとって最高のパフォーマンスを示すことになるはずの役柄がずらりと並んでいる。「フィデリオ」のレオノーレでは強靱な意志力とピーンと張った緊張感が凄いし、マスカーニ「ママの知るとおり」では繊細な声のコントロールでサントゥッツァの心情……弱々しく泣いているだけではない。心の揺らぎや秘めた強さをも表現する。「オテロ」でデズデモーナが歌う「アヴェ・マリア」では、歌の背後に死を悟ったかのような静謐さが漂っているようだ。「ヴェーゼンドンク歌曲集」はダヴィドセンの代名詞のような作品。さすがにずっしりと聴き応えのある演奏だ。録音は2020年8月、10月。新型コロナウィルスの感染拡大で、ロンドンはロックダウン。困難もあったと思うが、それだけに演奏するメンバーには心に期すものがあっただろう。大切にしたいアルバムだ。それにしてもダヴィドセンの声が圧巻だ。録音では、ピアニシモのデリケートなニュアンスからグーンと立ち上がる声の実在感を鮮明にとらえているので、とくに高音域に駆け上がったときの強烈な倍音の再現は、オーディオ・システムにとっては超ハード。ついスピーカーに近寄って「おい、大丈夫か?」とトゥイーターに向かって労ってやりたい気持ちになってしまった。

1992年にロッテルダムで開催されたE.フリプセ国際コンクールで優勝し、ヨーロッパの各都市でコンサートを行なっていたイリーナ・メジューエワが、活動の拠点を日本においてから四半世紀。バロックから近・現代まで幅広いレパートリーを手がけ、録音したアルバムも多いし、評価も高い。ベートーヴェン・ソナタ全集をはじめ、ショパンやラフマニノフ、メトネルもいい。それらの中で大好きなアルバムを2種。チャイコフスキーとグリーグの作品集だ。メジューエワは若い頃からテクニックはあるのに、だからといって勢いにまかせて弾くタイプではない。叙情的であっても過剰に没入したり、作為的な弾き方をすることもない。「あるがまま」という言葉があるが、作品の持つ美しさや和音から立ち上る豊かな薫りを繊細なタッチで表現する……まるで何もしていないかのように弾く。じつは、これが難しい。チャイコフスキーのアルバムで弾く「四季-12の性格的小品」は、なかなか「これ!」という演奏に出会わない。シンプルで愛らしい曲が並んでいるだけに、テクニカルになってしまうと興ざめだし、小細工はもっと困る。「1月 暖炉のそばで」では穏やかな時間の流れが心地よい。「5月 白夜」は高音域が美しい。音色で白夜の空気感を表現してしまうのだからすごい。「6月 舟歌」や「10月 秋の歌」もいい。誰もが知っている「11月 トロイカに乗って」の軽快で優しいテンポの何と魅力的なことだろう。グリーグのアルバムでは「抒情小曲集」からよく知られた曲が16曲。「アリエッタ」の出だしを聴いただけで「ああ、いいなー」とつぶやいてしまう。それぞれの曲が無理なくつながり、単調にならないように配列されていて、じっと聴き入っているととても気分がよく、「トロルドハウゲンの婚礼の日」の愉しげなリズムが鳴るあたりにはすっかり癒やされている。さらに「ソルヴェイグの歌」など歌曲からの編曲が5曲。グリーグが描こうとしたスカンジナヴィアの山や森や湖、そこを渡る風が音の情景として心に染み込んでくる。

 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。