注目タイトル Pick Up
ウィリアム・シャトナー a.k.a. カーク船長が齢90にして新作を発表文/國枝志郎

今月最大の驚きリリース。ウィリアム・シャトナー。そうです、SFドラマ / 映画『スター・トレック』のジェイムス・カーク船長役の人です。シャトナー氏、俳優としての顔がいちばん有名ではあるものの、SF作家やラジオDJとしての活動も続けており、そしてまたシンガーとしても1968年にデッカからボブ・ディランの「ミスター・タンブリン・マン」のカヴァーを含むアルバム『The Transformed Man』をリリースして以来10枚以上のソロ・アルバムを制作しているのだ。その共演者リストを見れば、それがたんなる俳優の余技という範疇を超えているのがわかるだろう。たとえばジョー・ジャクソン、ヘンリー・ロリンズ、エイミー・マン、エイドリアン・ブリュー、スティーヴ・ハウ、リック・ウェイクマン、スティーヴ・ヴァイ、アル・ディ・メオラ、イギー・ポップ、ブーツィー・コリンズ……おっと、これ以上書くとスペースがなくなってしまうのでやめておくけど、たとえば2004年リリースの『Has Been』は、ベン・フォールズがプロデュースしているというのも特筆しておきたい事実である。そんなシャトナー氏、コロナ禍真っ最中の2020年10月にロバート・ジョンソンやクリームなどのブルージーな作品からなるその名も『The Blues』をリリースして健在ぶりを示していたが、なんとたったの1年のインターバルでさらなるニュー・アルバムを用意していた。このバイタリティには恐れ入るしかない。この新作はバック・トゥ・ベイシックという風情でもあった前作『The Blues』と比べてもよりモダナイズされ、ロックありカントリーありジャズありクラシックあり、果てはヒップホップにまでアプローチするという攻めた内容。ゲストも豪華で、カントリー・シンガーのブラッド・ペイズリー、イーグルスのギタリストとして有名なジョー・ウォルシュ、ラップスティール・ギターの名手ロバート・ランドルフ、ラウンジ・リザーズのジョン・ルーリー、ジャズ・サックス奏者デイヴ・コズなど、ジャンルを横断した凄腕アーティストが大集結。プロデュースはニューヨークのアヴァン・ロック・バンド、ゼイ・マイト・ビー・ジャイアンツのメンバーで、『The Blues』にも参加していたダニエル・ミラー。本作はコロナ禍のためにミュージシャンは顔を突き合わせることなくさまざまな場所で録音され、それを最後にミラーがミックスしたという。全体的には非常にバラエティに富んだ、いい意味でバラけた音楽を、ひとつのアルバムとしてまとめたミラーの手腕は讃えられるべきだろう。アルバム・タイトルに自身の愛称を付けたということもあり、シャトナーにとってもこのアルバムは彼の音楽活動の集大成的な意味がありそう。齢90歳。彼にとって初のハイレゾ(96kHz/24bit)作品として堂々たる一作だ。

1991年3月13日の深夜、ベルリンのライプツィガー・シュトラーセ126番地にある地下室のドアが開いた。これが伝説のハード・テクノ・クラブ「TRESOR(トレゾア)」の始まりである。そのドアをくぐり抜けた者たちはやがてエレクトロニック・ミュージックの新たな地平を切り開いていくことになる。
同じ年に設立されたTRESOR RECORDSは、とくにアメリカの都市デトロイトで80年代後半に生まれたいわゆるデトロイト・テクノのアーティストの作品をリリースすることからスタートした。TRESORの記念すべき作品番号第1番(Tresor.001)が、X-101のハード・テクノなアルバムであることはとても重要な意味を持っている。X-101はデトロイト・テクノのハード・サイドを代表するユニット、アンダーグラウンド・レジスタンス(ジェフ・ミルズ、マイク・バンクスa.k.a.マッド・マイク、ロバート・フッド)の別名義。その後もTRESORはベルリンのアーティストとしてスヴェン・ルーリグの3Phase、のちにジ・オーブに参加するトーマス・フェールマンと元パレ・シャンブルクのモーリッツ・フォン・オズワルドの3MBの作品は別として、ブレイク・バクスター、エディ・フォークス、ジェフ・ミルズなどといったデトロイトのアーティストのハードな作品を次々に発表していくのである。TRESORのレーベル・カラーは、こうして“ベルリン=デトロイトの衛星都市”というイメージで語られるようになったのだった。
そんなTRESORが今年で設立から30年を迎えるというのはあらためて感慨深いものがある。今やテクノは特別なものではなくなったけれど、今でもテクノがアンダーグラウンドでカウンターカルチャーの代表だった時代のムードを色濃く残すTRESORというレーベルの存在感は圧倒的なものがあるのだ。そのTRESORが30周年を記念して巨大なセットをリリース。フィジカルでは12インチ12枚組、全52曲収録というすさまじい物量の大作である。この破格のボリュームはしかしTRESORという稀有なレーベルの歴史の重みと、未来への大いなる展望を考えれば必然であると思える。アンダーグラウンド・レジスタンス往年のハードな名曲「The Final Frontier」から始まり、未発表曲も交えながらベルリンの若き才能Mareena&JakoJakoのアンビエント・タッチな新曲「30 Perlen」で幕を閉じる5時間の旅。TRESORの歴史と未来をぜひハイレゾ(44.1kHz/24bit)で感じていただきたい。

この8月に伝説の1971年、箱根アフロディーテでの初来日公演の映像が『原子心母(箱根アフロディーテ50周年記念盤)』に収録されてオフィシャル・リリースが実現し、世界中のピンク・フロイド・ファンを狂喜させたこともまだ記憶に新しいが、間髪を入れずに今度はバックカタログが一挙にハイレゾで投入されて嬉しい悲鳴をあげている御同輩もさぞかし多かろう。そもそもピンク・フロイドは音源管理に異様に厳しいバンドとして知られていて、オフィシャルのアルバムと一部のベストやライヴ以外はなかなか世に出てこなかった。そうした傾向はハイレゾ・リリースにおいても同様で、たとえばフィジカルのハイレゾ版と言えるSACDのリリースも『狂気』や『炎』は一時出回っていたものの積極的な展開にはならなかったし、ハイレゾ・リリースとしては新規オムニバス『The Early Years, 1967-1972, Cre/ation』(2016年)と『The Later Years』(2019年)は除くとしても(どちらもハイレゾ化されている)、2014年の『The Endless River(永遠)』が同年に、1994年作の『The Division Bell(対)』が2016年にハイレゾ化されただけで、ほかのアルバムについては手付かずのまま残されていたのである。そんなファンの渇望が、ついに、ついに癒される日が来たのだ。大袈裟ではなくこれは大事件と言っていい。シド・バレットを擁した記念碑的なデビュー作『The Piper at the Gates of Dawn(夜明けの口笛吹き)』から1987年の『A Momentary Lapse Of Reason(鬱)』までのオリジナル・アルバムと1995年のライヴ・アルバム『Pulse』、そして意外なことにいくつかのベスト盤(『Relics(ピンク・フロイドの道、1971年)』『A Collection Of Great Dance Songs(時空の舞踏、1981年)』『A Foot In The Door: The Best Of Pink Floyd(百花繚乱、2016年。ただし同タイトルで選曲が違う編集盤が複数存在するので購入の際は曲目を確認すべし)』も含む合計17タイトルが今回ハイレゾ化。タイトルによっては192kHz版がなかったり44.1kHz版のみだったりするが、基本的にオリジナル・アルバムは24bitで48kHz/96kHz/192kHzの3種類のスペックでの配信となっている。それぞれ好みで選べばよいと思うが、波形をチェックするとサンプリング周波数にかなり忠実なリマスタリングがなされているようなので、できるかぎりハイスペックなデータで聴いてみていただきたい。SACD化もされている『狂気』に192kHz版がないのは残念だが、『原子心母』の192kHz版はまさに圧倒的!
チェリスト、ハリエット・クリーフの感情表現を克明にとらえた『Silent Dreams』文/長谷川教通
チェロは歌う楽器だ。シューベルトの「音楽に寄せて」「夜と夢」とチェロが奏でる“歌”を聴いていくとき、フッと深い想いに浸っている自分に気がつく。ハリエット・クリーフというオランダ出身の若いチェリストの音色は、何故こんなにも聴き手の心に響くのだろうか。彼女は幼い頃から歌が大好きで、眠りにつく前にはいつも祖母が子守歌のようにたくさんの美しい歌を聴かせてくれたという。悦びや哀しみ、憧れや痛みなど、人間の心にとって大切な感情の豊かさが、こうして育まれたのだろうか。13歳でチェロを始めたという。いまやチェロこそが彼女の内なる声を表現するかけがえのない存在となっているのだろう。アルバム・タイトルは『Silent Dreams』だ。静けさと沈黙、そして夢と憧れと想い出。ヨーロッパだけでなくアメリカやアジアのオーケストラからもオファーが舞い込み、2019年春からはアルテミス四重奏団にチェリストとして加わるなどハードなスケジュールをこなすクリーフだが、その表現はそんな派手なイメージとは正反対だ。内省的で、音色をコントロールしながら一つひとつの旋律に心を込めて奏でている。ピアノはロシア出身のマグダ・アマラ。ずっとデュオを組んでいる最良のパートナーとして、それぞれの曲の歌詞を徹底的に読み込みながら表現に反映させていったという。チェロとピアノのバランスに細心の注意が払われており、お互いの表現を大切にする意識が感じられる。アルバムの最後に置かれたR.シュトラウスの「朝」でのピアノの繊細な美しさとチェロとの親密な会話。ぜひ聴いてほしい。録音も秀逸だ。チェロ弦に弓を当てるときの位置を駒側に寄せたり、あるいは指板側に移動させながら微妙に音色を変化させ、弓圧を変えたりハイポジションを使って音の深みを表現する……そんなクリーフの感情表現を克明にとらえていて、これは感動ものだ。近接マイクで録った生々しさとは違う。響きの拡がりを取り込みながら、しかも微細な空気の震えを逃すことなく収録している。すばらしい。
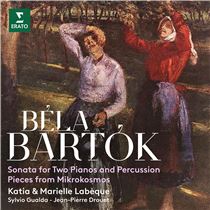
Katia & Marielle Labequeといえば、1970年代のクラシック音楽界でのスーパースター。日本でも姉カティアと妹マリエルによるピアノ・デュオ「ラベック姉妹」として、テレビCMにも出演するほどの人気ぶりだった。20歳前後の女性ピアニストが強烈なアタックで聴き手を刺激するのだから、70年代のアメリカン・ポップスはもちろんジャズだってこれほど鮮烈な音楽を発するアーティストはいなかった。それだけに音楽ファンには衝撃だったし、同時に新鮮だった。このバルトークのアルバム、録音は1970年だが、これがすばらしい。アナログ録音特有の太い音色……最新のデジタル録音だともっと楽器の輪郭が細かくて空間情報も入ってくるけれど、この時代の録音はピアノの粒立ちがよりクッキリとして塊のようになって迫ってくる。2台のピアノはクッキリと左右のチャンネルに定位し、おそらく左がカティアで右がマリエルだと思われるが、姉の硬質なタッチと先鋭感のある音色が鮮やかで、その奔放な動きにぴったりと息を合わせる妹。いくぶん抑えた表情ながら、バルトークならではのリズムが生き生きと表現されている。何より冴え冴えとした感性の煌めきが魅力だ。そして打楽器がすごい。シルヴィオ・グァルダといえば60~70年代の現代音楽シーンの最先端で活躍し、1968年からはパリ・オペラ座管弦楽団の首席打楽器奏者をもつとめたフランス打楽器界のレジェンドだ。またジャン=ピエール・ドゥルーエも打楽器奏者として鮮やかなパフォーマンスを繰り広げただけでなく作曲家としても活躍した名手。シロフォンのキーンと抜けるような高い音、バスドラのガツンとくる音圧感。これはオーディオ・ファンにとってはお宝と言ってもいい録音だろう。2021年、オリジナル・マスターテープからの192Hz/24bitによるリマスター音源だ。

1952年生まれのケント・ナガノ。もう巨匠と呼ばれていい年齢だが、どこかまだ若々しさが残っている。それって見た目?? いやいや、感性のことですよ。彼が近現代音楽を意欲的にレパートリーとしてきたからだろうか? そうかもしれない。アメリカの作品は言うまでもなく、つねに新しい音楽表現に挑戦し続けたからに違いない。バークレー交響楽団で28年間音楽監督を務めた後、ハレ管やリヨン国立オケ、ベルリン・ドイツ響にバイエルン国立歌劇場など、まさに世界を股にかけて活躍するケントさん。最近ではモントリオール響とのベートーヴェンやマーラー、バイエルン国立管とのブルックナーで高い評価を受ける一方で、北欧のエーテボリ響を振ったムソルグスキーの歌劇「ボリス・ゴドゥノフ」では演奏会形式ながら1869年原典版の全曲演奏をライヴ収録。その斬新なアプローチが話題となり、ハイレゾ配信もされた。つまり彼は特定のポストに執着したり、巨匠然とした評価に安住することなく、自分の意欲をかき立てる作品の演奏を実現させるオケとの共同作業を追い求めている。それが音楽家として生き様なのだろう。そんなケント・ナガノの十八番。それがメシアンだ。今回のアルバムではバイエルン放送響と組んで、2017年から2019年にかけて取り上げたメシアンのライヴ音源だ。まずは2017年の「我らの主イエス・キリストの変容」。とてつもない大曲&難曲で、5管編成の大オーケストラに100人の合唱と独唱、ピアノとチェロ、木管楽器、打楽器のソロが加わる。ピアノ・ソロはピエール=ロラン・エマールだ。これほど大規模な編成から発せられるメシアンの音をどうとらえればいいのだろうか。圧倒的な音の洪水か、それとも音がぶつかり合う不協和音の戦慄か。ケント・ナガノの指揮棒は、驚くほどの精緻さで響きをコントロールし、ソロを受け持つピアノやチェロ、そして木管の美しさ、打楽器の鮮烈な衝撃と抜けるような透明感をみごとに描き出す。メシアンの響きはけっして混沌ではない。鳥の鳴き声をイメージさせるピュアな音色、神秘的な合唱の美しさ。その背景に、2000年以上の年月が積み重なった宗教的な畏敬という精神性の深さを感じとることができる。名演だ。録音はとても純度が高く、大編成にもかかわらず響きはクリアで、合唱のひずみのなさも特筆ものだ。2018年の「クロノクロミー~大オーケストラのために」、2019年の「ミのための詩~ソプラノとオーケストラのために」を加え、CD換算3枚分の内容。ケント・ナガノのキャリアにおいて、もっとも重要なアルバムになった。

 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。