第2回 GUIROの髙倉一修と細野晴臣『omni Sight Seeing』を1位にして考える未来のザ・ベストテン
'
チャンチャカチャーン(古いタイプのファンファーレ)。『CDジャーナル』本誌で連載中の「未来のザ・ベストテン」、Web版第2回は本誌第3回のGUIROの髙倉一修が登場です!(ややこしい) 「この名盤を1位に置いて、いま、そして未来に聴いてもらいたいザ・ベストテン(2位から下)を考えよう!」というこの企画。今回、彼が1位に選定したのは細野晴臣が89年にリリースした『omni Sight Seeing』。電子音楽、ワールド・ミュージック、20世紀ジャズが独自のセンスで融合された傑作から発想したランキングとは?
'

髙倉一修(GUIRO)
――『omni Sight Seeing』の発売は89年7月。
「平成の始まりの年に、これが出てたってことは結構大きかった。80年代の細野さんのソロは、『S・F・X』(84年)を経て、そこからフレンズ・オブ・アースというユニットになっていった。フレンズ・オブ・アースは人とやってるものだったから、細野さんだけの作品という感じがしなくて。ソロ名義ではアンビエントもやっていたけど、当時十代だった子供の僕にはとっつきにくいものでした。そういう意味では、ひさびさに細野さんのソロとしての“何か”を感じるものだったんです」
――その“何か”というのはYMOやそれ以前の70年代のソロ作で感じていたようなもの?
「そうです。ただ、タイトルからして『omni』とついてるから、オムニバスを連想してしまい、自分で自分のコンピレーションを作ったような感じを最初に受けた。聴いてみるとその距離感をさらに実感して、これまでとはやはり違うなと。全体的なムードもどちらかといえば静寂でしたしね。でも、それから30年でものすごく聴こえ方が変わったし、よくよく振り返ると、折に触れて自分が音楽を聴く指針って、ここから得てるものがすごく大きいなと感じます」
――細野さんにとっても、この作品は“これ以前”と“これ以降”がクロスフェードした重要な作品だと思います。
「1位にした理由を自分でもいろいろ考えたんですけどね。僕がGUIROを休止していた時期(2009~2015年)は、曲作りではなく聴きたいと思っていたものを腰を据えて聴く期間としていて、なおかつ録音当時のレコードのサウンドで聴くことにも身体が喜ぶ感覚があって重視していた。その聴取の大きな柱として(デューク・)エリントンと(クロード・)ソーンヒル、クラシック、日本の民謡があったんです」
クロード・ソーンヒル
『Snowfall』
デューク・エリントン
『Caravan』
――それぞれ『omni』の根幹をなす要素ですね。
「そこには、古典に学ぶという側面が多分にあって、その道を示してくれたのがそもそも『Omni』だったと気づいて。それだけじゃなく、ここ数年も、TR-808の音色をこれぞという音で聴かせてくれる作品としても、“スーパーロー信仰”にとらわれない良いサウンドのリファレンスとしても、『Omni』は、ますます重要な盤だと思えてます」
――オリジナルのSP盤で聴くソーンヒルやエリントンが上位に入ってるのもその理由が大きい?
「ソーンヒルとエリントンについての認識が深まるきっかけはこのアルバムでした。ソーンヒルもブックレットに引用元として名前が記載されていたし。SP盤で聴くデューク・エリントンは衝撃で、〈キャラヴァン〉の最初の演奏のすごさもそれでわかった。〈キャラヴァン〉は最初はエリントン名義じゃなく、バンド・メンバーのバーニー・ビガードのグループとして前年に出したテイクがあって、細野さんの演奏はそっちを基にしてることが聴き取れます。そこにレス・ポールやジーン・クルーパ、ビリー・エクスタインとかを登場させたりしてる」
――ほかにランキングとして入ってくる作品としては、どういうものがあります?
「ジルベルト・ジルがコンテンポラリー・ダンス集団のグルーポ・コルポのために作ったアルバム『Gil』は、詳細はわかりませんが彼を題材にしたダンスのサウンドトラックのようです。ジルがスタジオで指示を出し音が作られ、それがダンスに反映されていく様子がYouTubeにも上がってます。細野さんの打込み楽曲の特徴である抑制されたグルーヴ感、明るいトーンと呪術的なものの同居をこの作品にも感じて、とても近い感覚で聴いてるかな。シャソールはまた別の観点。『Omni』ってパリで録音もしてるという要素が結構大きいんです。パリでは89年がフランス革命からちょうど200年の節目だったことから細野さんは〈Laugh-Gas〉を着想したそうだし。パリ在住の音楽家シャソールは、フランス革命以前の植民地支配でマルティニークに連れてこられたクレオールの末裔でもある。彼のアルバム『BIG SUN』は、故郷マルティニークの映像素材をユニークな手法で音楽的に再構成していて、ダーウィン進化論とスティーヴ・ライヒのミニマリズムが通奏低音にある重層的テーマの作品だそうです。ライヒに強く影響を受けているというのも細野さんとの共通項かな。アプローチはまったく違うけど、この2人が『Omni』の頃に邂逅するという世界線が存在していたとしたら……と妄想してしまう」
ジルベルト・ジル
『Gil』
――音楽作品以外だと、どうでしょう?
「宮澤賢治の短編童話〈貝の火〉とか。細野さんが『銀河鉄道の夜』(85年)のサントラにすでに『Omni』に至る曲想の変化が出ているというのもあるし、『Omini』に入ってる〈PREOCENE〉という曲は『銀河鉄道の夜』に出てくる賢治の造語“プリオシン海岸”がモチーフだったりする。僕自身は賢治の世界にはまだ入門したぐらいの感じ。これからの人生で時間をかけて読んでいきたいと思う人。この〈貝の火〉は、比較的昔から読んでいてすごく好きなんですよ。ある意味めちゃめちゃブラックだし、無常。〈PREOCENE〉からの連想でいえば、まだレコーディングされたヴァージョンは聴いてないけど、ceroの髙城晶平くんのソロ・バンド“Shohei Takagi Parallela Botanica”がライヴでこの曲をやってますよね。それもランキングに入れたい。髙城君の言葉のセンスにつねづねすごく惹かれてるし、彼も思うところあってカヴァーしてると思うから、そういう意味で(※後日談:リリース後、もちろん聴きました。すばらしいカヴァーでした)」
細野晴臣
『銀河鉄道の夜』
――そろそろランキングが出揃ってきました。
「人物が入っててもいいんですよね? だったら、ルドルフ・シュタイナー(神秘思想家/哲学者/教育家)を入れたい。細野さんは昔からUFOや精神世界とか、ある意味男の子らしい感覚を持ち続けたまま大人になって、そこから創作のインスピレーションを得ていたようなところが強かったと思うし、『Omni』でも引用のなかにライアル・ワトソンやヴィルヘルム・ライヒなど神秘思想家的位置付けの人物が登場する。細野さんとシュタイナーにはとくに結びつきを見出せないんだけど、自分にとっての“目に見えない世界のことを知る存在”として僕は惹かれてます」
――ハーパース・ビザールも選んでますね。
「あのアルバムに入ってる〈ハッピー・トーク〉を選んだつもりなんです。あの曲、〈PREOCENE〉の一節“Walking through the door”のメロディとそっくりなところがあって、聴くたびにそれが思い浮かんでしまうから。細野さんの中のバーバンクが無意識に顔を出したのかしらと思うと楽しい」
ハーパース・ビザール
『Feelin' Groovy』
――なるほど、あの曲はもともとミュージカル映画『南太平洋』の曲だし、マーティン・デニーもやっていて、エキゾ趣味にもつながりますよね。すごく興味深いランキング!
「そして、自分の曲をランキングに置いてもよければ、『Omini』へのアンサーとしての〈三世紀〉なのかも、と思える節があるので末席に(※『A MEZZANINE(あ・めっざにね)』に収録)」
――あの曲は打ち込みであることも通じてるけど、時空を超える感じとか、鳥瞰で音楽のルーツをたどる感じとかもつながるかも。次点に選ばれてるホドロフスキーや南米音楽のコンピレーションも気になります。いつか別の場所で拡大版やってみてもいいのかも。
取材・文/松永良平
| 今回の未来のザ・ベストテン |
|---|
| 1位 | | omni Sight Seeing
細野晴臣 |
| 2位 | | Snowfall
クロード・ソーンヒル |
| 3位 | | Caravan
デューク・エリントン |
| 4位 | | Gil
ジルベルト・ジル |
| 5位 | | BIG SUN
シャソール |
| 6位 | | PREOCENE
Shohei Takagi Parallela Botanica |
| 7位 | | 貝の火
宮沢賢治 |
| 8位 | | ルドルフ・シュタイナー |
| 9位 | | Feelin' Groovy
ハーパース・ビザール |
| 10位 | | 三世紀
GUIRO |
| 次点 | | The Original Sound Of Cumbia: The History Of Colombian Cumbia & Porro As Told By The Phonograph 1948-79
VARIOUS ARTISTS |
| 次点 | | リアリティのダンス
アレハンドロ・ホドロフスキー |




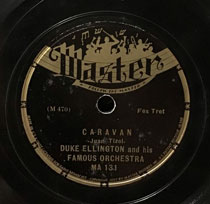
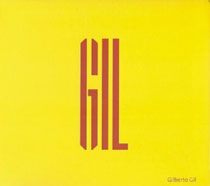
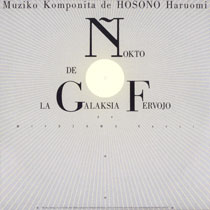
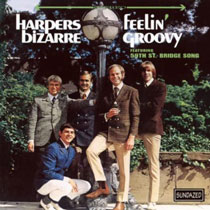
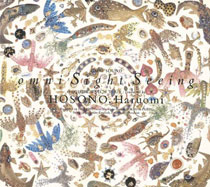


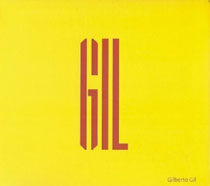


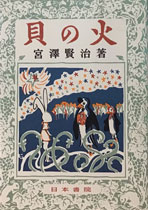

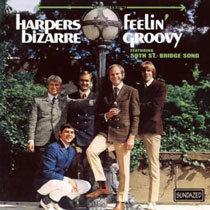
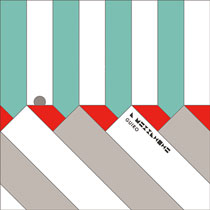

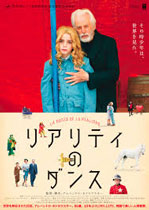
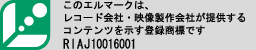
 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。